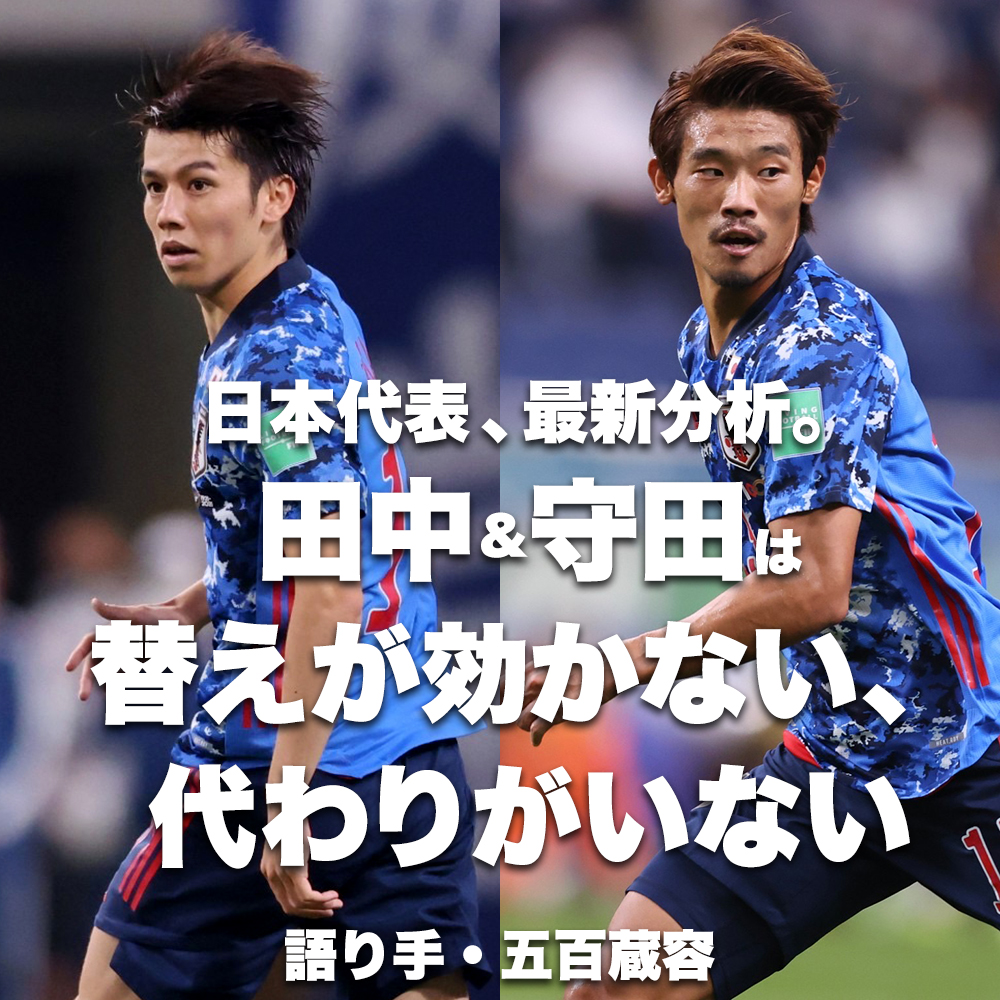
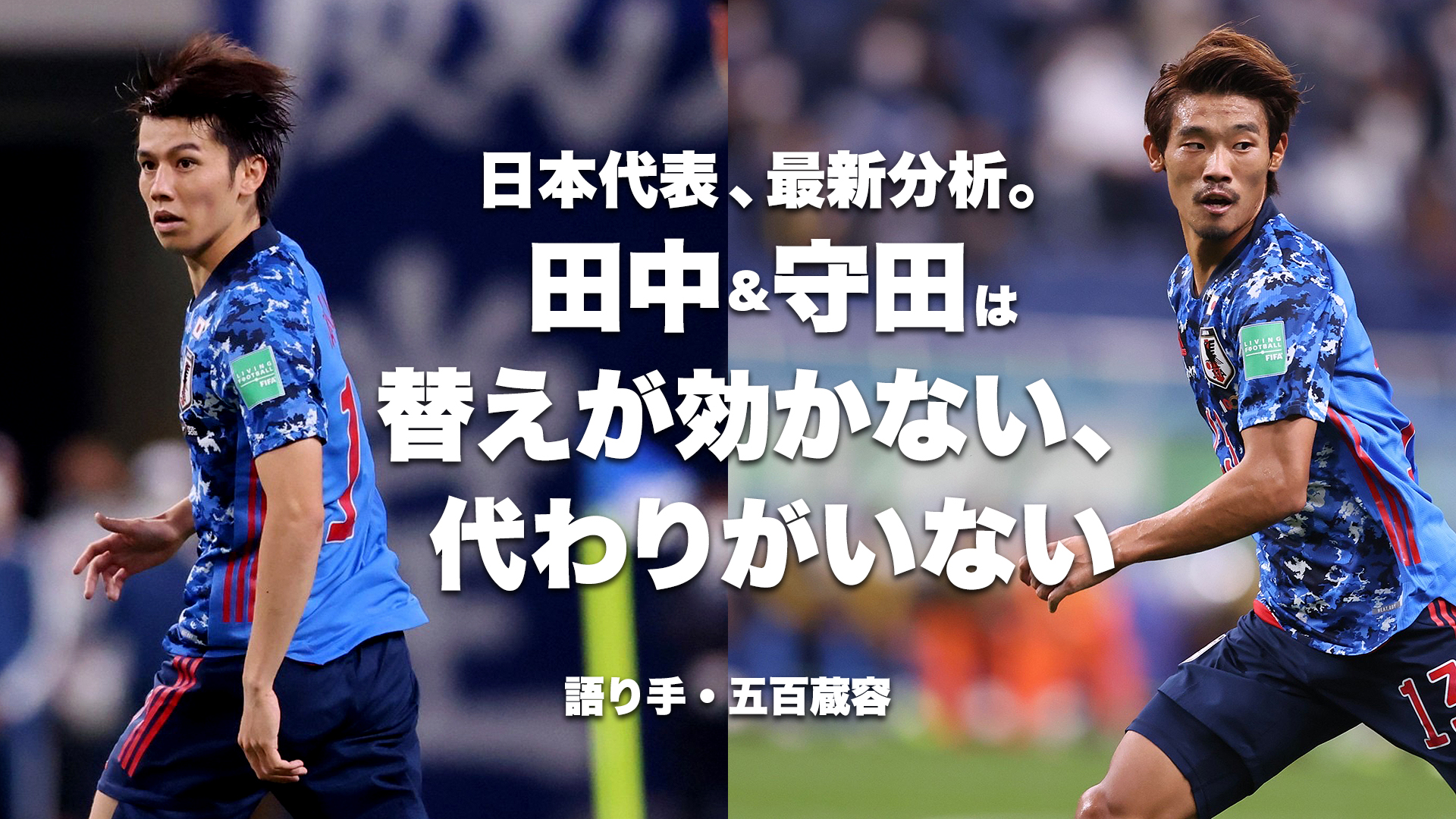
2022年1月27日、中国に2-0で勝利。続く2月1日、サウジアラビアにも2-0で勝利。ワールドカップ出場に向け、日本代表は5連勝でグループ2位をキープした。
この2試合を通して、4-3-3システムが高い精度を誇ったことや、それをもたらした田中碧、守田英正、遠藤航の中盤3人の機能性、そして伊東純也が圧巻のパフォーマンスを続けていることなど、日本にとってポジティブな結果だったことは間違いない。
3月24日には、自力でのW杯出場の期待がかかる運命のオーストラリア戦を控えている。
アジア予選を定点観測してきたなかで、中国戦、 サウジアラビア戦で見えた、日本のリアルな現在地とはどこか。日本はこのままW杯へと突き進めるのか──。
分析家・五百蔵氏へのインタビュー形式で真意に迫る。
※インタビューは2月20日に実施しました
■目次
・インサイド中心の戦いはアジアで圧倒できるレベル
・初速と伸びの両方のスピードを使い分ける伊東純也
・「左サイド問題」を森保監督は気にしていないはず
インタビュー:北健一郎
構成:本田好伸
写真:高橋学、浦正弘
※記事内の表記
CH=センターハーフ
WG=ウイング
CF=センターフォワード
SB=サイドバック
CB=センターバック
DH=ディフェンシブハーフ
インサイド中心の戦いはアジアで圧倒できるレベルに
──2022年1月、2月の中国戦、サウジアラビア戦は、前回お話してもらったオマーン戦、ベトナム戦の延長線上にあるものでしょうか。さらにさかのぼると、ホームで戦った2021年10月のオーストラリア戦の延長線上にあると捉えていいでしょうか?
五百蔵容(以下、五百蔵) そうですね。4-3-3がある程度は形になってきた試合だと思っています。
──遠藤航がアンカー、田中碧と守田英正がインサイドハーフという形になりました。
五百蔵 最初の頃はやはり「やってみた」という感じが強く、4-3-3でインサイドハーフ2枚とアンカーよりも、3CHのようなイメージでした。中国戦前までは顕著だったのですが、WGとトップの選手との関係性は、インサイドハーフの2人がもう一つ、ケーススタディを詰められていない状態で、1列目と2列目が分断しがちでした。
それでも、基本的に日本はカウンターチームという話を前回もしましたし、それでも点を取れるので問題ありません。現段階で、アジアのレベルでは問題ないという感じです。これまでの試合では、その3枚のMFと前の3枚が有機的に絡めていませんでした。本来の4-3-3で期待されるものを出せていないなか、伊東純也、南野拓実が走り回っている状況。そこがかなり詰められていたな、という2試合でしたね。
試合のなかで「できたときもある」ではなく、後ろと前が絡みながらきちんとタスクとして回るようになり、大迫勇也と南野がさらに活きるようになりました。特に大迫が機能した。「大迫のいるチームはこうしたほうがいい」という形がようやくできていた印象です。というのは、インサイドハーフのエリアにおいて、インサイドハーフが相手のボランチに対して、視野に入る、入らない、右に立つ、左に立つと気にさせつつ、裏側に入って相手のCBを止めようとしたりすることで、大迫の自由度がかなり増しました。大迫が孤立して、CBをつけておけばOKという対策が通用しないレベルになったということです。
日本の場合、WGはワイドの選手がインサイドに入ったりワイドに行ったりするタイプが多いですが、田中・守田がインサイドハーフらしい仕事を存分に行えるようになったことで、南野も自由を得られるようになっていました。その際、遠藤、田中、守田の3枚は、役割を変えながらぐるぐるとポジションを入れ替えて、自分たちの仕事を相手につかませないようにもしていました。
CFが引いた際、入れ違いにSBとCBの間に入る動きなどをしたときも、インサイドハーフとアンカー間のバランスをとる意識も高く、インサイドハーフ2枚がアタッカーと絡んで行っても、奪われたときのためにもう1枚が備えている形ができていました。3センタータイプだったときとは異なり、本来の役割を担いつつポジションの循環性を出せて、さらに付随してアタッカーも相手のマークを逃れる形ができていたので、かなりいいなという感じでした。

──大迫が活かせるようになったのは、つまりインサイドハーフのなにがよかった、と。
五百蔵 第一に立ち位置です。田中と守田の2人のうまさ。中国もサウジアラビアも、相手ボランチは2DHで日本のインサイドハーフを見ていましたが、日本も同じように相手を見るので、まずは対面に立つ状況でした。そこで、相手の視野から外れきらないような“くさい”立ち位置を取る。そうやって、視野の端っこあたりに移動したり、前に戻ったり、気がついたら裏に入るような立ち位置のチェンジを繰り返します。
彼ら自身がそうしたいというより、ワイドの選手や大迫、田中であれば守田、守田であれば田中が、それぞれ相方となるインサイドハーフの位置をちゃんと確認しながら、自分がそこに立つことで仕事をしていました。CBと2DHがその2人を見ることになることで大迫が動けるようになり、SBの注意も引くようなポジショニングをするので、伊東が裏に出ることも効果的になった。田中と守田が、アタッカーの立ち位置をうまく調整していました。
あの2人は基本的にそういう選手なので10月のオーストラリア戦からそういうプレーをしていたのですが、周囲との相互作用ができるようになってきたということですね。「田中、守田がいる」ということを、明らかに日本が共通理解として持つようになりました。
4-3-3のシステムが期待通りに相手選手を動かせるようになっているので、中国やサウジアラビアのように、4バックのチームは非常に守りづらいでしょうね。インサイドハーフを中心に押し込んでいく日本のやり方は、アジアレベルでは特に、2バック(4バック)では相当に際立つ強さを示せるようになっていると思います。

──チームの方向性が確立し、いい流れができてきているということですね。
五百蔵 はい。ただし問題は、その相互作用は田中と守田しかもたらせないということです。他の選手がそこに入っても、基本的には機能していません。中国戦の終盤も、選手交代でインサイドハーフに久保建英が入りましたが、その役割はできません。そう考えると逆に、彼ら2人が使えなくなった場合にピンチだなという感じがします。それに、機能性は上がったとは言え、だから点が入るというわけではないことも事実としてあります。
初速と伸びの両方のスピードを使い分ける伊東純也
──日本の得点シーンを含め、伊東が絡む割合が相当増しています。それは個人能力の高さによるものなのか、チームとして彼を活かせる形になっているということなのか。
五百蔵 森保監督のチームという意味では、両方だと思います。以前の原稿でも“委任戦術”を明言してきましたし、選手ファーストの構築ですから、選手を活かすための組み合わせがベースにあります。伊東は明らかにカウンター向きの選手ですから、彼を使って日本の特徴を出そうとするならば、必然的に伊東頼みのチームになります。実際、サウジアラビア戦も、中国戦も明らかなように、ヨーイドンの勝負では相手はついて来られません。

サウジアラビア戦の1点目の南野の得点も、こういうWGがいればこれができるよねという形でした。スルーパスに伊東が抜け出して、ファーで仕留めるという。
それに、伊東は足の速さがクローズアップされているなかで、特にヨーイドンの初速と、ロングスプリントの最後の伸びの両方を持ち合わせています。つまり、戦術的にも使い勝手がすごくいい。相手と駆け引きができますからね。中国は伊東にスタートを切らせないように張り付いた守備をしていましたが、伊東は相手から少しズレて立つことで勝負しました。
あれもカウンター状況でしたが、あえてマイナス方向に離れてからスタートを切ることで「助走」距離を稼ぎ、初速から伸びていくフェーズで相手を完全に抜き去りました。本人も自らの特性を理解して使い分けていますし、チームとしてもそれを理解した組み立てを意識しています。
──日本の大きな武器である「伊東のスピード」は初速と伸びの両方があるんですね。
五百蔵 そうですね。しかも、立ち上がりのスピードをエリア内でも活かせるようになっていますし、周囲もそこを使うようになっています。オマーン戦で三笘薫の突破から伊東が決めたときも、中国戦で中山雄太のクロスに合わせたときもそうでした。あれは、ボックス内にいて、相手の視野外から初速で一気に前に入って決めています。昔の伊東からは考えられないようなプレーです。チームもその特徴を理解しているからこそ、大外にいる伊東を選択肢にできていて、スペースがない状況でもあの場所に“置く”クロスを出せるわけです。
そのまま大外ではなく、あえて中に入れるほうを選べることは、相当ポジティブだと思います。もちろん、伊東でしか取れていない点は評価が分かれるところではありますけど。
──伊東は本来ウインガー特性ですが、最近はインサイドでボールを受けるバリエーションも見せています。プレーの幅を広げている印象でしょうか?
五百蔵 それは感じますね。インサイドハーフの仕事を、チームとして表現できていることの表れだと思います。ワイドの選手とインサイドハーフが連動して、相手ボランチの間のハーフスペースでどんな動きをするかによって、トップの選手もワイドの選手も自由になれる。そういう動きをチームとして共有して、体現できているということかなと。
先ほどからお伝えしているように、田中と守田しかできないということを除けば非常にポジティブですし、インサイドハーフのところで相手に奪われない、キープできるという状況は相当に脅威だと思います。
「左サイド問題」を森保監督は気にしていないはず
──もう少し伊東の話を続けますが、伊東を起点とした右サイドからの得点が多く、攻撃も偏っています。中国戦を終えて「左サイドが課題」という指摘もメディアで報じられています。どうしてこのような構造になっているのでしょうか?
五百蔵 おそらく、森保監督は、どちらかに偏るといったことは正直、どっちでもいいと思っているのではないかなと。攻撃のあり方としては割と、昔のアトレチコ・マドリードのように片方のサイドだけで攻撃を完結される感じではなく、実は両サイドを使っています。決めているのが伊東、アシストが伊東ということだけ。伊東からのクロスには外側の選手が入ってきていますし、インサイドハーフも裏抜けしておとりになる形も出来始めています。どこで決めるかで偏りが生じていますが、そんなに気にしていないと思いますね。
とは言え、南野にもっと決めてもらわないと、というのはあると思います。決められるチャンスは作り始めていますからもう少し仕事ができるはずです。そこは、SBの選択とも関係するので難しい部分ですけど。右サイドのほうが攻撃的に振る舞っていますし、伊東を使う以前の柴崎岳のときから、基本的には右サイド偏重のビルドアップでした。

──伊東ではなく、堂安律を起用していたときなども。
五百蔵 そうです。もちろん、左WGや左SBの攻撃面での課題もありますけど、逆に日本の右サイドからの失点もあるわけです。これは、清水英斗さんが書いていましたが、今は中山よりも長友佑都が選ばれています。ですから、左SBは“そういうこと”にしていると思います。守備面のファーストチョイスが長友であって、試合が進み深い時間になってきたら中山と交代する。その点でも、中山の投入時間が早まっていることは一つのメッセージだと感じます。彼は対人やコミュニケーションで課題が指摘されていますけど、もう少し早い時間から入って、周囲とコミュニケーションをとって、彼の特性であるビルドアップにもっと関与してほしい、という。森保監督の信頼が少しずつ増していることがわかる起用ではないかと思います。
──左サイドは、森保監督が総合的な判断で長友を選んできた。
五百蔵 はい。攻撃もフィニッシュも決して左が機能していないわけではなく、両サイド共にエリア内に侵入できているなかで、得点やアシストが右に偏っているということですね。
これ自体は、もう少し続くように思います。インサイドハーフの機能性が上がっているなかで、守田が左から頻繁に裏抜けを狙っている様子もありますから、もう少し左右の厚みを出して、バランスを取っていくという見立てがあるのではないかと感じています。

──いわゆる「左サイド問題」は、良い悪いではないということはわかりました。とは言え感じるのは、両WGの立ち位置の違いです。伊東はワイドを活用しますが、南野は限りなく中に立っていて、CFに近いようです。それは南野の特性か、チームの狙いか。
五百蔵 まずは、南野の特性だと思います。ただし、4-2-3-1のときのトップ下にどんな仕事をさせてきたかという点を考える必要があります。南野がサイドではなく、1.5列目で出ていた事例を考えてみると、左右のワイドの選手の特性を変えておく狙いを感じます。
というのも、インサイドに入った選手の仕事はある程度決まっている節があります。三笘が途中からしか使われない理由もそこにありそうです。つまり、プレスバックです。ワイドでも、インサイドでも、プレスバックしないといけないし、繰り返さないといけない。そう考えたときに、奪えそうなところで奪い切れる部分では、南野が選ばれるはずです。
彼はリバプールでも似たようなトレーニングをしていて適性とうまさがありますし、チームが要求するタスクにも合っています。4-2-3-1ではトップ下がその仕事をしますけど、インサイドに絞って1.5列目に入るワイドの選手にも、同じようなことが求められています。
こうした前提を踏まえ、4-2-3-1より、今の4-3-3のほうが良くなっています。インサイドハーフと、インサイドに入ったワイドの選手が連携を取って相手を挟んだり、プレッシャーを与えてディレイしたり、取り切ったりできているので。結局、肝はインサイドハーフなんです。

──なるほど。
五百蔵 南野がインサイドに絞ってトップ下やセカンドストライカーの位置に入ることでトップのアタッカーを自由にさせやすいですし、SBとの絡みでも、インサイドに入った前の選手がちゃんとプレスバックに来るだけではなく、SB選手自身も意外とインサイドに入ってきてインサイドハーフの裏のスペースを守っているシーンを見ることがあります。森保ジャパンの傾向の一つですね。
SBのそういった仕事は4-2-3-1のときからあったものの時々ある程度で、メカニズム化されたものには感じませんでした。選手の個々の判断でそうしている委任戦術として、というか。でも、4-3-3になってから、特にサウジアラビア戦と中国戦ではその狙いが顕著になっていました。
右SBの酒井宏樹も左SBの長友も、日本のボール保持時にインサイドハーフがめちゃくちゃ動くので、0.5列上がって絞り、インサイドハーフが動いて空いたスペースや、単純にインサイドハーフの裏を守るシーンが目立ちました。カウンタープレスの対応が整理されたということだと思います。インサイドレーンのプレスバック、間に入ったインサイドハーフと、その裏のインサイドに入るSBの形がかなり整い始めています。
──特にカウンター対応という点で守備面の成熟も増してきている。
五百蔵 かなりまとまってきていると感じます。点を取れていないだけですね。それこそ、中国戦は4点くらい取れるだけの力の差はありました。インサイドハーフを使うシステムの練度は、相当に上がっていて、かなりいい感じです。だからこそ、次のオーストラリア戦はそこが眼目ではないでしょうか。相手が4バックであれば相当、守りづらいと感じるはずですし、日本が先制した場合、かなり敵陣で支配しながら進められると思います。
ボールを握り、押し込みながらも崩しきれないかもしれないですけど、それも織り込み済み。森保監督は、相手をどんどん崩す狙いではなく、今やってきていることも、東京五輪でも、それ以前でも共通してやってきたのは「なるべく敵陣で過ごす」こと。それによって、勝つ可能性を少しずつでも上げるという考え方を明らかに感じることができますから。
──なるほど。では、運命のオーストラリア戦の展望は次回、お伺いします!
▷分析家・五百蔵容の論考
- 2021.9.2|変数か、定数か。分析家が論じる、東京五輪に見る日本サッカー
- 2021.9.29|日本代表の弱点は、「試合が始まってから考えている」こと。
- 2021.11.10|柴崎のミスは、森保“委任戦術”の必然?変化に対して脆弱な日本
- 2021.11.11|森保監督は、「コンディション問題」を選手に解決させている?
▷分析家・五百蔵容へのインタビュー
- 2021.12.17|活路は“必然の誘発”にあり?日本代表の伸びしろと限界値
- 2022.3.22|中盤の最強コンビ、田中&守田は替えが効かない、代わりがいない
- 2022.3.23|“史上最高の状態“の日本は、W杯出場へ勝負に出る?慎重に戦う?
▷プロフィール
五百蔵容(いほろいただし)
1969年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部を卒業後、株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガゲームス)に入社。2006年に独立・起業し、有限会社スタジオモナドを設立。ゲームを中心とした企画・シナリオ制作を行うかたわら、VICTORY、footballista、Number Webなどにサッカー分析記事を寄稿。著書に「砕かれたハリルホジッチ・プラン 日本サッカーにビジョンはあるか?」「サムライブルーの勝利と敗北 サッカーロシアW杯日本代表・全試合戦術完全解析」(いずれも星海社新書/2018年刊)がある。
Twitterアカウント:@500zoo
Follow @ssn_supersports




