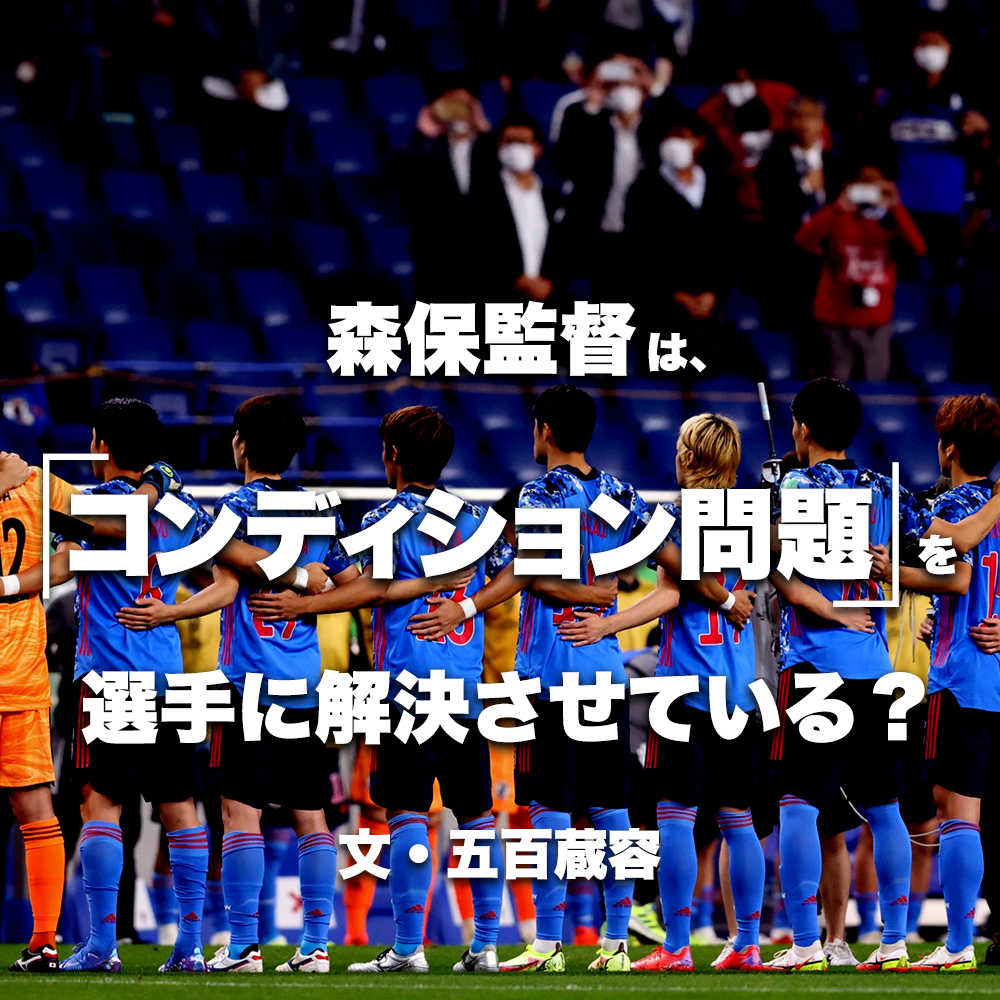
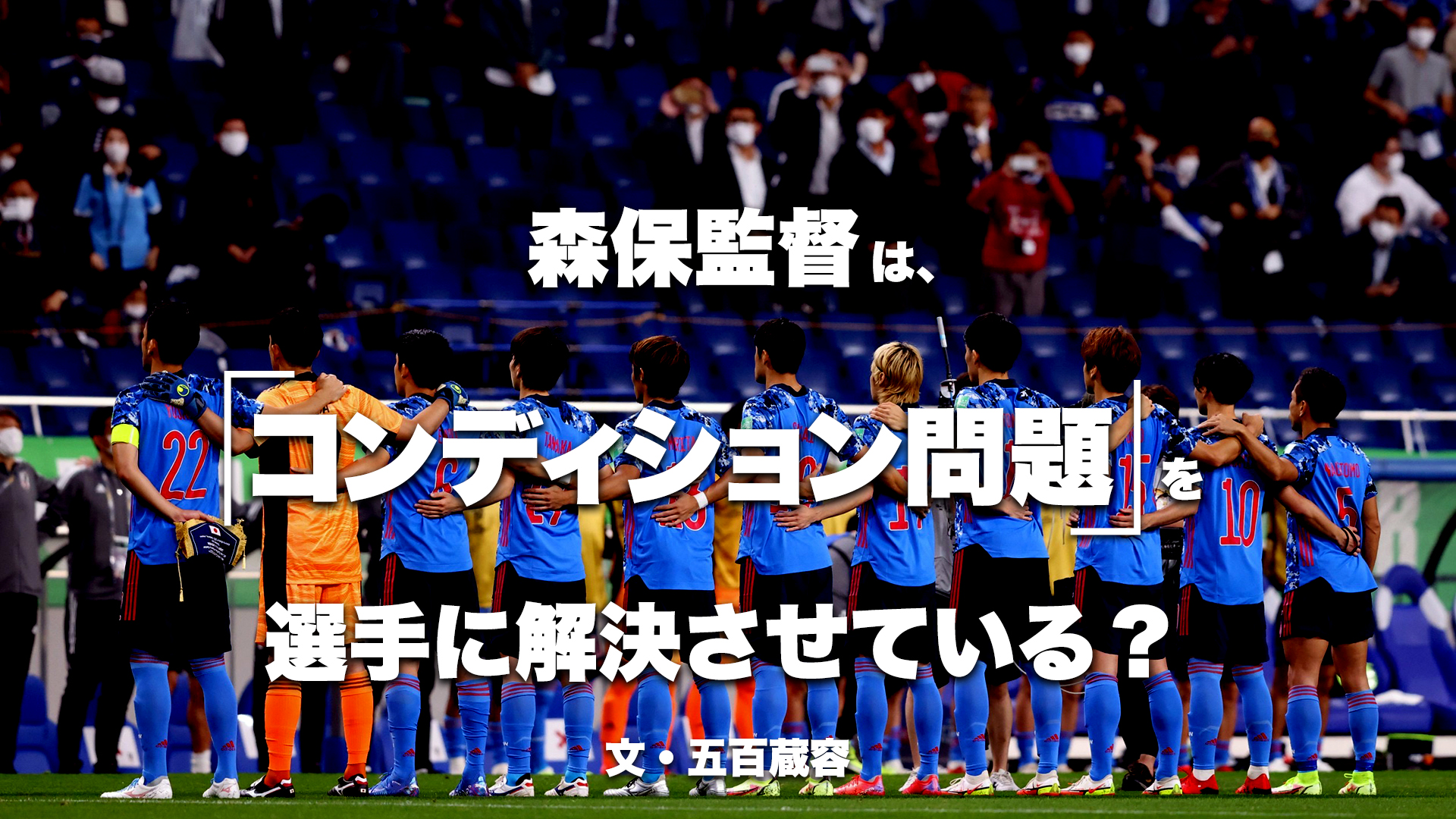
■目次
・オーストラリアを事前分析した日本の人選とタスクセット
・日本のゲームプランを狂わせたオーストラリアのムーイ
・日本:ゲームプラン空転=豪州:許容範囲のリスクが深刻化
・「結果」が出たものの「判断のまずさ」も相当数あった
文=五百蔵容
写真=高橋学
※記事内の表記
CH=センターハーフ
DH=ディフェンシブハーフ
OMF=オフェンシブミッドフィルダー
WG=ウイング
CB=センターバック
SB=サイドバック
SH=サイドハーフ
2022年カタールワールドカップ・アジア最終予選第3節、日本は敵地でサウジアラビア代表に敗れました。内容的にはかなり入念な準備の存在を感じさせるものであった一方、肝心の委任戦術──「ピッチで判断し、対応していく」──については難しさが露見し、まさに「対応できなかった」ところで決勝点を奪われたことは残念であり、このチームの現在地を示すものでもあったと思います。
具体的な様相は前回記事で詳述しましたが、この敗戦を受けて第4節のオーストラリア戦は文字通り「負けられない戦い」となり、これまでフォーメーションレベルでは目立った変更してこなかった森保監督に大きな決断をうながしたようです。
オーストラリアもまた、いつもとは異なる、対日本戦用の特別な仕立てをもってこの大一番に臨んできました。その結果、日豪お互いの狙い、思惑がすっきりとは噛み合わないなか、その状況を打開するための様々な試行錯誤が両チーム間で繰り広げられるという、ある意味サッカーらしい、ビッグマッチらしい面白いゲームとなりました。
本稿では、そのオーストラリア戦を通じ「委任戦術」がどのように機能し、またおよばなかったかという点に注目し、日本代表の現状について考えてみたいと思います。
オーストラリアを事前分析した日本の人選とタスクセット
この試合、日本は田中碧、守田英正をインサイドハーフに起用、アンカーを遠藤航とした3CHを中盤に展開する4-3-3のフォーメーションを選択しました。4-2-3-1を基本とするオーストラリアの2DH+1OMFの中盤に対し、ちょうどピタリとマーキングが合わせられる布陣です。また、試合が始まると判明したとおり、南野拓実と伊東純也の両WGは、守備時には中央に絞ってハーフスペースを閉じる、もしくは相手のCBとSBの間のコースに位置し、CBとSBどちらにもプレッシャーをかけられるうように備えていました。
特に前半、日本は中央に絞った4-3-3のままミドルゾーンで守備ブロックを形成しながら押し上げていく形を多く見せており、オーストラリア代表の基本フォーメーションやビルドアップに対してプレッシングを仕掛け、寸断可能なプランを立てて試合に入ってきたことが感じられました。

オーストラリアを分析すると、ボール保持時にDHが両サイドに開くシーンが目立ちます。自らも相手のプレッシングをかわしつつ、空いた中央のスペースを自チームの別のポジションの選手が使い、相手のプレッシングの深度を惑わす(ラインを降りていくオーストラリアの選手にどこまでついていくべきか考えさせるなど)ことで、ボール前進をスムーズにするメカニズムにこの行動は結びついています。
オーストラリアはポジショナルプレー基盤のバリエーションをいくつも保有しているチームですが、このDHのポジショニング移動によるビルドアップルートの創出はその中でも重要なものの一つと思われました。日本はインサイドハーフのいるフォーメーションを採用することと、守備時のWGのポジショニング・タスク設定によっておそらくその形にも対応する計画だったと思われます。
相手の2DHにこちらの2インサイドハーフをマンツーマン気味に当てながら、WGのポジショニングでCBから外側に逃げるパスコース、ハーフスペースを通すパスコースを奪いビルドアップを詰まらせる。そのような場合オーストラリアはロングボールを相手のDFラインとDHラインの間に落とし、セカンドボールに対しカウンタープレスをかけることで敵陣でボールを確保するパターンを持っていますが、4-3-3であればアンカーの遠藤航が残っているので、バックラインの吉田麻也・冨安健洋との連携で自由を与えない。
オーストラリアDHがサイドに開いても、WGのポジショニングが彼らへのパスコースを阻害、あるいは彼らに直接プレスバックをかけられるようにあらかじめ設定されている上、インサイドハーフが中央からハーフスペースを固めているので、レーン間・ライン間を移動するオーストラリアのポジショニング変換、ビルドアップルート変更に柔軟に対応できる……サウジアラビア戦と同じく、しっかりとした事前分析と準備を反映した人選とタスクセットに加え、委任戦術により鍛えてきた、ピッチにいる選手たちの判断力、対応力で勝ちきれる。そういった思惑だったのでしょう。
ただし、オーストラリアがやり方を変えてきたこともあり、日本のゲームプランは試合開始直後から半ば解体され、修正を迫られます。
日本のゲームプランを狂わせたオーストラリアのムーイ
オーストラリアは、オリジナルポジションが4-2-3-1を形成するフォーメーションを取りつつ、そこから状況に応じて様々な陣形に変化してきます。日本戦では、左SHに1stチョイスのウインガー・アタッカー、メイベルではなくベテランのボールプレーヤー、13番・ムーイ(下の写真左)を起用することで、これまでの彼らの試合であまり見られなかったバリエーションを打ち出してきました。

ムーイはオーストラリアの遠藤保仁、中村俊輔といったクラシックなタイプのゲームメーカーで、状況に応じてピッチのあちこちに移動しながらビルドアップのリンクマンや逃げ場所を作ってボール保持をスムーズにしつつ、相手の守備の基準点を惑わせるのが巧みな選手です。相手の陣形、ポジショニングを見て逆手に取ることもうまく、いわゆる「サッカーを知っている」選手と言えます。
ムーイが起用されるときは4-2-3-1のDHの一角やトップ下が多いのですが、この試合では左SHでのスタート。通常、SHは比較的ポジショニング移動や稼動エリアが戦術的に限定されるポジションなのですが、ムーイは完全なフリーマン、サイドからスタートするもう1枚のCHとして起用されているようでした。
自チームの状況、日本の状況をうかがいながら中央に移動するだけではなく、DHのエリアに落ちたり逆サイドにまで進出したり、およそ中盤の選手が担いうる様々な動きを見せ、ミドルゾーンのほぼ全域に顔を出していました。
このムーイの存在と幅広いタスクが、日本のゲームプランを狂わせることになります。彼の動きは多彩かつ神出鬼没ですが、その役割は煎じ詰めればオーストラリアの3人の中盤に+1として加わり、日本の3枚の中盤に対して4枚を当て、恒常的に数的優位を得るというものでした。

つまり、この試合のオーストラリアは、ボール保持時に従前の4-2-3-1ではなく、4-2-2-2もしくは4-3-1-2と表現しうるやり方で入ってきたことになります。日本の4-3-3は、そのタスク構成を見てもオーストラリアが正三角形(トップ下+2DH)・逆三角形(2CH+1DH)どのように変化するにしろ中盤を3枚で構成することを前提とした選択だったので、試合開始の時点で「マークできない+1をどうつかまえるか」「+1が存在することで生じる諸問題にどう対応するか」という難問に早くもさらされることになりました。
日本:ゲームプラン空転=豪州:許容範囲のリスクが深刻化
結論から記すと、日本代表は「ムーイ問題」そのものには明快な解決策を見いだせないまま試合を過ごしていくことになります。そのため、左右のインサイドハーフが動いた後のスペースや、アンカーがサイドに動いた後、インサイドハーフやアンカーがオーストラリアのトップ下をケアしに動いた後のスペースに狡猾に侵入し、ボールを受けては前進させたり日本のプレッシャーからボールを逃がすムーイをつかまえることができず、オーストラリアが前進する局面をおそらく想定以上に多く許すことになりました。
さしあたり、それぞれの担当するゾーンもしくはレーンにフリーマン(ムーイ)が入ってきたら対応するという形でムーイを監視する、可能であればプレッシャーをかける、つかまえにいく対応を行ってはいます。けれども、オーストラリアは日本の守備に対してムーイが浮く、ということを利用したポジショニング循環を行っていたので、「ムーイに付いてしまったら他が空きそこを利用される」ということ、その状況の発生位置が自陣になってしまうことなどから慎重な対応を余儀なくされ、結果として「事実上の放置」ということになっている様子でした。
日本はこの試合、マーキングをバシッとハメ込んでオーストラリアから自由を奪うことをおそらく狙っており、とりわけ「2枚のインサイドハーフを2DHに当て、オーストラリアの心臓部にプレッシャーをかける」「オーストラリアDHエリアに常時プレッシャーを与える」、「そこでボールを奪ってショートカウンターで仕留める」ということを意図していたと思われます。
左右のWGがいわゆる「外切り」可能なポジションに付くシーンが少なからずあったのも、その可能性を高める措置だったでしょう。オーストラリアのビルドアップを内側に誘導し、そのボールを受けるDHにインサイドハーフが強烈なプレッシングをかけて奪い取り得点機につなげる。そうなれば、日本にとって理想的な展開だったはずです。
けれども、上述のようにムーイのタスクによって中盤のマークを噛み合わせづらくさせられたことで日本の計算は成り立たなくなってしまいました。
ただ、ここからがこの試合の面白いところ、見応えのあるところでした。“ムーイシステム”は、日本代表にとっては「用意したゲームプランが空転する」効果をもたらした一方、オーストラリアにとっては「許容可能と計算していたリスクがより深刻に顕在化する」といった状況が現出する要因にもなっていたように見えるのです。
ムーイが本来はSHが守るべきスペースを軽々と放棄してしまうため、オーストラリア陣左サイドに大きなスペースが恒常的に生まれることが避けられない状況だったのですが、インサイドハーフのいるフォーメーションを採用していたことによって、日本はショートカウンターの局面でもビルドアップする局面でも、4-2-3-1採用時よりもこのスペースをより素早く、より効果的に用いることができるようになっていました。
Jリーグで極めて機能的な4-3-3システムを採っている川崎フロンターレで主軸を担っていたこのポジションの名手・田中碧と守田英正を起用していたことも手伝ってそのようなシーンは前半からいくつも見られ、オーストラリアは思惑通りボールを握って前進でき、カウンタープレスも相応に機能させていながらも、日本の攻撃の脅威を減殺できないという戦況に陥っていたと思われます。

また、日本の4-3-3は人選的に3CH・3DHの陣形としても機能するようになっていたため
、ミドルゾーンのマーキングを曖昧にされ、スペースを暴露するリスクに対して、3枚のMFでバイタルエリアをブロックすることで「ムーイをつかまえられなくても、引いてスペースを消してしまう」というという選択を取る余地がありました。
おそらくピッチ上で下されたのであろうこの選択は、オーストラリアによりボールを、主導権をにぎらせるリスクを伴っていましたが、早い時間に先制できたこと、計画に沿ったミドルプレス、ハイプレスを機能させるのが容易ではなくなった戦況を考えると、悪くない判断だったと思われます。
総体的に見て、この試合はお互いの想定、事前の準備をそれぞれが異なる仕方で裏切るようないわゆる噛み合わない試合なっていましたが、その状況にお互いがお互いの強化方針に則ってどのようにアジャストしていくか、その試行錯誤に見るべきところの多いゲームだったと言えます。
オーストラリアは、彼らのポジショナルプレー基盤のメカニズムの強みを生かすような状況認知、事前に所持している引き出しを開ける速度などで対応していました。たとえば、彼らは前半3分と経たないうちに日本が4-3-3だということをチームとして認知し、守備時に4-4-2ブロックを組むときに最も4-3-3側に選択肢を与えない組み方を選択し、一定程度の安定性を確保しつつ、“ムーイタスク”の有効性を享受して日本陣に迫っています。
日本もまた、事前の計画とかなり異なるピッチ上の風景がおそらく見えていたなか、選手たちは「本来は中央に2枚のDHしかいないところに3枚いる」「中央の選手がサイドのプレッシングに思い切り参加していっても、中央から逆サイドに位置する選手が1枚ずつ付いて、中央のプロテクトや逆サイドを使ったカウンターに安全に移行できる」といった「4-3-3というフォーメーションが本来持つ特徴」を生かすという方向に舵を切り直し、ムーイの跋扈に戸惑い押し込まれながらも、いい場所でボールを奪い返し切り返すといった状況を手に入れてもいました。田中碧の先制点などは4-3-3に典型的なサイド追い込み→プレッシングからのショートカウンターを起点としたものでした。

「結果」が出たものの「判断のまずさ」も相当数あった
委任戦術の面からみて、オーストラリア戦はまずますの内容だったと考えることができます。「入念な事前準備が行われた」「それが効果的に働かない状況が生じた」という点ではサウジアラビア戦と似通っていましたが、早い時間に先制点を奪えたこともあり、オーストラリアがこちらの想定とかなり異なるやり方を取ってきたことに対して余裕を持って対峙できました。「お互いが想定外の状況に対応しなければならない」という戦況を見据え、自らが陥っている問題への的を絞った対応はできずとも、オーストラリアが被っている問題点には付け込めています。
その一方で、失点につながったシーンのようになかなか機能しないWGの外切りに試合を通じてこだわり続け、CBにつっかけたところをサイドにクリーンに通され、それをつぶしに長躯出た長友佑都が無効化されて裏を突かれるといった「判断のまずさ」も相当数の局面で見受けられました。
外切りの失敗からサイドをクリーンに前進される、長友の裏を使われる、というのは前半から繰り返されていたため、このシーンではオーストラリアのCBとDHは意図的に日本のWG(南野)が外切りプレッシングを引きつけてそういったシーンを作り出そうとしており、そのもくろみにまんまと乗せられてしまった格好でした。

こういった点は、サウジアラビア戦において露呈した委任戦術の穴と同じく、「一部のグループ間で共有されている判断と修正が、別のグループに行き渡るのに時間を要する」不具合かもしれませんし、だとすれば問題は手当されていないと見ることもできるでしょう。
サウジアラビア戦とオーストラリア戦という10月の2連戦は、最低限の結果を出しつつ、委任戦術の面では期待される柔軟性を見せられた試合・局面、見せられなかった試合・局面が比較的はっきりと見て取れるシリーズでもありました。「結果」が出たオーストラリア戦が顕著ですが、「柔軟性」を支えていたのが一部のポジションの選手の距離・回数共に突出したスプリントである点は注目していきたいところです。
これは現状仮説にすぎませんが、委任戦術上どうしても起こるエラー(10月の両試合で出たコミュニケーションエラーなど)を、そうした局所的に偏向して過大なスプリントの質量が埋めているのだとしたら、このチームに対ししばしば取り沙汰される「コンディション問題」とはチームのフィジカルなパフォーマンスだけでなく、委任戦術の遂行度にすら大きく影響するファクターなのかもしれません。
そういった点にも留意しつつ、11月のアウェー2連戦、ベトナム代表戦、オマーン代表戦をしっかりと観て、現在日本が選択しているやり方がどのような展望を開きうるのか、見据えていきたいところです。
▷分析家・五百蔵容の論考
- 2021.9.2|変数か、定数か。分析家が論じる、東京五輪に見る日本サッカー
- 2021.9.29|日本代表の弱点は、「試合が始まってから考えている」こと。
- 2021.11.10|柴崎のミスは、森保“委任戦術”の必然?変化に対して脆弱な日本
- 2021.11.11|森保監督は、「コンディション問題」を選手に解決させている?
▷分析家・五百蔵容へのインタビュー
- 2021.12.17|活路は“必然の誘発”にあり?日本代表の伸びしろと限界値
▷プロフィール
五百蔵容(いほろいただし)
1969年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部を卒業後、株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガゲームス)に入社。2006年に独立・起業し、有限会社スタジオモナドを設立。ゲームを中心とした企画・シナリオ制作を行うかたわら、VICTORY、footballista、Number Webなどにサッカー分析記事を寄稿。著書に「砕かれたハリルホジッチ・プラン 日本サッカーにビジョンはあるか?」「サムライブルーの勝利と敗北 サッカーロシアW杯日本代表・全試合戦術完全解析」(いずれも星海社新書/2018年刊)がある。
Twitterアカウント:@500zoo
Follow @ssn_supersports




