
変数か、定数か。分析家・五百蔵容が論じる、東京五輪に見る日本サッカー
スペインと対極にある日本サッカーの問題点と対策
ただし、問題が2つあります。
一つは、短期的・戦術的問題。
本戦で明らかになったように、このやり方はより厳しいコンペティションとなる決勝トーナメントでは特に攻撃面、チャンスメイクの質量と得点力に大きな不備が生じることを露呈しました。
バイエルン・ミュンヘンやリヴァプールのようにプレッシング、ブロッキングできたとしても、上述のように最終局面の攻撃に深さをしばしば欠き、特定の選手、経路やコンビネーションを抑えられたら得点力が極端に低下しています。
少ない手数でバーチカルに敵陣侵入する攻撃、2列目の機動性と即興的なコンビネーションに依存した攻撃だけでは限界があったのは明らかで、より脅威を与えうる最前線のアタッカー(CF)を組み込み、相手の中央DFへのペネトレーションと2列目の機動性を組み合わせた、より多層的で豊富なバリエーションの実装が最低でも必要になるでしょう。
また、ビルドアップ面で戦略性に乏しいことも問題でした。縦に速い攻撃が抑えられた時に、ビルドアップによって相手陣形に動揺を与える術がほとんどなく、逆にシンプルなビルドアップルートに計画的なプレッシングを受けチャンスメイクされる状態でした。
これは単に、中央にゲームメイカー、「司令塔」を置き巧みな配球をさせれば済む問題ではありません。チーム全体の動的なポジショニングの組み合わせで相手の陣形に繰り返し打撃を与え、計画的にチャンスメイクする戦略性が必要になります。
例えばスペイン五輪代表は、質の高いポジショナルプレーを実装することで相手陣形を破壊可能な戦略的チームプレーを披露していました。
その鍵は、一見して目につくCBの巧みな球出しや中盤の流動性ではなく、WGとCFの仕事を基盤にしたチーム全体のポジショニング調整にあります。
スペイン代表のビルドアップでは、ボール保持者周囲のポジショニング調整で誰かをフリーにする巧みさが目立ちます。そのフリーマンに対し守備側は即座に対応できません。両翼のWGのポジショニングによって DFラインの動きが制御され、そのことによって生じるバイタルエリアのスペースをCFや内側に入ってくるWG、インサイドハーフが使おうとしているため、守備側のDHやCBはどこをマークするか常に判断し、対応を変えなければならなくなるからです。
そのことで「最も危険なエリア(バイタルエリア)でマークが曖昧になる」状況をスペイン代表は継続的に生み出すことができます。そして、その波及効果として、自陣側へポジションを移動するインサイドハーフへのマークが困難となり、そのマークをはっきりさせようとすると高い配給能力を持つCBへのマークが足らなくなり、結果としてどこかがフリーになってしまうのです。
スペイン代表が演出するこの「曖昧さ」は一時的なものなので、守備側はマークの受け渡しを調整して対応することができます。ですが、彼らはそこで生じるわずかな時間を利用してボールを前進させ、瞬く間にチャンスメイクしてしまいます。
彼らが個として得意とする──日本をはじめとして世界中で手本と見なされている──ゾーン間のポジショニング、相手のプレッシングやマークを引きつけるプレー、ワンタッチで素早くボールを動かすプレーの組み合わせは、この構造下でこそ活用可能です。
森保監督の五輪代表のやり方は、スペイン代表のそれとある意味対極にあると言えます。
日本は、相手の陣形を復原的に破壊しうる全体的なポジショニング戦略によって主導的に相手の守備に繰り返し問題を起こしボールを前進させるのではなく、プレッシングとデュエルのポイントを特定・設計し、相手のやり方がそもそも持っているウィークポイント、それでうまれるスペースにあらかじめポジショニングし、それをチームとして共有することで素早く縦に前進しています。
特定のシチュエーションやエリアにおいては流動性を見せるものの、相手の陣形やゲーム全体の趨勢を主導的にコントロールするようなマクロな流動性を得られる方法ではなく、その「限定的な流動性」を把握されケアされると打つ手がなくなるのは明らかでした。
もし現在のやり方を突き詰めていくのであれば、今回ある程度「整理」したことで明確化したやり方の「幅」をもっと広く取る、このやり方の中で複数のバリエーションを持てるように向上させていく必要があるでしょう。
そこでは当然、「幅を狭く取ったから選手たちの自主的な判断がそろいやすくなっていたのでは?」「そこを広げていくと、その判断がそろいにくくなるのでは」という問題も生じるでしょうが、「選手たちが自主的に考え判断する」コンセプトを堅持するのであれば、いずれにせよクリアしていかねばなりません。

2つ目は、中長期的・戦略的問題です。
本稿で見てきたように、今回のU-24五輪代表はかなり整理・整備されたチームになっていました。だからこそ課題や現時点での限界も明確に見え、「これからどうしていくか」を議論可能な水準に日本サッカーを立たせうる内容と結果になったように思います。
今後もこのやり方を突き詰めていくのか、それともその限界を越えるため別のやり方にシフトしていくのか。本論考でも注目した具体的な特徴、長所、問題、限界を共通の基盤として議論を発展させていけるのではないかと考えます。
そこで改めて、日本サッカーの長期的発展の基盤として提出されつつも、その曖昧さがしばしば批判の的となる、「Japan’s Way」(ジャパンズウェイ)をどう捉えるかという論点も具体性を帯びていくのではないでしょうか。
日本人らしさを生かしたジャパンズウェイ
ジャパンズウェイの曖昧さは、あえて良い意味に捉えれば、サッカーというゲームそのもののもつ曖昧さ、時代と共に変転していかざるをえない特性、余白に適合しているとも言えます。サッカーネイションの一つであるイタリアでは、サッカーは時に「丈の短い毛布のようなもの」とたとえられます。寒さを凌ごうと頭を覆えば足が出てしまうし、足をケアすれば頭が寒風に晒されてしまう。どんなやり方も、戦術も、システムもフォーメーションも、とりわけこのスポーツでは完全な方策とはなり得ないことをうまく表した比喩と言えます。
それはつまり、このボールゲームでは特定の戦術、ゲームモデル、特定の思考傾向に拠ることそのものがリスクになるかもしれないということです。サッカーにとって、それらは変数でしかない可能性があるのです。ですから、変数に拘泥(こうでい)するよりも、どんな状況でも不変と見なせる定数、基質のほうに潜心(せんしん)する必要があるのでは? という考え方には一定の説得力があるでしょう。
ジャパンズウェイがその定数、基質になりうるのであれば、それを担保した上で折々の時代、世代にふさわしいやり方、トレンドをその都度キャッチアップし、変数として代入・実装していけばいいということになります。
それこそがジャパンズウェイの意義であって、その曖昧さは「どんなトレンドにも適合していける柔軟性」と同義なのだ、というのであれば、一定の筋が通っていると見ることもできます。以前の日本代表が目指していたように見える“スペイン風のボールポゼッション”も、森保監督が今回実施した(そして今後も実施するであろう)ハイ&ミドルプレスとローブロッキング、バーチカルなカウンター主体のやり方も、「日本人らしさを生かした」という枕詞を冠せば「ブレ」でもなんでもないということになります。
一方、この見方に拠るならば、日本サッカーは必要であればジャパンズウェイの上で、あらゆる変数──ゲームモデル、戦術、システム──を適時、常に、迅速に導入し、国際的な競争力を十分に持ちうるクオリティで実施可能な状態であるべき、ということになります。
それは現実的と言えるのか? という大きなクエスチョンが当然そこには生じるでしょう。そして、その実現可能性が怪しいのであれば、“定数としてのジャパンズウェイ“にもまた「本当に定数、基質足りうるのか?」という疑義が再度投げかけられることになります。
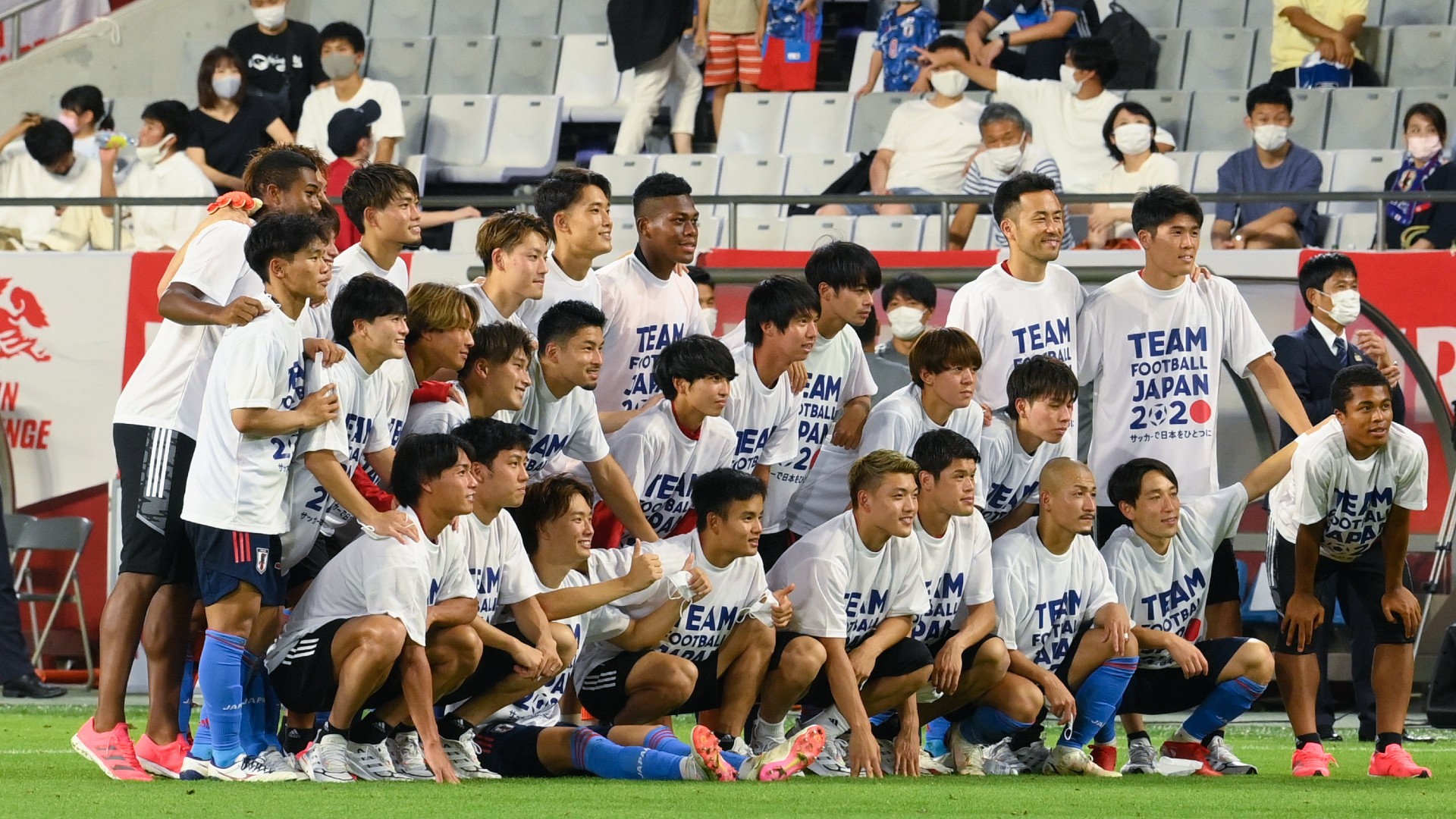
必要な“定数”は民族的・文化的な「らしさ」なのではないのではないか? 時代とともに変わるトレンド、様々な戦術・ゲームモデルを柔軟に受容可能とするために必要なのは、サッカーというゲームそのものに対する本質的な理解、知見なのではないか? と。
来年にはカタールW杯があります。日本サッカーにとって2020年代最大の目標の一つであった東京五輪での内容と結果を受け、サッカーを楽しみ、外側から支える私たちも、ロジカルで建設的な議論をますます盛り上げていく必要があると考えています。
▷分析家・五百蔵容の論考
- 2021.9.2|変数か、定数か。分析家が論じる、東京五輪に見る日本サッカー
- 2021.9.29|日本代表の弱点は、「試合が始まってから考えている」こと。
- 2021.11.10|柴崎のミスは、森保“委任戦術”の必然?変化に対して脆弱な日本
- 2021.11.11|森保監督は、「コンディション問題」を選手に解決させている?
▷分析家・五百蔵容へのインタビュー
- 2021.12.17|活路は“必然の誘発”にあり?日本代表の伸びしろと限界値
▷プロフィール
五百蔵容(いほろいただし)
1969年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部を卒業後、株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガゲームス)に入社。2006年に独立・起業し、有限会社スタジオモナドを設立。ゲームを中心とした企画・シナリオ制作を行うかたわら、VICTORY、footballista、Number Webなどにサッカー分析記事を寄稿。著書に「砕かれたハリルホジッチ・プラン 日本サッカーにビジョンはあるか?」「サムライブルーの勝利と敗北 サッカーロシアW杯日本代表・全試合戦術完全解析」(いずれも星海社新書/2018年刊)がある。
Twitterアカウント:@500zoo
Follow @ssn_supersports







