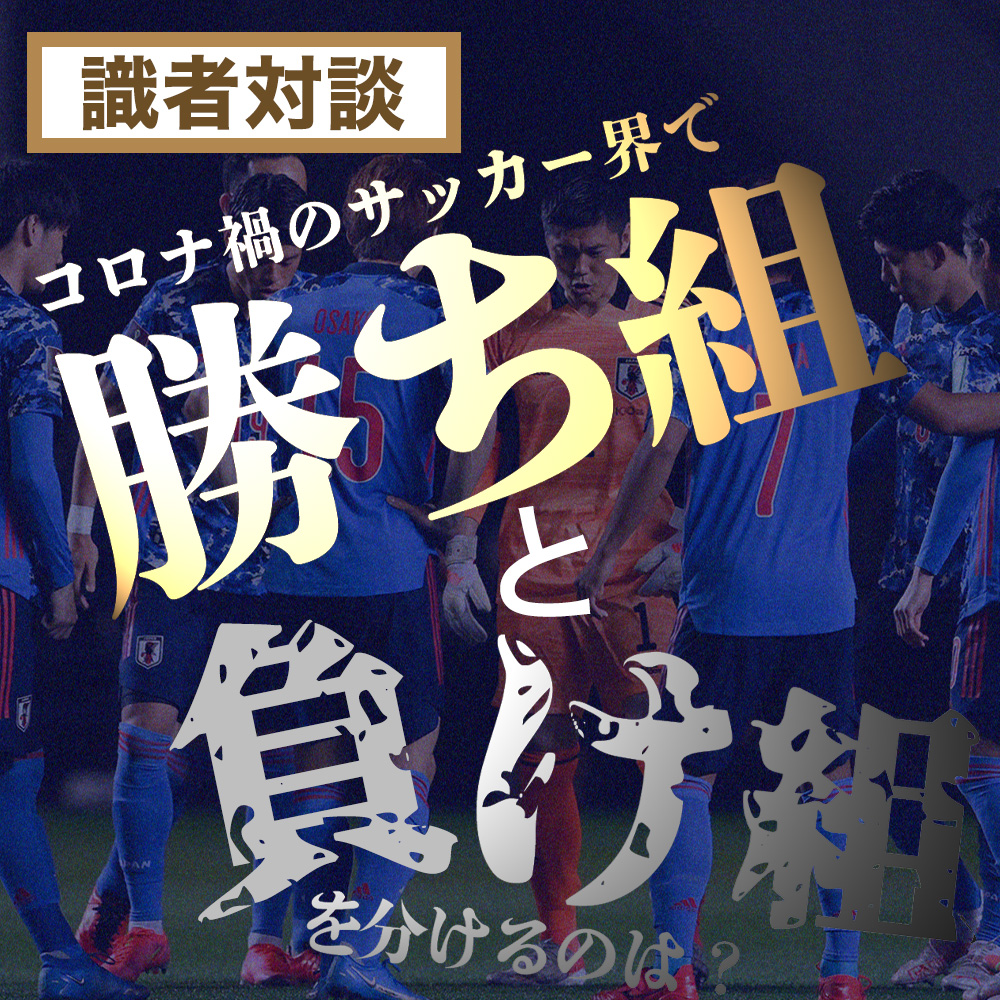

2020年以前と2020年以降で世界は大きく変わった。新型コロナウイルスの影響はあらゆる業界に強制的な変化を突きつけた。
スポーツ界も例外ではない。
スタジアムやアリーナにお客さんを呼んで満員にする。選手とファンが積極的に交流できる場をつくって関心をもってもらう。
コロナ前までは当たり前のようにできていたことができなくなり、大幅な施策や方針の転換を迫られた。
コロナがいつまでに収束するか、確実な目処は今も立っていない。そんな中で生き残っていくためには何が必要になるのか。
上野直彦と北健一郎、さまざまな立場からスポーツに関わる2人が語り合った。
■クレジット
進行=Smart Sports News編集部
構成=北健一郎
■目次
・サッカーバブルは弾けてしまったのか?
・コロナ禍のマイナスをどう取り戻す?
・ゴールの瞬間は最大の課金チャンス
・「WEリーグ」に勝算はあるか?
サッカーバブルは弾けてしまったのか?
──ワールドカップ最終予選のアウェイゲームが地上波で放送されないことが話題になりましたが、お二人は「サッカー日本代表」というコンテンツをどうとらえていますか?
北健一郎(以下、北) サッカー日本代表が“国民的コンテンツ”だったのは2011年から2014年までだったと思います。いわゆる本田圭佑・香川真司時代ですね。2010年の南アフリカワールドカップでのベスト16をきっかけに、新規のファンがかなり入ってきていました。
この時期はサッカー番組だけじゃなく、一般的なニュースとかワイドショーとかでもサッカーの露出がすごく多かった。われわれジャーナリストもテレビやラジオへの出演依頼が多かったです。しかし2014年を境に、メディアへの露出が減っていきました。
テレビやラジオといったマスメディアは、ニーズがなければサッカーを取り上げる必要はない。それでも日本代表戦は強力なコンテンツでしたが、アジア最終予選のアウェイゲームを民放で放送されないことが象徴するように、コンテンツの価値が下がっているのは間違いありません。
──1つの例として、北さんを含めサッカーライターさんの本があまり出なくなりましたよね。
北 例えば、「サムライサッカーキング」という日本代表に特化した雑誌が創刊されたのは2011年です。当時の編集長だった岩本義弘さんもおっしゃっていましたが、あの時代は日本代表のネタをツイートするとすぐに何百、何千リツイートされていました。
でも、そんなバブル的な人気は長くは持たなかった。「サムライサッカーキング」は2014年6月号を最後に休刊しています。マスが興味を持つコンテンツは常に移り変わっていて、サッカーの日本代表はそこから外れてしまったのかなと思います。
上野直彦(以下、上野) 自分は会社経営もしているので、様々な分野の方と話していて強く感じるのはサッカーの話題や例え話が一切出てこないことです。プロ野球や相撲は多いです。例えば、ピンチを表現する場合に「9回裏2アウト満塁で3ボール2ストライクの状況だよね」と言うじゃないですか? 「天皇杯決勝で延長PK戦の3-4と劣勢のなかのGKだよね」とは言われない。イギリスなら例え話としていくらでもフットボールが出てきます。
個人的にスポーツでのキャリアの最初は、INAC神戸(INAC神戸レオネッサ)でスカウティング担当をしていたのですが、それもあって女子サッカーを長く取材しています。なかでも元なでしこジャパンの宮間あやさんとはウマも合ったのでしょうか、最長インタビュアーだったそうです。
彼女の言葉で有名なのが「女子サッカーを文化にしたい」というものです。この言葉は一人歩きしてしまったのですが、その真意はどこにでもある公園で、お母さんと娘がパス交換をしている、女子が河原で練習試合を普通にしている風景を作りたいといったものでした。
なでしこジャパンがW杯で優勝し、女子サッカーの認知は一定ラインまで高まってきましたが、そこからもう1つ壁を乗り越えられていません。男子も女子も、あくまで全体としてですがサッカーを文化にできる領域までには未だ届いていないのではないでしょうか。
──仕事のたとえで使うのは野球が多いです(ツーアウト満塁、など)。サッカーのたとえを出しても、あまり刺さっていない実感があります。
上野 メディアとして2つ問題点を感じるのは、一つはグローバルなサッカーメディアが日本発で出てきていないということ。マーケットがすべて国内向けなので、サッカー人気が低迷する影響をダイレクトに受けてしまう。
中国語圏や英語圏にも発信しないと、例えば東南アジアの人たちがJリーグで活躍する自国選手の活躍の裏側やディテールを読めるメディアがない。遅かれ早かれメディアは立ち行かなくなるでしょう。
英語でも韓国語でもスペイン語でもいいのですが、とにかく記者さんには第二言語ができない人が圧倒的に多い。日本サッカーはまだまだキャッチアップする側、謙虚な姿勢で他国の最新事例から直接インプットできないのは痛いです。
もう一つの問題は、メディアの業界でも単価がほとんど固定化されてしまっていて、競争原理が働いていません。お金が回っていなければ、優秀な人材も入ってこない。構造的な変化が必要な状況なのかなと危機感を感じています。
コロナ禍のマイナスをどう取り戻す?
──コロナの影響にも触れていきたいと思います。2019年はJリーグ全体でも過去最大の入場者数、最大収益になっていました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大による入場制限などを受け、入場料収入やグッズ収入が壊滅的に減っています。
北 クラブの経営規模が大きいところほど、コロナによるダメージはあると思います。浦和レッズなどの人気クラブは、平均的に3万人ほどの集客を見込んで、人件費や運営費を設計しています。
ところがコロナ禍におけるJリーグの規定で言うと、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象地域は、上限5000人か収容人数の50%の少ない方であり、解除後も1カ月間は上限1万人もしくは50%の少ない方で開催すると定めています。チケットの売上枚数は、最大でもこれまでの半分以下なのに対して、価格を倍にできているわけではない。それがもう2シーズンも続いている。
J1で優勝して高額な賞金が得られるのは1クラブだけです。優勝するために外国人選手や日本代表選手など高額年俸の選手を補強して人件費が膨らんでしまえば、優勝できなかった場合はさらに厳しい状況になってしまう。今後はチームとして難しい舵取りを強いられることになります。
最大で50%しか入れられない状況では収益性の根本的な改善は望めません。諸外国では、ワクチンパスポートの運用が始まっており、コロナ前の日常に戻っている国が増えています。
──日本でも、ワクチンパスポートの議論は始まっています。人口の7、8割がワクチン接種を終えた段階で導入するのではないかと言われてます。
北 スマートスポーツニュースでカジノ専門家の木曽崇さんに話を伺いましたが、ワクチンパスポートを導入するかどうかが、日本のスポーツを含めたレジャー産業の正常化につながると考えていて、僕もその考えに同意しています。
欧州と日本ではコロナに対する考えが違って、欧州ではある程度の感染には目をつむり、ワクチンパスポートを持っていれば、原則としてコロナ前と同じようにやれる。今後の日本がそっちに向かうのか、今のように感染拡大、人流抑制という名目でずっと観客数に制限を設けた状態でやり続けるのか。ここが大きな鍵を握っていると思います。
上野 スポーツの4大収入は、これまでは放映権収入、入場料収入、物販収入、スポンサーセールス収入でしたが、今後はそこにスポーツトークンやベッティングなどテクノロジーとリンクした新しいサービスが5本目や6本目の収入源になるのではないかと数年前から考えて記事にもしてきました。
今でこそ、Jリーグクラブも用いておりよく耳にするようになったスポーツトークンですが、2018年の頃には「危ない」「怪しい」と見向きもされてきませんでした。
しかし、スポーツビジネスは新しい時代に移行しています。東京オリンピック・パラリンピックで開閉会式のエグゼクティブプロデューサーを務められ、とてもリスペクトしている日置貴之氏が“スポーツビジネス3.0”と言っていましたが、コロナによって逆に収入が増えるチャンスもあるのではないでしょうか。
トークン、ベッティング、ヘルスケア、フィンテック……スポーツとの掛け算で新たなサービスがどんどん生まれています。このパラダイムシフトはスポーツ界だけではなく、他の分野でも起こっているもので、だからこそマクロな視点を持った方がいいと考えます。
北 上野さんがおっしゃるように、このコロナによる現状を損失と考えるのか、改革と考えるのかで大きく分かれると思います。
実際にスタジアムやアリーナに来られないことを単純な損失ではなく、そこにチャンスがあるのではないかと逆転の発想を持つことができるかどうか。今までは6万人の箱を埋めるためにやってきて、これからは今まで通りのやり方なら3万人になってしまう。しかし10万人にリーチできる可能性があるとも思います。
例えば人気アーティストのライブ配信。今まで、東京ドームなどで行われてきたライブでは人が収まりきれませんでした。しかしライブ配信することで、リーチできる人数を格段に増やすことができる。体験できる価値はライブとオンラインではまだ差がありますが、そこを解決するための技術が開発されています。
VRの技術があれば、観戦空間を拡張できる可能性もあります。例えば、卓球台の周りで見られる超VIPシートはライブであれば10席しか作れなかったけど、それを1万人に売ることもできるかもしれません。そういう発想の転換をしていく必要があります。
上野 ARやVRは個人的に大好きで、“メタバース”、いわゆる仮想空間は今後大きなキーワードになってくるでしょう。すべての産業がメタバースに集約されていく。どこのサービスでアクセスするかの競争も激しくなっていくでしょう。この分野でも日本発のサービスが出てくるのを楽しみにしているんです。
ゴールの瞬間は最大の“課金チャンス”
──スーパーチャット(YouTubeの投げ銭機能)のようにユーザーがリアルタイムで課金できたり、自分の好きな画角で見られたり、好きな選手にインタビューができたり。いろいろな付加価値をつけたチケットがあったら面白いですね。
北 スポーツのライブは価値が高まる可能性が高いです。インターネットテレビの「ABEMA」は今シーズンからMLBの放送が始まって、格闘技はペーパービューもしていて、Fリーグは全試合放送している。明らかにスポーツコンテンツは拡充しています。
これからはライブで見なければ価値がないコンテンツはスポーツくらいになるからです。今まではテレビが番組表に沿っていろいろなものを映し出し、ユーザーはその時間に合わせてドラマを見てきました。でも、NetflixやAmazonプライムなど、自分の好きなタイミングでコンテンツを見られるようになった。
ネタバレさえなければ、ドラマや映画はいつ見ても楽しめます。でもスポーツは、試合開始時間に合わせて、リアルタイムで見なければコンテンツとしての価値は大きく下がる。日本代表戦を1週間後に見るなんて人は、ほとんどいないでしょう。スポーツこそ、ライブで見る最後の砦。だから放映権も高騰している。
上野 メタバースや観戦のDXは進んでいくのは間違いありません。しかしリアルタイムやライブによるスポーツ観戦の価値も続いていき、2軸の世界になると思います。僕が注目していたのはBリーグの取り組みで、オールスターの時に開催された「ライブエクスペリメント」。アウェイの試合を収益化させる手法の原型といっていいでしょう。
富山でオールスターを開催し、品川で8Kのビジョンを4つや5つ作って、そこでみんなで観戦する。ハーフタイムにはチアリーディングがあって、DJのショーがあって、レジェンドの選手が出てくるトークショーまである。1万円ほどのチケットでずっと楽しませてくれます。リーグ2年目の恵比寿会場も翌年の品川会場も体験させていただきましたが、非常に未来価値の高いものでした。
スポーツは今までアウェイの収益を取りこぼしていました。横浜スタジアムもビジターの広島戦の際に開放して、オーロラビジョンで試合を流したら、1日平均で3000人来た実例もあります。
こういう取り組みはまさにライブに価値があるからこそ。配信ビジネスが進む一方で、ライブビジネスの価値はもっと上がる。単価が上がることは並行して行なわれると思います。
──試合を見ているとすごく課金したくなることってありますね(笑)。ゴールシーンなど感情が動くタイミングは、大きなチャンスだと思います。
北 スポーツのゴールシーンって感覚がバグるじゃないですか? DAZNに月額課金していますが、3000円くらいならアドオンで課金してもいいかなという感覚があります。プラットフォームに何割か持っていかれたとしても、残りは全てチームに入るなら。
──「もっと払いたい」というファン・サポーターは、潜在的には多いはず。いまは、課金のタイミングがチケットとグッズぐらいしかない。ゴールが決まれば課金が増えるなら、チームも3-0で満足しないで「4、5点取ろう」となりますよね。
北 NewsPicksの『デューデリだん!』番組でmixiの木村弘毅社長が話していたのですが、UIの設計がすごく重要だと。mixiは競輪のアプリに力を注いでいます。そこでは『モンスターストライク』などで培われたソーシャルゲームのノウハウが活かされているそうです。
今のDAZNの中継は、基本的に一方通行です。配信されている映像を見て、何か自分の発信をするツールはツイッター。そのUIの中で課金できたり、ゴールを一緒に喜ぶような画面に切り替わるなどができれば、もっと応援しようとなります。ユーザーを惹きつけるUIを設計して、スポーツの体験価値を上げることが大事になると思います。
上野 先ほどの“スポーツビジネス3.0”の軸の一つは、スポーツベッティングです。アメリカだと大学スポーツも賭けの対象になっています。ただ、日本の将来において大学スポーツや高校野球などが賭けの対象になるにはものすごいハードルがあるでしょう。
しかし、スポーツベッティングが広がっていけば、収益の一部が女性競技やパラ競技などに還元されて、ある種のエコシステムが形成されていく。日本のスポーツ発展にとって非常にポテンシャルが高いものになっていくとみています。
コロナ禍は今も大変な状況ではありますが、一方でパラダイムシフトの後押しをしている側面もあり、この時代を「何とかしのごう」と考える者と「改革のチャンスだ」と捉える者で大きな差が生まれていくでしょう。
「WEリーグ」に勝算はあるか?
──9月12日、女子プロサッカーリーグのWEリーグが開幕しました。ただ、盛り上がっていたのは現行のサッカーファンがメインに見えました。このタイミングで開幕することに、どのくらい勝算があったのでしょうか?
北 WEリーグは「思想」を前面に打ち出しているなという印象です。例えば日本サッカーリーグ(JSL)からJリーグになった時や、JBLやBJリーグからBリーグになった時はプロスポーツとして見た目も含めて大きく変わった感があった。
しかしWEリーグの光景は、なでしこリーグとほとんど変わりません。ウーマン・エンパワーメントリーグというリーグの名前からわかるように、女性を最大化しようという思想に訴えかけるやり方をしました。
女性のエンパワーメントはトレンドで、このトレンドをリーグのコアに置いた時に、一般の方々にどれだけ刺さるかというと僕はまだ弱いのかなと思います。雇用の状態が変わったとかはあっても、ピッチで見られるものは変わっていないわけですから。
上野 北さんがおっしゃるように、理念は素晴らしいです。問題は、経営を維持できる構造かどうか。 個人的にLリーグ時代から女子サッカーを見続けていますが、構造的に何も変わっていません。
第一に、この国はプロ化の定義が曖昧なままです。JリーグもBリーグもWEリーグもプロリーグを名乗っていますが、統一したフォーマットがあるかといえばそうではありません。
北 WEリーグはなでしこリーグの上位リーグとしてできたものであり、一種のプレミア化です。ただ、「なでしこ」というワードは多くの人が女子サッカーを連想させるほどの強烈なインプレッションを獲得しています。これをわざわざ捨てて、WEリーグの下においてスタートしましたが、それならなでしこリーグをプロ化した方が大きくスタートダッシュできた可能性はあると思います。
──すでに浸透したブランドではなく、新ブランドとしてリーグを立ち上げるのは並大抵のことではないですよね。Googleトレンドを見る限り、WEリーグは開幕の段階でもあまり話題になっていなかったように見えます。
上野 WEリーグの戦略には、2つの前提条件があったと思います。2023年に女子ワールドカップを日本に招致すること。東京オリンピックで銅メダル以上をとること。この2つでストーリーを組んでいましたが、どちらも達成できなかった。新しい戦略を立て直さなければいけませんが、具体的な動きは今も見えてきません。
JリーグとBリーグが一気に盛り上がりましたが、基本的には別の構造をもっています。同じなのは、どちらも初代チェアマンを務めたのは川淵三郎さん。個人的にリスペクトしてやまない方ですが、日本の場合は川淵さんのように引っ張っていける強烈なリーダーがいないと実現できないのかなと思います。
──Jリーグは1993年開幕であり、ほぼ30年前の話です。当時の成功事例を再び踏襲することは、かなり難しそうです。今くらいメディア環境が激変していると、それに合わせた戦略が必要になってくると思います。
上野 おそらく来年からスタートするラグビーのプロリーグについても同じような課題が出てくるのではないでしょうか。
北 Jリーグでも、J3ではサッカーだけで生活ができない選手がいます。男子サッカーより稼ぎにくいであろう女子サッカーをプロ化したとして、上位チームは食えても下位チームはどうなるのかな? とは思いますね。
月収10~20万円台の選手がたくさん出てきた時に、「女性をエンパワーメントする」という理念との齟齬は出てくる気がします。「その条件なら、一般企業に就職した方がいいのでは?」と思われない状況を作ることが大事だと思います。
<了>
■プロフィール
上野直彦(うえの・なおひこ)
スポーツジャーナリスト。日本ブロックチェーン協会事務局長、早稲田大学スポーツビジネス研究所・招聘研究員、江戸川大学、追手門学院大学で非常勤講師、ブロックチェーン企業ALiSアンバサダー 、Gaudiyクリエティブディレクターなど、スポーツビジネスや女子サッカー、育成年代、Jクラブの下部組織などあらゆるジャンルで活躍。漫画『アオアシ』取材・原案協力、『スポーツビジネスの未来 2021 ー2030』(日経BP)、NewsPicks「ビジネスはJリーグを救えるか?」連載、Forbes JAPANへの寄稿など。趣味はサッカー、ゴルフ、マラソン、トライアスロン。
北健一郎(きた・けんいちろう)
1982年7月6日生まれ。北海道出身。2005年よりサッカー・フットサルを中心としたライター・編集者として幅広く活動する。 これまでに著者・構成として関わった書籍は50冊以上、累計発行部数は50万部を超える。 代表作は「なぜボランチはムダなパスを出すのか?」「サッカーはミスが9割」など。FIFAワールドカップは2010年、2014年、2018年と3大会連続取材中。 テレビ番組やラジオ番組などにコメンテーターとして出演するほか、イベントの司会・MCも数多くこなす。 2018年からはスポーツのWEBメディアやオンラインサービスを軸にしており、WHITE BOARD、Smart Sports News、フットサル全力応援メディアSAL、アベマFリーグLIVEで編集長・プロデューサーを務める。 2021年4月、株式会社ウニベルサーレを創業。通称「キタケン」。
Follow @ssn_supersports




