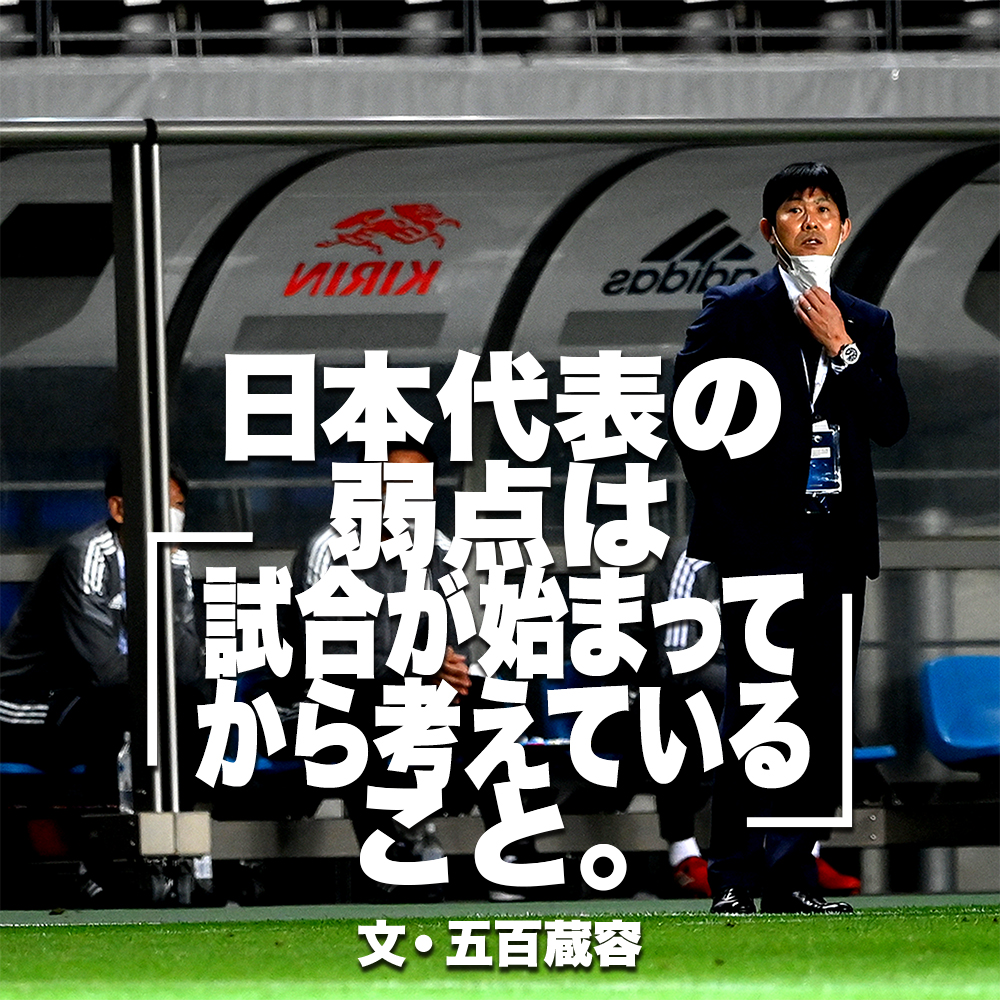
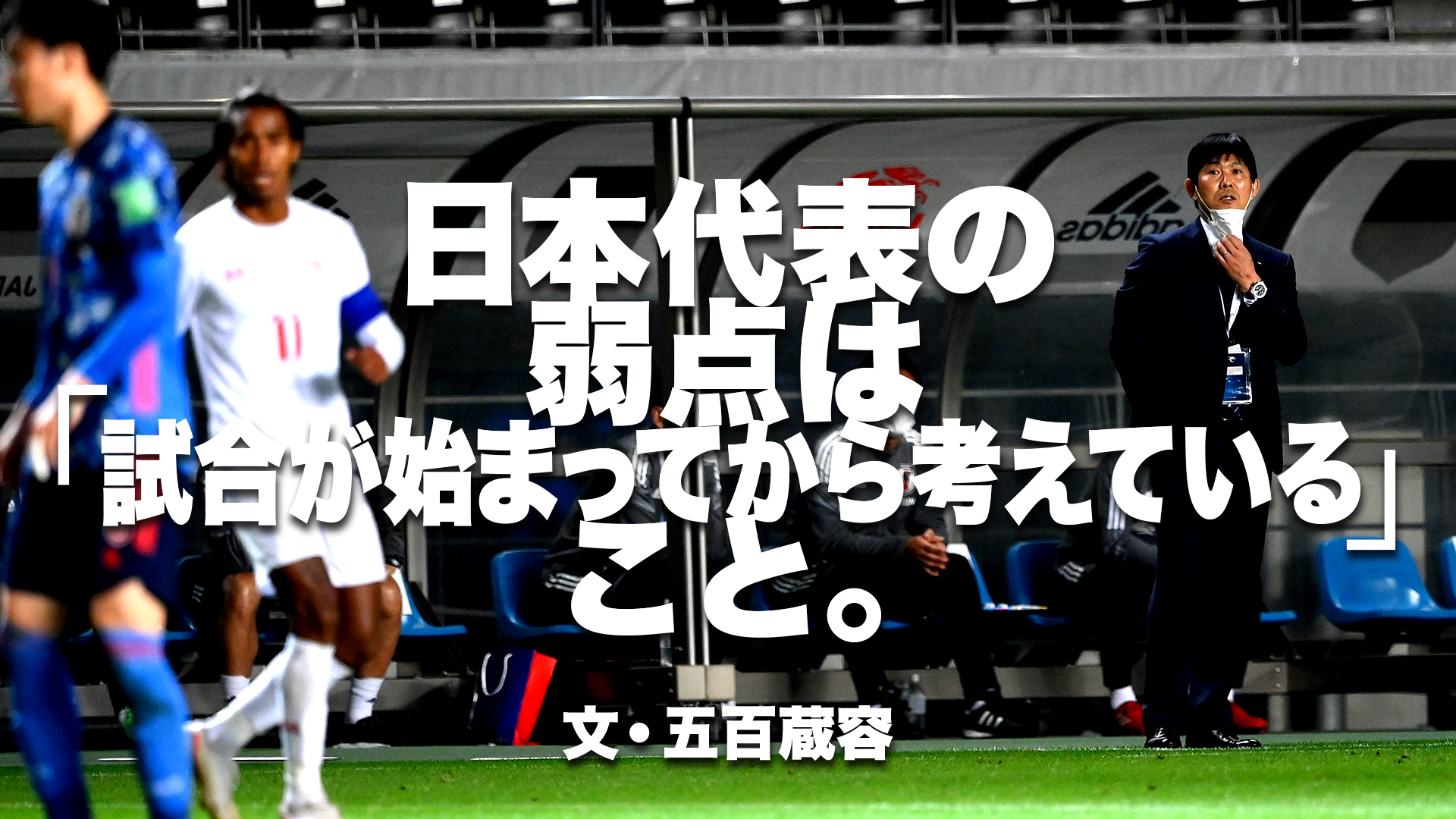
2022年カタールワールドカップ・アジア最終予選、日本代表は初戦のオマーン代表戦に敗北しました。ホームでの敗戦以上に、内容面で相当に上回られ、90分を通じてゲームを思惑通りに支配され、思惑通りに点を取られるという形で、最終予選の展望に初戦から暗雲たちこめるという戦いとなりました。
チームの立ち上げ後ほぼ3年が経過し、その間に蓄積された取材・選手コメントなどの証言から現在ではほぼ明らかになっていますが、戦術的な判断、時には戦略レベルの判断をも選手たちに委任することで「ピッチで起こる様々な問題に対し基本的に選手たちで対応する。対応力を向上させ、その対応力で勝利する」。カタールW杯ベスト8をその「委任戦術」「委任戦略」で勝ち取るという大戦略を森保一監督の日本代表は採っています。
その大戦略から考えると、コンディション差はあったにせよ、オマーン代表の仕掛けてきたアタッカー3枚+CH3枚で完全に閉じてしまう4-3-3ブロックからのカウンター、日本のDFラインにギャップメイクする周到な準備に対し、試合を通じて有効な対応をできず、ソリューションを見出せなかったことは、敗戦以上に大きな問題でした。
第2節、中国代表戦は文字通り負けられない戦いとなりましたが、勝ち点3を確実にもぎ取るだけでなく、大戦略を必要な水準で遂行できたか、カタールW杯本戦がおよそ1年後に迫る状況にふさわしい進捗を示せるかという課題にも、日本代表は同時に直面していたと言えるでしょう。
文:五百蔵容
写真:浦正弘
※記事内の表記
CH=センターハーフ
WB=ウイングバック
WG=ウイング
SH=サイドハーフ
SB=サイドバック
CB=センターバック
中国代表の日本対策:日本が進捗確認する状況は整った
通常はボール非保持時には4-1-4-1、もしくは4-4-2の守備ブロックから攻撃時には4-3-3に移行し、同格以下の相手にはビルドアップを試みつつも、基本的には前線の選手のクオリティを見込みロングボールによる陣地確保、陣地回復を最優先にゲームを進める。
高い位置から守備を仕掛けるオプションも持つが、奪いきる意図はなく、相手を追い込み自陣深い位置でミスを誘うか、蹴らせてボールを回収、ロングボールからの陣地確保につなげていく。それが中国代表の通常のやり方でしたが、日本戦では陣形、やり方を大きく変更してきました。
3バックシステムを採用し、ボール非保持時には両サイドのWBが下がって5枚のDFラインを構成する5-3-2で自陣に引き、日本の攻撃を受け止めます。WBは日本のWG(SH)を見ていますが、ぴったりとマークしサイドに付いていくのではなく、インサイドへの侵入を警戒しているという格好。
サイドに張る日本のWGなりSBなりにボールが出た場合は基本的にWBではなく、ボールサイドのインサイドハーフが出て対応します。CBとWBの間にギャップ(隙間)を作られることを阻止し、ゴール前(ボックス前)を3枚のCB+2枚のWB=計5枚のDFでしっかりと固め、中央(インサイド)での日本選手のコンビネーションアタックが機能するようなスペースも与えない。
サイドを捨てる形になりますが、しっかりと自陣に引いて日本にDFライン裏のスペースを与えなければ──中央でDFラインがしっかりと準備できる状態であれば──中で対応できるのでクロスをあげさせてもよい、という割り切り方でした。
ボール保持時には右WBが右SB化、左CBが左SB化して4-3-3に変化しますが、攻め手はロングボールを蹴って陣地回復を最優先なのは変わらず、けれども5-3-2で自陣に撤退するため、ロングボールを引き取る前線の選手も低い位置に引いたところから単独で前に出て行くため日本の陣形内で孤立しボールを失うシチュエーションがほとんどで、カウンターもほとんど成立しないという状態でしたが、ゴール前に確実に鍵をかけ失点を避け、ロングボールから一種の”事故”を起こしわずかでも得点機を得られれば……。そういう戦略だったかと思われます。
報道によれば、日本代表は中国がこのやり方を採ってくることを全く予期しておらず、試合開始前に配布されるメンバー表から「3バックの可能性大」とはじめて認識し、限られた時間で突貫での準備を余儀なくされたと言います。
中国代表が5-3-2での自陣撤退を採用した試合は直近では基本的にはないため、それ自体は致し方ないことだと思われます。
その一方で、「サッカーは常に想定外の事態が生じるもの」ゆえに「ピッチで選手たちが判断し、対応しなければならない」として選手への委任戦術、委任戦略を採っている日本代表としては、これはある意味おあつらえ向きの状況でした。
現場での臨機応変の対応力、それを支える選手ファーストの思想、選手の自主性を重んじる、考えるサッカーの追求、それが遂行しやすい状況作り……そういったサイクルを底ざさえする「日本人らしさ」を追求した和のチーム作り。世につれ変化してく「変数」である「戦術」「作戦」に拠ることなく、不変の「定数」たる「ジャパンズウェイ」でW杯を勝つ。この中国戦はまさにその進捗状況を推し量るにふさわしいセッティングとなったのではないかと思われます。

※なお本稿の導入編とも言える「変数」「定数」「ジャパンズウェイ」に触れながら「東京五輪に見る日本サッカー」を記した論考はこちらをご覧ください
日本代表の試行錯誤①:様々な方法で相手の対応を観察
「失点をしないこと」を最優先に設計された中国代表の差し手に対して、どこでスペースを生み出し、活用し、狙いを持ってゴールを陥れるか。日本代表が、ピッチに立ってからそれを考え始めているのは明らかでした。
日本はまず、自らがサイドにボールを配球した時、サイドから攻撃を仕掛けた時の中国代表の対応を見るところからスタートします。
自らのサイドからの仕掛けに対し、中国代表のWBがどう振る舞うか。WBがサイドに釣り出されて来ないならば、誰が日本のサイドアタックをケアしに動くのか。5-3-2の守備では、WBが中央にステイするのであれば中盤の3枚のうち、ボールサイドのインサイドハーフが動くしかありません。前半10分頃まで、日本代表は、サイド~中央でボールを出し入れするなかで、WBの動きを確認しつつ、そのタスクを肩代わりするインサイドハーフの仕事範囲がどれほどか、確認を進めているようでした。
前半10分前後で、日本代表はサイドでフリーになる、もしくはプレッシャーを相手のやり方上あまり受けないSBからのクロスをゴール前で合わせられるか、サイドで時間をかけてからのクロスでどうか、アーリークロスはどうか、アーリークロスをあげると見せかけてライン裏に走る選手を使うロングボールを出し、そこから相手の対応・崩れ方を観察するなど、様々な試行錯誤を行っています。
通常、5-3-2で中央の閉塞を優先した守備を行うと、インサイドハーフのタスクが過重になります。WBが見ることのできないサイドのケアはもちろん、前線の2枚に与えられた守備タスクの軽重によっては、適時前方に進出して彼らの守備を肩代わりすることも求められます。その上、3枚のセンターハーフの一角としてDFライン前のスペースもプロテクトしなければなりません。
中国代表の5-3-2もこの通例にもれず、インサイドハーフはサイド、中央、2トップ後方と、3つのエリアをケアしに動き回ることになっていました。
前半11分30秒前後の時間帯で、サイド攻撃を意識させ、CBとWBを中央にセットさせると共にインサイドハーフの移動を強いる形、タスク過多に付け込む形でインサイドハーフを動かしたあとのスペースを使ってシュートチャンスを生み出しているので、前半10分頃までには、攻撃を仕掛けながらの様子見で日本代表はそのことを認識するに至っていたと思われます。
このシーンでは、中国代表が対応して守り切りましたが、「インサイドハーフを動かされた場合、そのスペースを使う相手を潰しきれるか潰せないかという判断を早期に行い、
できるだけ早くDFラインに戻る」という約束事を彼らがもっているという情報を得られたのは大きかったでしょう。純粋に「相手の出方を見て判断する」という意味においては、前半10分強でいい形を表現できていたと言えるシーンでした。

日本代表の試行錯誤②:サイド・インサイドの選択肢の偏り
前半15分前後には、インサイドハーフのところでスペースが得られることをチーム全体がおそらく共有し始めていて、ワイドのアタッカーがインサイドに入りそこを利用しようとするシーンが連続します。
この試合では、
・ボールの動かし方次第で中国代表のインサイドハーフを動かし、スペースメイクできる
・対面となる相手WBが大外まで付いてこないので、サイドをSBに任せることができる
といった理由から、WG(伊東純也・古橋亨梧)がインサイドに入ってプレーするシーンが多く見られます。
サイドの選手が中央に入ってきて中央に密集を形成しすぎ、カウンターを受ける際にがら空きとなったワイドのスペースや中央の密集を縦方向にスキップされ、人数が薄くなった場所を使われて危険な状況を招くという、日本代表の悪癖は以前から広く指摘されていますが、この試合のように相手のやり方にアジャストするために中央への侵入頻度、人数を増やすというケースも多いのが実情です。
相手がそこを捨てる選択、準備をしている場合は単純にワイドに張ってもスペースメイク、ギャップメイクがしづらくなります。
そんな場合、ワイドにポジショニングするアタッカーが適時インサイドに入っていくことで相手を動かそうとする、脅威を与えようとするのは世界的な傾向であり、だからこそワイドでもインサイドで仕事できるWGが主流になっています。
日本代表、日本サッカーに足りないのは、そういったポジション移動からの選択肢がインサイドでのコンビネーションアタックに偏ってしまうこと、インサイドのポジショニングから相手を外側に動かすチームとしての戦術、グループワークに乏しいといったことと思われます。
このため、相手からすれば日本が広くポジショニングしている時はサイドアタックを警戒、インサイドに多人数がポジショニングした状態からのアタックは中央で人数をかけたコンビネーションアタックを警戒、と対応と反撃が容易になってしまいます。
その傾向はこの試合でも現れており、中国のやり方にも起因するものの彼らにほとんど攻撃機会を与えず日本代表の攻撃練習といった趣のなか、試行錯誤は重ねれどもなかなか相手を効果的に動かせない時間帯が続きます。
前半18分前後からは、中国がプレッシングを行わないためほぼ完全にフリーになり精度の高いプレーが恒常的に可能な状態にあるCB、主に冨安健洋からのロングフィードでエリアを取る、エリアチェンジをすることで中国の陣形を縦に、左右に動かしてスペースを得られないかという試行錯誤も重ねられていきます。
試行錯誤の成果が出た得点:中国の対応を逆手に取った伊東
前半21分、38分とインサイドハーフ周りの問題を利用した起点作りから決定機を作り出したあと、40分に伊東の突破からの先制点が生まれます。
この先制点は、伊東の頭脳的なポジショニングと、そこからのランを伊東が最も効果的に活用できる最適なタイミングでパスを出した遠藤航、その意図を的確に察知し最適な駆け引きとスピードでDFライン裏に走り込んだ大迫勇也の三者のプレーが、中国が最も警戒していた「サイドでスピードアップを許し、中央のDFラインの準備が整わないうちにシュートに持ち込まれる」というシチュエーションを生み出した素晴らしい得点シーンでした。
中国はインサイドハーフとWB、CBのタスクの組み合わせで日本からDFライン周辺のスペースを奪い、サイド攻撃のスピードを落とし裏に出づらくさせ、そのことでDFラインがゴール前に人数をそろえ、侵入してくる日本のアタッカーを前方に置いてマークしやすくしていました。
日本のサイドアタッカーがその監視枠内で行動しても、思うようにプレースペースやランのコースを得られず、この仕組みを壊すことがなかなかできませんでした。ならばと伊東は彼らの監視枠内に入っていくのではなく、足を止めてその外側にポジショニングし、WBやインサイドハーフからあえて遠い距離を取ることで「自分の周囲に誰もいない=自分の周囲にスペースを作り出す」ことに成功しました。
そして、そこでボールを受けると、助走を取る形でスピードアップし、そのスピードのまま、対応に出てきた中国選手を振り切ってDFラインの裏に出てクロスを上げたのです。伊東のポジショニングからの攻略は、この試合の中国代表のやり方を逆手にとった見事なものでした。

試行錯誤と対応に費やした時間:40/90分
想定外のやり方を採ってきた中国代表に対して、日本代表はその委任戦術、委任戦略の狙い通りに、ピッチ上で選手たちが自主的に対応し、試行錯誤してソリューションを導き出して得点し、勝利しました。そのこと自体はポジティブでしょう。
ただ、攻略の糸口を見出すのにおよそ20/90分、実際に攻略に結びつけるまでに40/90分を消費しています。これは森保監督の日本代表にとって常態といえます。
「事前の分析を選手たちに落とし込む濃度を高めた試合」以外──事前落とし込みの濃度を低くした試合、中国戦のように相手が想定外のやり方を採ってきた試合──では、ほとんどすべての試合で、相手のやり方の確認に前半の半ば程度、チームでのソリューションの共有と実行までに前半いっぱいの時間を消費しています。
これは、現在のチームにおける最初のビッグトーナメントであった2019年のアジアカップグループリーグ初戦、トルクメニスタン代表戦での「対応」と概ね同等のタイムラインでもあります。
私たちは、これをどう見るべきでしょうか?
日本代表の「対応力」は、目標とするカタールW杯ベスト8進出の実現に足るような向上を見せているのでしょうか。それとも「それがサッカーなのだから、(1試合のなかで)この程度の時間がかかるのは当然」なのでしょうか。
大戦略の脆弱性:戦略そのものが日本の弱み
また、中国が力関係的に日本に対するのと同じような劣位にあるオーストラリア代表に対してはこの戦術を採らず、日本戦のみ変更してきたことを考えると、日本に相対する敵はすでにこう考え始めている可能性があります。すなわち、こうです。
「日本はピッチインしてから選手たちに対応を考えさせているので、これまでやっていないやり方をぶつければ、彼らがその場で考えて試行錯誤をはじめ、こちらの攻略に手間取る時間を利用して一撃を与える、ひと泡吹かせる可能性が高まる」
「彼らが手間取る時間をできるだけ長く取れれば、勝利できずとも勝ち点1を手にできる可能性が高まる」「日本の想定と違うやり方を採用する」ということは、「自チームにとってもいつもと異なるやり方になり、パフォーマンスを落とすデメリット」よりも「日本側がピッチ内対応に手間取り時間をロスすることによるメリット」のほうが大きいと相手が判断しているということでもあります。
それは、相手がこのように見ているということでもあります。
「日本は“ピッチ内で考え対応する”という戦略を採っているが、必要な水準に達していない」
「必要な水準に達していない戦略に固執しているのは日本の弱みである」
日本がこのやり方で勝っていくためには、それが弱みではなく明確な強みになるように「対応力」を向上させていかねばなりません。
このチームは立ち上げからすでに3年が経っています。その間に東京五輪という「本戦」も挟む関係上、五輪世代の融合をはじめから視野に入れたラージグループを形成し、「選手たちの判断」を重要視し、委任戦術でチームの対応力を必要な水準まで上げる方針を3年間遂行してきました。
東京五輪の結果と内容から振り返っても明らかなように(東京五輪における日本代表の総括分析をした拙稿を、いま一度こちらに貼ります)、準備してきた範囲内ではチームで判断をそろえ、いい判断からの選手たちでの対応を遂行できるが、相手が対応を変えてくると判断が遅れてしまい、必要な(求められる水準の)対応ができない──3年を経て、日本代表はいまだその状態にあることは現実です。それゆえ、中国戦では敵将に「日本が採っている戦略そのものが日本の弱み」とみられたのかもしれません。

「毎日練習し、話し合う時間があり、実践する試合数も多く、PDCAを短いサイクルで回せるクラブチームならともかく、代表チームは年間試合数が限られており、全員がそろうとは限らない3~5日程度の練習と戦術落とし込みの期間しかもてない。必要な水準の対応力を身につけることが可能なのか?」
「押し通そうとするならばもっと情報処理や意志共有のやり方にテクノロジーを大胆に導入するなど、大がかりなトレーニング改革が必要なのでは?」
「今のやり方では間に合わないのではないか」
現在の日本代表の戦略は、当初よりこのような危惧が持たれるものでもありました。3年かかって現在の水準──2019年アジアカップと、少なくともソリューションを見出すのに要する時間という面では同等の対応力──にあるというのは、その危惧が現実になりつつあると考えることも可能でしょう。最終予選で同グループの強敵、オーストラリア代表が、サウジアラビア代表が、日本代表のこの「弱み」を突くようなやり方を採ってきた場合、日本代表はどう「対応」するのか。「対応」を模索している間に致命的な一撃を食らわないような試合ができるのか、どうか。
今後の最終予選を戦っていくにあたり、重要な論点となるでしょう。
▷分析家・五百蔵容の論考
- 2021.9.2|変数か、定数か。分析家が論じる、東京五輪に見る日本サッカー
- 2021.9.29|日本代表の弱点は、「試合が始まってから考えている」こと。
- 2021.11.10|柴崎のミスは、森保“委任戦術”の必然?変化に対して脆弱な日本
- 2021.11.11|森保監督は、「コンディション問題」を選手に解決させている?
▷分析家・五百蔵容へのインタビュー
- 2021.12.17|活路は“必然の誘発”にあり?日本代表の伸びしろと限界値
▷プロフィール
五百蔵容(いほろいただし)
1969年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部を卒業後、株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガゲームス)に入社。2006年に独立・起業し、有限会社スタジオモナドを設立。ゲームを中心とした企画・シナリオ制作を行うかたわら、VICTORY、footballista、Number Webなどにサッカー分析記事を寄稿。著書に「砕かれたハリルホジッチ・プラン 日本サッカーにビジョンはあるか?」「サムライブルーの勝利と敗北 サッカーロシアW杯日本代表・全試合戦術完全解析」(いずれも星海社新書/2018年刊)がある。
Twitterアカウント:@500zoo
Follow @ssn_supersports




