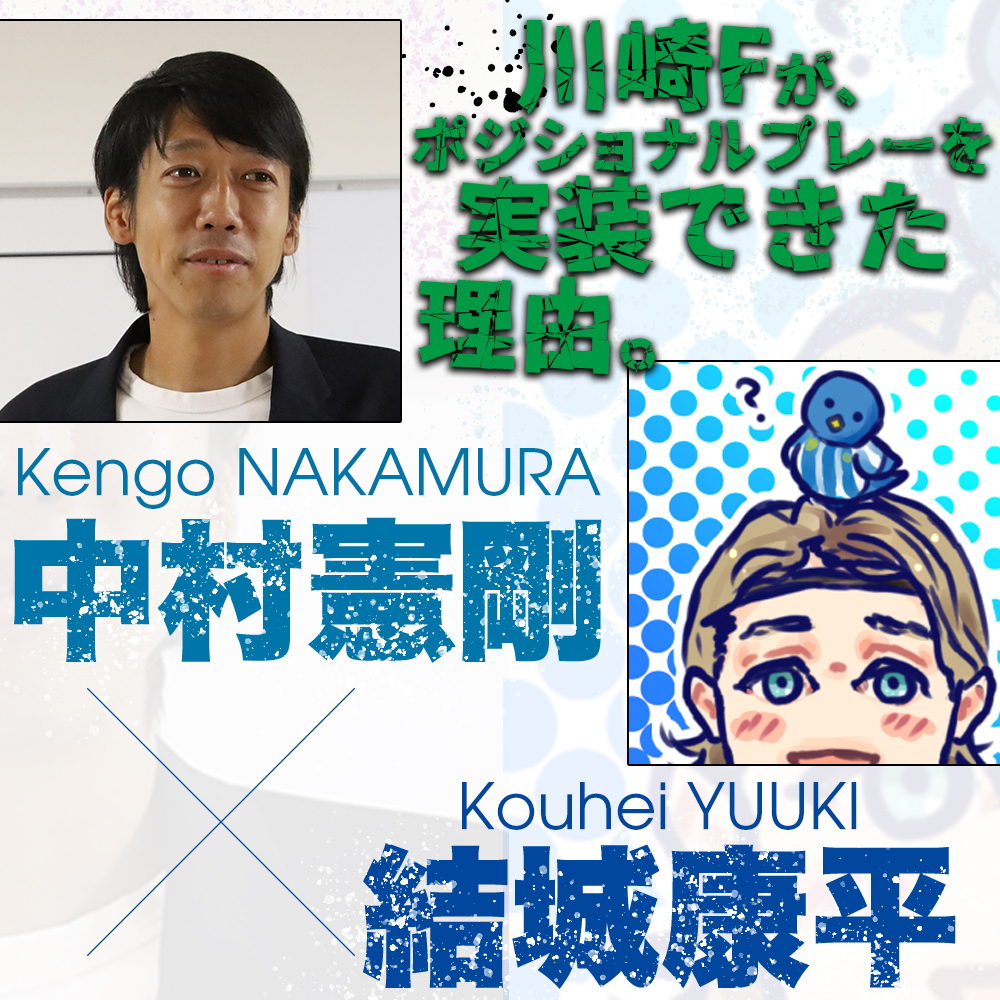

川崎フロンターレを2020シーズン限りで引退後、精力的にサッカーを発信されている中村憲剛さん。ポジショナルプレーについて日本でいち早く紹介するなど、インターネット界隈で絶大な支持を集めるフットボールライターの結城康平さん。
「トップ選手」と「WEB論客」という異色の組み合わせによる対談が実現。川崎が作ってきたサッカーの哲学や、「ポジショナルプレー」の概念について語り合いました。
■関連記事
■目次
・少年時代に見たバルサが衝撃的だった
・フロンターレが作ってきたサッカー哲学
・後出しジャンケンで導き出される最適解
・ポジショナルプレーは戦術ではなく概念
少年時代に見たバルサが衝撃的だった
──今回の対談は、中村憲剛さんがフットボールライターの結城康平さんの記事を読み、「おもしろかった」、「話してみたい」と感じたところから実現しました。さっそくですが、お二人はお互いについてどんなイメージを持っていましたか?
中村憲剛(以下、中村) きっかけは覚えていないんですが、Twitterで誰かがリツイートした結城さんの記事を見て、非常に読みやすかっただけでなく、内容に共感するところがあったんです。
当時、僕も現役を引退して記事を書き始めていたので、自分のマッチレビューの答え合わせのような感覚もありました。
昨日(対談日の前日)、結城さんがアップされたアジア最終予選アウェイ・オマーン戦のレビューも読んだばかりで、試合をどう見ているかという目線も含めて、自分の考えとすり合わせ、参考にさせていただいています。
結城康平(以下、結城) ありがとうございます。
僕からすると、中村憲剛さんはJリーグや日本代表で活躍されていたトッププレイヤーというだけでなく、引退後の解説を聞いていても、書かれたものを読んでも、選手時代からロジカルにサッカーを見てこられた人なのだなという印象を持っています。
僕らライターはどうしても外から想像して書く部分が多くなりますけど、憲剛さんは選手としての目線、現場からの視点をきちんと言語化されているので、今後、書き手として、解説者として、指導者として、どんなふうに活躍されるのか本当に楽しみです。
中村 結城さんはサッカーはやっていたんですか?
結城 全然うまくはありませんでしたが、小学校から高校まで。その後は趣味でサッカー、フットサルをしていて、見るほうは中学生くらいからです。雑誌や名鑑を買ったりしながらEUROやW杯を見始めて、徐々に海外リーグも見るようになりました。
中村 サッカーについて書き始めたのはいつ頃なんですか?
結城 最初はミクシィに観た試合の感想を書き始めて、サッカーに詳しいライターやブロガーの人たち、育成年代を追いかけている方々とコミュニケーションを取るようになっていって……という流れでした。18歳くらいだったと思います。
──その後、結城さんはスコットランドの大学院に留学されて、そこで英語のスキルや海外サッカーの知識をキャッチアップするようになったと聞いています。
結城 そうですね。23歳から2年半留学していて、海外サッカーを観戦したり、プロの指導者さんと実際に喋ったり、戦術に関する英語の文献にも触れる機会があって感覚が変わりました。
また、現地のユースや下部リーグのある意味、洗練されていないサッカーを見たことで、選手の成長過程を感じられたのもいい経験だったと思います。
中村 僕は日本でしかやってないから、海外でしっかりとサッカーを見てきた経験があるのは少しうらやましいです。
結城 いえいえ、とはいっても趣味の延長でしかないので。憲剛さんは……。
中村 恥ずかしながらサッカーノートをほとんど書いたことがないんです。ただ、文字に起こしたことがない代わりに、小学生の頃から自分の出た試合に限らず、海外リーグも含めていろんな試合を何回も見ていました。
結城 同じ試合を?
中村 そうです。1回目と2回目、2回目と3回目も違う発見があって、内容が頭に残るんですよね。その繰り返しのなかで、自分なりのサッカーを見るポイントが整理され、書くための引き出しも増えていったのかなと思っています。
結城 それは自分のプレーのいいイメージを固める作業でもあるんですか?
中村 そうですね。でも、1回、2回、3回と連続では見ないようにしていました。主観が強くなりすぎてしまうので、客観視するために、間にライターさんの書いたレポートや解説を読んだり、他の試合を挟んだりして、冷静に見られるよう工夫していました。
正直、うまくいかなかった自分の試合は見返したくないんですけど、そこはがんばって2回、3回と。次に同じミスが起きないように努力していたつもりです。
結城 海外サッカーもずっと追いかけてきた感じですか?
中村 僕は、ずっとバルサが好きで。カンプ・ノウに行ったことは一度もないんですけどね……(苦笑)。きっかけは1992年のUEFAチャンピオンズカップ決勝でした。監督はヨハン・クライフで、ペップ・グアルディオラやロナルド・クーマンがいました。
そのチームが同じ年の12月にトヨタカップで日本に来て、サンパウロと対戦。試合には負けたんですが、僕の中ではサンパウロよりもバルサの見せたサッカーのインパクトが大きかったんですね。
特にプレイヤーとしてのグアルディオラが好きで、「プレッシャーが激しい中盤の真ん中の位置で、あんなに細くて足も速くない選手になんでボールが集まるんだろう」と思っていました。
今もそうですけど、僕自身が細くて足も速くない選手だったので、当時は海外ではグアルディオラ、日本ではラモスさんに自分を投影しつつ、ボールがたくさん集まり、ゲームを支配する選手に憧れていたんです。
フロンターレが作ってきたサッカー哲学
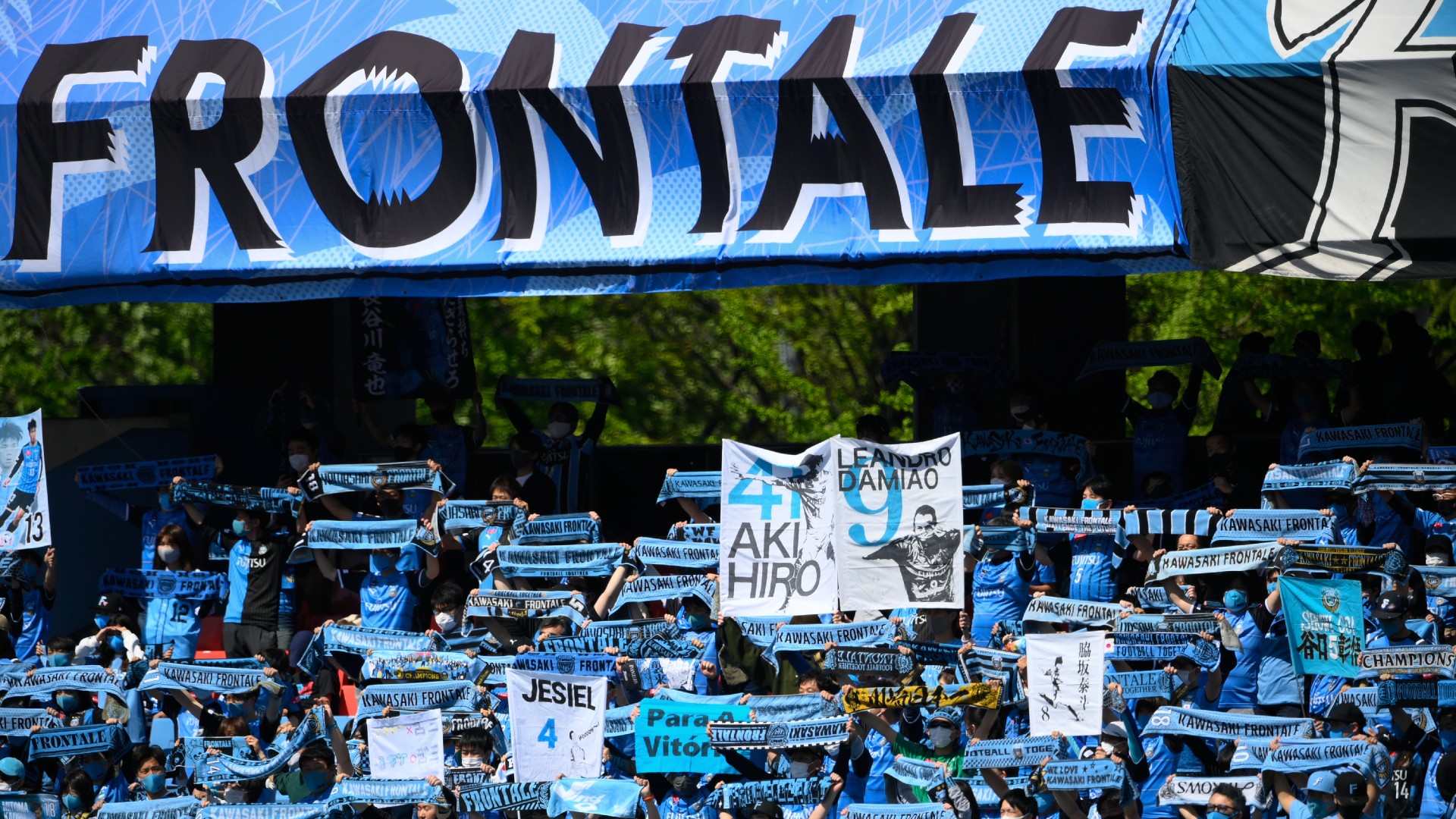
結城 憲剛さんはもちろんなんですが、川崎フロンターレの選手は視野や認知能力が優れていて、すごく周りの状況が見えていますよね。今はどういう局面で、どう相手を背負ってプレーするかを意識的に考えてプレーしていると感じています。
中村 それ、この間の最終予選の日本対オーストラリア戦のレビューでも書いてくれていましたよね。
結城 はい。僕はフロンターレの選手がすごいというのをここ最近、遅れて実感したんです。日本で話題になっているのは知っていましたが、実際にプレーを見て「なるほど。彼らがすごいのはこういうところなんだな」と。アプローチは違っていても、海外のサッカーの最先端に向かっている。それがすごく面白いですよね。
中村 代表での田中碧と守田英正のプレーを分析しつつ、「独特なフリーの感覚」、「自分が受けられない状況でもボールの方向を指示しながら先の状況を読むスキルは、『最近の川崎』が発展させてきた独自の感覚に思える」と書いてくれたじゃないですか。
「ああ、そこをわかりやすく言語化してくれる人がいる」とうれしくなって。それも結城さんと話してみたいと思った理由の1つです。
結城 憲剛さんたちが作ってきた川崎の文化やスタイル、考え方が若い選手に伝わり、彼らが国内外のトップレベルで戦っていること。特に大卒ルーキーの守田選手、三笘薫選手といった選手たちが1、2年のプロ経験で海外に移籍していく姿は、今までJリーグを見てきたなかでも異質なことが起こっている感じがしています。
しかも、主力となった若手が抜けても川崎というクラブの力は落ちていない。バルセロナを例にするのが正しいかどうかはわからないですけど、監督や選手の考えとクラブの文化がうまく一致して、新しいゲームモデルや哲学が作り上げられているのはたしかで、それはファンからしたらたまらないことだろうなと思って見ています。
中村 ありがとうございます。
結城 あとは、長期的に川崎が作ってきた哲学を日本のサッカー界がどう理解して、強化に活かしていけるかが鍵かなと思います。
また、僕からすると代表の中核を担っている選手にはますますがんばってほしいですし、田中選手なんかは東京オリンピックでのプレーを見ていて本当にすごく気に入ってしまいました。単純に見ていてワクワクしますし、頭もいいですし、止める、蹴る、ターンなどの細かい技術の高さがすごく光る選手。まるで、ルカ・モドリッチを見るような感覚になりました。
中村 ……。なんだろう、このうれしいようなこそばゆい感じは(笑)。
結城 当たってくる相手のベクトルを意識して逆を取る、みたいなプレーが僕の中でモドリッチをイメージさせるんですね。相手のプレッシャーを把握しておいて先に動かし、抜ける動きを見ていると「日本にもこういう選手が出てきたんだ」と思いますね。
川崎のサッカーを語るとき、「止める・蹴る」の技術がキーワード的に使われることが多いですが、一方で相手への意識もポイントですよね。「相手がこうくるから、こう動こう」と。中盤の選手を中心に、相手を困らせる立ち位置への意識の強さをすごく感じています。
中村 「相手を見る」ことがとても大事だと思います。立ち位置1つで、どう局面を打開するか。相手をいなしていけるか。どんなシステムだとしても、最終的には相手が僕らに対して何をどうしてくるのかを見てプレーできるかどうかが重要になってきます。
そして、相手を見るにはしっかりとボールを止めなければいけない。2012年に風間八宏さんが来て、ボールをしっかりと止めることの意味を再確認しました。ピタッと止まれば視線が上がる時間がより長くなるので、その分相手も味方も空いてるスペースもより長い時間見ることができます。
さらに言うと、見る時間が長くなれば、自分を活かす立ち位置、味方を助ける動き、相手の逆を取る方法など、意識できるものも増えるんですよね。
碧や守田も代表でやっていますけど、ハーフスペースに落ちて、相手を見て、自分のところに誰がくるかを掴んで、いなして等、逆に相手に問題を突きつける。そういうプレーをボールがないときにしょっちゅうやっていると、今度は相手が勝手に動いてくれる。そのあたりの彼らの意識が、結城さんの何かに触れたのかもしれないですね。
■JリーグYBCルヴァンカップ準決勝第1戦|川崎vs鹿島|ゴール動画(引用:Jリーグ公式/2019年10月10日)
後出しジャンケンで導き出される最適解
結城 たとえば、憲剛さんの現役時代、僕は「中村選手はボールに触れる前、何回逆サイドを見ているか」といったところを意識して見ていました。数秒の間に2回、3回、4回と、見るプレーをしていて、3回目と4回目の間にボールをタッチしていたりする。その感覚がたまらないんですよね。
中村 そんなところをたまらなく見ている人、あまり多くないですよ(笑)。
結城 田中選手だけでなく守田選手も代表の中で比較しても、見る回数と時間が圧倒的。断続的に相手を見て局面のイメージを固めていて、ボールに関与する最中も首を振り、プレーの選択を最後まで調整している。その動きに注目していると、本当に鍛えられているなと感じます。
中村 彼らは「自分がここに立つことで何が起きるか」をある程度想定できていると思うんです。だから、何回か相手を見た後、微調整してプレーを決めていくことができます。
たとえばハーフスペースもしくは2トップ脇に降りた時に、「ここに立ったら相手の右のサイドハーフかボランチどちらが出てくるか見れる。どちらも来なければ前を向いてプレーをすれば良いし、どちらかがマークに付きに来て、更に味方がそのマーカーの空けたスペースに立ってくれれば、無理せず自分を上手く利用してシンプルにそこを使えばいいし……」と。常に複数の選択肢を持っています。
守田が試合後に「後出しジャンケン」というワードを使っていたんですけど、これは僕も現役時代使っていた言葉で、相手を見て、自分がここに立てば優位だと思う立ち位置に先に立てば、その後、自分の予測できる範囲内で敵味方ともに周囲が勝手に動いていくので、それを見て最適なプレーを選択すればいいわけです。
結城 やっぱりそうなんですね。
中村 僕の現役時代から今も理想としているイメージは、ペップ・バルサです。ボールを70%以上保持して、相手には持たせない。シャビやイニエスタは、あの背丈で屈強なディフェンスたちの間の中間ポジションでボールを受け、相手をいなして、体を触らせない。そして、間を縫ってどんどんパスを回しゴールを獲り続ける。好みのスタイルは人それぞれですし、時代も変わってきていますが、僕にとってはあれがサッカーの完成形でした。
相手がプレーできないくらいのボール保持率と奪われたときの即時奪回力。立ち位置やパスをつけるタイミングや角度、守備のスイッチの入れ方など、当時はバルサの試合を何度も見て、徹底的に研究しました。
結城 なるほど。
中村 当時のバルサの選手たちは、システムの中である程度立ち位置は決まっているのですが、GKとCBの2人以外は中間ポジションで相手がどこからくるか、相手の出方を見ながら、みんなで立ち位置を変化させて、ゴールに向かっていきました。その作業を試合中ずっと続けながら、しかも、ボールを奪われない技術がある。相手を押し込んでしまえば、ボールを奪われてもすぐに切り替えることで取り返せる。頭と目と技術がとても優れていたと思います。
当時から自分がそういう理想を追っていて、風間さんが来た時、むしろ僕以上にボールを持ちたい人だったので、ボール保持をしながらゴールに向かうと言う点では理想をより追求できました。
結城 そうやって今のフロンターレにつながる土台が作られていったわけですね。
ポジショナルプレーは戦術ではなく概念
──中村さんがバルサのサッカーのイメージをチーム内で共有していく上で、結城さんが日本に広めたとも言える「ポジショナルプレー」という概念が説明をしやすくしてくれたという話をされていました。
結城 ありがとうございます。それは嬉しいですね。
──結城さんはWEB上で海外のサッカーに関する論文、戦術に関連する記事や書籍を翻訳し、発信するなかで『欧州サッカーの新解釈。ポジショナルプレーのすべて』という本も出されています。当初、論文などの翻訳を始めたのはどうしてだったんですか?
結城 ポジショナルプレーに関しては、昔から考えは存在していて、ヨーロッパで名書と言われるような本が日本でも翻訳されていました。ただ、それが日本のサッカー界では知られていなかったんですね。
これは他の戦術論にも当てはまる話で、日本側がキャッチアップできていないのか、ヨーロッパでも成熟していない概念だから伝わっていないのか。
ヨーロッパ最先端のサッカー思想は勉強になるのに、なかなか広まらない。
僕は大学院時代、図書館でサッカー関連の論文や書籍が簡単に漁れる環境にいたので「誰かに届け……」と、ひたすら紹介する生活をしていました。
『欧州サッカーの新解釈。ポジショナルプレーのすべて』に関しては、時期的にもいまさらながらの感はあったものの、WEB上に書いてきた内容を整理して伝えることが重要なのかなと思い、書かせてもらいました。
中村 サッカーではわかりやすい「言葉」があると、考え方や動き方の浸透がすごく早くなると思うんです。古くはアイコンタクト、ゾーンプレス、最近ではポジショナルプレー、5レーン、ハーフスペース……。
その言葉ひとつで「あれね!」と意識が共有できる。ただ、「言葉」に縛られやすいのも日本人の特徴かなと。
大事なのはどうやって相手のゴールに向かって点を取るかであって、その過程を整理するために特定の「言葉」を使うことが正しいと思っています。それを戦術にしてしまうのは危険だなというのが僕の考えなんですけど、結城さんはどう思いますか?
結城 僕も同意見です。そんななか、ポジショナルプレーという言葉がこれだけ使われるようになったのは、カバーする範囲が広いからでしょう。ただ、ポジショナルプレーは戦術ではなく、あくまで概念です。
「これ!」という正解はなくて、フアン・マヌエル・リージョが言う“ポジショナルプレー”、グアルディオラが言う“ポジショナルプレー”、アントニオ・コンテが言う“ポジショナルプレー”は概念が同じでも、ピッチへの落とし込み方は全然違います。
それをきちんと伝えたいんですが、言葉が独り歩きして、すごい武器のように思われてしまっているのは残念だな、と。流行れば流行るほど元々の意味と違った意味合いで使われてしまうのは、どの世界でもあることかもしれないですけど、それを思い知りました。
中村 でも、サッカー界に一石を投じたのは間違いないと思います。
結城 誰かの考えるきっかけになっていたらいいなと思います。でも、僕は何かを作ったわけではなくて、すでにあるものを紹介しただけなので。そういう意味では、改めてヨーロッパは進んでいると感じました。僕が翻訳しているものは、最先端のサッカーからは遅れている情報ですから。
中村 昔に比べたらその「ズレ」は確実に少しずつ埋まってきているとは思うんですが、世界の潮流をJリーグが即座にキャッチアップできていない現状はまだまだあると思います。
結城 メディアの責任でもありますが、「最新」と言われて紹介されている内容がヨーロッパ基準で言うと、全然、最新じゃないんですよね。
中村 僕はペップ・バルサに影響されているところがあるので、ポジショナルプレーという言葉は全く知りませんでしたが、バルサを見て勉強し続けたことで勝手に当時ポジショナルプレーをトライしていたのかなと思ってます。
元々、自分が相手を背負ったり、ぶつかったりしながらプレーできる選手じゃなかったので、学生の頃から相手とちょっと離れたところにポジションを取って、いかに自分がフリーでプレーするかを考えながらやってきました。
そこでペップ・バルサに出会って、相手を見ながら中間ポジションを取って相手を困らせ、ボールを支配し続けゴールを決めるサッカーを見て、「今自分がトライしているこのやり方は合っているんだな」と。
立ち位置ひとつで相手が自分にくるように仕向ける。守備をしている相手が困るような立ち位置を取る。複数の選択肢を持ってプレーをする。だから、改めて「ポジショナルプレー」と定義されたものを見ても新鮮さはなく、むしろ「ああ、これだよね」という納得感の方が大きかったです。
結城 ポジショナルプレーの概念は、トップ選手が感覚的に積み上げてきたものを言語化し、整理して、トップ選手以外の人でもできるように、組織として形になるようにまとめたものだと思っています。
ヨーロッパの選手たちは、日本の選手よりも我が強いので、彼らをまとめる方法論の1つなのかなとも考えています。だから、自らのプレーが相手を困らせるだけでなく、味方を助けるというポジショナルプレーの概念に触れたとき、「わかる」という感覚を持つ日本の選手は多いのかな、と。
その点、今日のお話を聞いて、憲剛さんや川崎の選手は早い段階からヨーロッパで作られた基準にキャッチアップし、自分たちのスタイルに落とし込んで、それが今のクラブの力の源になっているのかもしれないと思いました。
■プロフィール
中村憲剛(なかむら・けんご)
1980年10月31日生まれ、東京都小平市出身。小学生時代に府ロクサッカークラブでサッカーを始め、都立久留米高校(現・東京都立東久留米総合高校)、中央大学を経て2003年に川崎フロンターレ加入。06年10月、日本代表デビュー、10年の南アフリカW杯出場をはたす。国際Aマッチ68試合出場6得点。川崎の中心選手として17年、18年、20年とJリーグ優勝、19年にルヴァンカップ優勝と数々のタイトルを獲得。05年から19年まで15年連続Jリーグ優秀選手賞、Jリーグベストイレブン8回選出。16年には歴代最年長36歳でJリーグ最優秀選手賞。19年に左ひざ前十字靱帯を損傷し、長期間のリハビリを強いられながらも10カ月後に完全復活を果たす。20年限りで現役引退。21年より川崎フロンターレFrontale Relations Organizer(FRO)に就任。
結城康平(ゆうき・こうへい)
1990年生まれ、宮崎県出身。ライターとして複数の媒体に寄稿しつつ、翻訳・通訳・編集として活動。欧州サッカーを中心に「何でも屋」として複数のプロジェクトに参加している。海外サッカー専門誌『フットボリスタ』で「TACTICAL FRONTIER 進化型サッカー評論」を連載中。スコットランドで過ごした大学院生時代に培った英語文献を読み解くスキルを活用しながら「欧州最先端の戦術研究」に独自の視点でアプローチする。日本のサッカー論談にポジショナルプレーを紹介した伝道師としても知られる。
■関連記事
.movieBox {
position: relative;
padding-bottom: 56.25%;
height: 0;
overflow: hidden;
margin-bottom: 30px;
}
.movieBox iframe {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}
Follow @ssn_supersports




