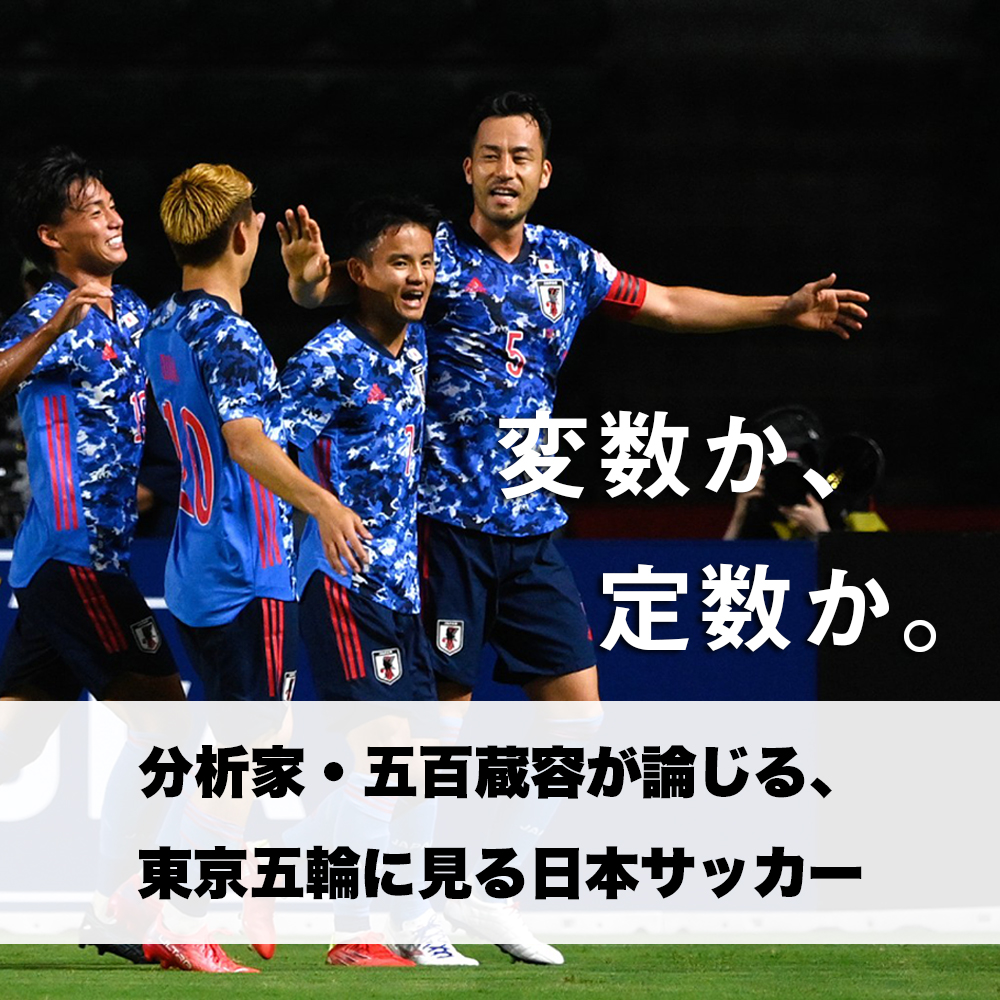
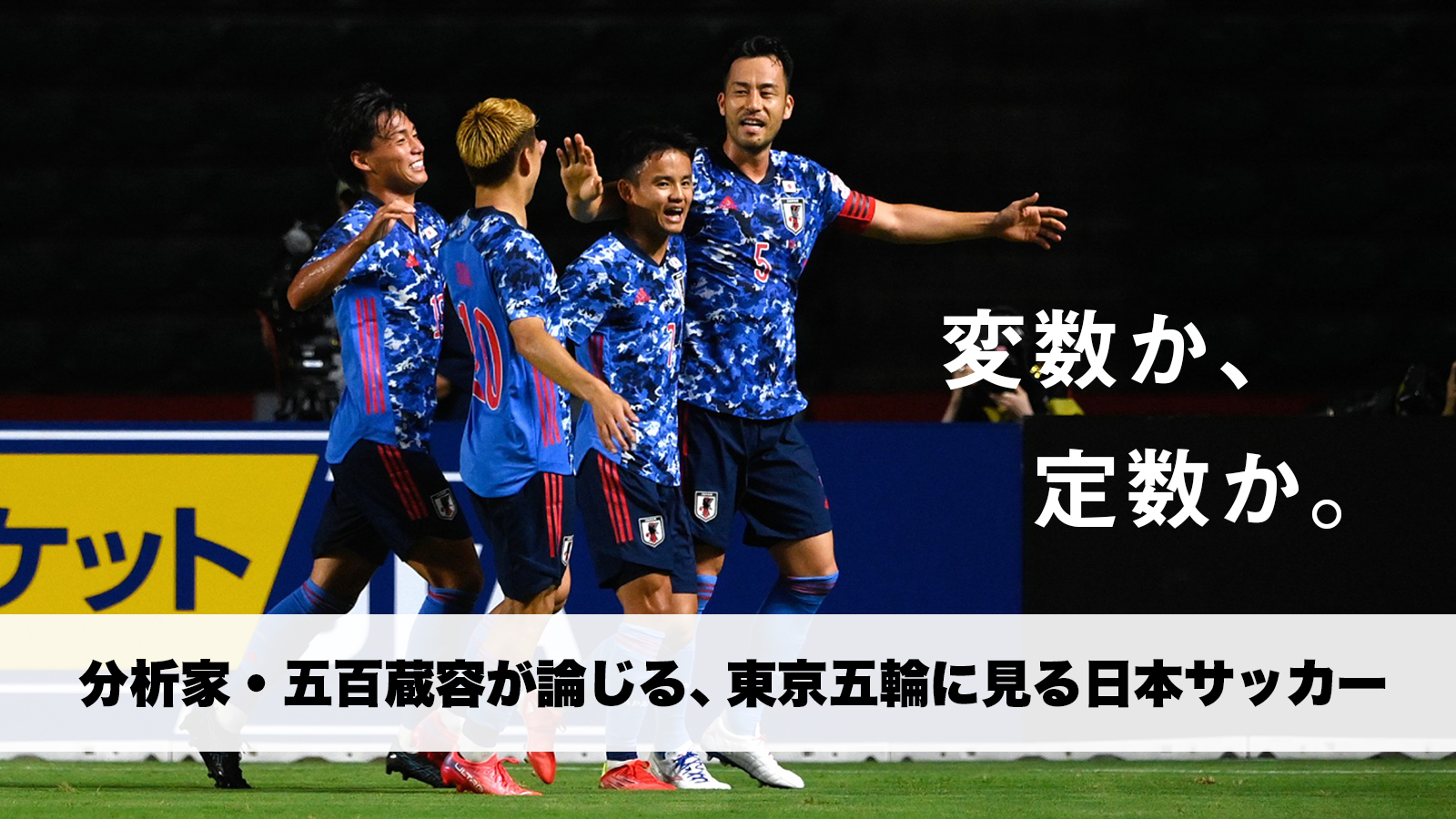
2021年東京五輪で金メダル獲得を目指した、森保一監督率いる男子サッカーU-24五輪代表チームは、躍動的で印象的なパフォーマンスを見せ、健闘しました。けれども最終的にはスペイン、メキシコといった世界的強豪チームに相次いで敗れ、金メダルどころかメダル獲得にすら至らないという結果に終わりました。
本論考では、U-24五輪代表チームが実施したサッカーを総括し「Japan’s Way」(ジャパンズウェイ)の再考も絡め、日本サッカーの現在地について検討したいと思います。
文:五百蔵容
写真:浦正弘
※記事内の表記
DH=ディフェンシブハーフ
CF=センターフォワード
CB=センターバック
SB=サイドバック
WG=ウイング
大会前に整備された攻守の組織と敗戦の原因
U-24五輪代表のサッカーは、五輪イヤー(延期後)である2021年に入ってからの強化試合で急速に整備されていきました。
それは4バックのゾーンDFによるブロックを敷き、ハイプレスとミドルプレスやカウンタープレスからのカウンター、ショートカウンターからチャンスメイクを狙うというもの。特筆すべきは4-4-2〜4-4-1-1〜4-2-3-1といった攻守における最小限の変化をベースに、相手のフォーメーション、やり方にアジャストしたマーキングとポジショニングを行い、攻・守・トランジション各フェーズでチームとしての狙いを整理していた点です。
対戦相手の分析結果の落とし込みや試合毎の作戦について必ずしもガッチリ固めることはせず、「選手に自主的に考えさせ、ピッチ上で答えを出させる」ことを主眼とする強化過程から、森保監督指揮下のフル代表、アンダー代表(U-24五輪代表)は、ともすれば「事前分析が疎か」「選手に考えさせると言いつつ、無策で放り出す結果に終わり、単に迷わせているのではないか?」といった批判を受けてきました。就任当初のアジアカップにおけるいくつかの試合(とりわけ初戦のトルクメニスタン戦、決勝のカタール戦)をはじめとして、相手のやり方に対応するのに時間がかかるため苦戦、苦杯を舐めることも多く、その指導方針には疑問が呈されてきたのは確かです。
ですが、本戦に向けて仕上がった五輪代表は、上記の整備を行うことにより、相手のやり方にアジャストする形、変化の幅を明確かつ最小限にし、そのことで選手が自主的な判断で修正を行う幅も限定、ゆえに個々の判断が同じ方向性を向きやすく、すりあわせがしやすい状態になっていました。
相手のフォーメーションに合わせたマンマークトラッキングを志向するハイプレス、ミドルプレスを主体に前向きな守備を試みつつ、守備から攻撃遷移時(ポジティブトランジション)には、縦方向に速く前進するバーチカルな攻撃を最優先に。
トランジションサッカーへの適性とプレス耐性が高く、リンクマンとしても優秀なDH(遠藤航、田中碧)から相手の急所にポジショニングしたアタッカー(久保建英、堂安律)へ縦パスをつけ、そこから相手の状況を見てドリブルなりコンビネーションなりで手数をかけずスピードアップして敵ボックスに迫る。縦のルートが得られない場合は、サイドにボールを運び、SBを起点にハーフスペースとアウトサイドの2択を軸に外側のスペースを使って前進する。
このシンプルな前進手段を生かす準備が日本はできていました。
本戦での対戦相手がほぼアンカーシステムないし3センターハーフのシステムを採用していたため、久保、堂安ら強力なアタッカーがその泣きどころであるアンカー脇やインサイドハーフの裏にポジショニングしつつ適時ワイドに開き相手のマークを曖昧にさせます。
その行動は必然的に「アウトサイドかハーフスペース、インサイドか」という2択を相手にせまる仕掛けと、五輪代表チームが「相手のやり方」とその変化にアジャストする方法の共通理解を両立させるようになっていました。
シンプルですが相手のやり方にあらかじめ適応したこのプレー構造を手にしていたため、日本の選手たちは縦にいければ縦、外が空いていれば外、と素早く決断し、状況に応じ判断を変えながらプレーできていたのです。
敵ボックスに攻め込んだ後、ボールを失ったらできるだけ高い位置で、ボックス近辺でもカウンタープレスをかけ奪い切る意識も高く、共通認識になっていました。やり方が整理されていることからバイタルエリアに進出したDHが自陣から脱出しようとする敵ボールの頭を抑えやすい(予測がしやすい)状態を手に入れていて、敵陣でのボール回収率を上げ、走力とその維持を要求されるこのサッカーで可能な限り体力消耗を抑え終盤まで求められる強度を維持することにつながっていたといえます。
チームとしての判断スピードは国際試合でも十分に通用するレベルに達しており、直前の強化試合や本戦のグループリーグではインテンシティ高く縦に攻め、守るトランジションサッカーが、2列目の攻撃力を生かした得点力を伴って十分に表現できていました。
この面に関して言えば、前線とディフェンスのタレントのクオリティ含め、これまでで最良のサッカーを見せていたとさえ言えると思います。

ですが、決勝トーナメントに入ると五輪代表のサッカーは急速に対応されていきます。
2列目のアタッカーを活用するやり方をケアする形で中央を封鎖され、サイドのビルドアップルートもインサイド・アウトサイドを経由するパターンを特定されて危険なプレッシングを受けます。選手個々のプレス耐性、デュエルの強度、アタッカーの個で打開しうる能力のおかげでボールを前進させることはできても、相手の泣きどころを急襲するスピードは減衰し、チャンスメイクの頻度、脅威度が低下していきました。
攻撃面で仕掛ける工夫が2列目に偏っていたのは強みでもありましたが、相手のレベルが上がるにつれ難しくなっていく要因でもありました。CFは2列目のパフォーマンスを生かすためのタスクを多数引き受け、2列目の内外のポジショニングやコンビネーションに連動して外側に開くなどボックスやシュート局面から離れる動きを少なからず行っていました。本来は得点源となるべきCFが2列目を生かすためのデコイ役に終始することを意味し、2列目絡みの攻撃ルートが封じられると打つ手がなくなる問題につながっています。
整備されたはずの守備についても、情況は芳しくないものになっていきました。
準決勝のスペイン戦は顕著でしたが、頼みのハイ&ミドルプレス、カウンタープレスが剥がされるケースが増え、とりわけボックス近辺でのそれが決勝トーナメントではほとんど効かなくなってしまいました。プレッシングの実効性が低下することで体力消耗を早め、疲労が蓄積し、最後の試合となった3位決定戦における細部のパフォーマンスに悪影響を及ぼす遠因になったかもしれません。
最終的に、グループリーグでは3試合で7得点・1失点でしたが、決勝トーナメントでは同じく3試合で失点は4、得点はわずかに1という結果に終わりました。
日本が志向するトランジションサッカーの妥当性
U-24五輪代表が行き着いたサッカーは、それ自体は高く評価できるものだと思います。
2019〜2020年度の欧州CLを、強度の高いプレッシングをチーム全体で敢行し続けるトランジションサッカーで制したバイエルン・ミュンヘンを、森保監督は「我々が目指すべき戦い方」と評していましたが、五輪代表は現時点での到達水準はともかくとして、その方向性を表現するチームとして整理されていました。
この方向性は国際的トレンドとしてしばらくは確実に続くものでもあり、世界にキャッチアップしていかねばならない日本の立ち位置を考えても妥当性のあるものと思えます。
この方向性の強みはもう一つあります。
インテンシティにおいて、従来日本選手の弱みに数えられていたデュエルにおいても代表選手個々のレベルが上がってきたため、予選では強度の高いプレッシングと守備で相対的にクオリティ差のある相手の攻撃の芽を着実に摘み、攻撃では個の力で仕留めに行けるでしょうし、イレギュラーな状況も個の質で凌ぎきれるでしょう。
本戦でも、相対的にクオリティがこちらより高い相手に対し守備をしっかり行う目処が立てやすく、世界水準に近づいてきたアタッカーの個とコンビネーションを生かして攻撃し、少ない得点機会を決めるといった展開を期待できます。
どちらの場合でも、自分たちのボトム(守備のブロック、フェーズ)を安定させ、相手のウィークポイントを割り出してそこに集中して縦に速いアタックを繰り出す、ということになります。これは日本代表の長年の課題──予選ではポゼッション主体のサッカーでゲームを支配し「格下」を退けるが、本戦ではボールが握れないため、予選とは異なる守備的なサッカーで臨まねばならない──を解消し、攻守のウェイト調整や作戦力の強化を施すことによって、ワールドカップ予選と本戦を同じコンセプトのサッカーで戦える可能性が高くなることを意味します。ポジティブな展望が開けそうです。
スペインと対極にある日本サッカーの問題点と対策
ただし、問題が2つあります。
一つは、短期的・戦術的問題。
本戦で明らかになったように、このやり方はより厳しいコンペティションとなる決勝トーナメントでは特に攻撃面、チャンスメイクの質量と得点力に大きな不備が生じることを露呈しました。
バイエルン・ミュンヘンやリヴァプールのようにプレッシング、ブロッキングできたとしても、上述のように最終局面の攻撃に深さをしばしば欠き、特定の選手、経路やコンビネーションを抑えられたら得点力が極端に低下しています。
少ない手数でバーチカルに敵陣侵入する攻撃、2列目の機動性と即興的なコンビネーションに依存した攻撃だけでは限界があったのは明らかで、より脅威を与えうる最前線のアタッカー(CF)を組み込み、相手の中央DFへのペネトレーションと2列目の機動性を組み合わせた、より多層的で豊富なバリエーションの実装が最低でも必要になるでしょう。
また、ビルドアップ面で戦略性に乏しいことも問題でした。縦に速い攻撃が抑えられた時に、ビルドアップによって相手陣形に動揺を与える術がほとんどなく、逆にシンプルなビルドアップルートに計画的なプレッシングを受けチャンスメイクされる状態でした。
これは単に、中央にゲームメイカー、「司令塔」を置き巧みな配球をさせれば済む問題ではありません。チーム全体の動的なポジショニングの組み合わせで相手の陣形に繰り返し打撃を与え、計画的にチャンスメイクする戦略性が必要になります。
例えばスペイン五輪代表は、質の高いポジショナルプレーを実装することで相手陣形を破壊可能な戦略的チームプレーを披露していました。
その鍵は、一見して目につくCBの巧みな球出しや中盤の流動性ではなく、WGとCFの仕事を基盤にしたチーム全体のポジショニング調整にあります。
スペイン代表のビルドアップでは、ボール保持者周囲のポジショニング調整で誰かをフリーにする巧みさが目立ちます。そのフリーマンに対し守備側は即座に対応できません。両翼のWGのポジショニングによって DFラインの動きが制御され、そのことによって生じるバイタルエリアのスペースをCFや内側に入ってくるWG、インサイドハーフが使おうとしているため、守備側のDHやCBはどこをマークするか常に判断し、対応を変えなければならなくなるからです。
そのことで「最も危険なエリア(バイタルエリア)でマークが曖昧になる」状況をスペイン代表は継続的に生み出すことができます。そして、その波及効果として、自陣側へポジションを移動するインサイドハーフへのマークが困難となり、そのマークをはっきりさせようとすると高い配給能力を持つCBへのマークが足らなくなり、結果としてどこかがフリーになってしまうのです。
スペイン代表が演出するこの「曖昧さ」は一時的なものなので、守備側はマークの受け渡しを調整して対応することができます。ですが、彼らはそこで生じるわずかな時間を利用してボールを前進させ、瞬く間にチャンスメイクしてしまいます。
彼らが個として得意とする──日本をはじめとして世界中で手本と見なされている──ゾーン間のポジショニング、相手のプレッシングやマークを引きつけるプレー、ワンタッチで素早くボールを動かすプレーの組み合わせは、この構造下でこそ活用可能です。
森保監督の五輪代表のやり方は、スペイン代表のそれとある意味対極にあると言えます。
日本は、相手の陣形を復原的に破壊しうる全体的なポジショニング戦略によって主導的に相手の守備に繰り返し問題を起こしボールを前進させるのではなく、プレッシングとデュエルのポイントを特定・設計し、相手のやり方がそもそも持っているウィークポイント、それでうまれるスペースにあらかじめポジショニングし、それをチームとして共有することで素早く縦に前進しています。
特定のシチュエーションやエリアにおいては流動性を見せるものの、相手の陣形やゲーム全体の趨勢を主導的にコントロールするようなマクロな流動性を得られる方法ではなく、その「限定的な流動性」を把握されケアされると打つ手がなくなるのは明らかでした。
もし現在のやり方を突き詰めていくのであれば、今回ある程度「整理」したことで明確化したやり方の「幅」をもっと広く取る、このやり方の中で複数のバリエーションを持てるように向上させていく必要があるでしょう。
そこでは当然、「幅を狭く取ったから選手たちの自主的な判断がそろいやすくなっていたのでは?」「そこを広げていくと、その判断がそろいにくくなるのでは」という問題も生じるでしょうが、「選手たちが自主的に考え判断する」コンセプトを堅持するのであれば、いずれにせよクリアしていかねばなりません。

2つ目は、中長期的・戦略的問題です。
本稿で見てきたように、今回のU-24五輪代表はかなり整理・整備されたチームになっていました。だからこそ課題や現時点での限界も明確に見え、「これからどうしていくか」を議論可能な水準に日本サッカーを立たせうる内容と結果になったように思います。
今後もこのやり方を突き詰めていくのか、それともその限界を越えるため別のやり方にシフトしていくのか。本論考でも注目した具体的な特徴、長所、問題、限界を共通の基盤として議論を発展させていけるのではないかと考えます。
そこで改めて、日本サッカーの長期的発展の基盤として提出されつつも、その曖昧さがしばしば批判の的となる、「Japan’s Way」(ジャパンズウェイ)をどう捉えるかという論点も具体性を帯びていくのではないでしょうか。
日本人らしさを生かしたジャパンズウェイ
ジャパンズウェイの曖昧さは、あえて良い意味に捉えれば、サッカーというゲームそのもののもつ曖昧さ、時代と共に変転していかざるをえない特性、余白に適合しているとも言えます。サッカーネイションの一つであるイタリアでは、サッカーは時に「丈の短い毛布のようなもの」とたとえられます。寒さを凌ごうと頭を覆えば足が出てしまうし、足をケアすれば頭が寒風に晒されてしまう。どんなやり方も、戦術も、システムもフォーメーションも、とりわけこのスポーツでは完全な方策とはなり得ないことをうまく表した比喩と言えます。
それはつまり、このボールゲームでは特定の戦術、ゲームモデル、特定の思考傾向に拠ることそのものがリスクになるかもしれないということです。サッカーにとって、それらは変数でしかない可能性があるのです。ですから、変数に拘泥(こうでい)するよりも、どんな状況でも不変と見なせる定数、基質のほうに潜心(せんしん)する必要があるのでは? という考え方には一定の説得力があるでしょう。
ジャパンズウェイがその定数、基質になりうるのであれば、それを担保した上で折々の時代、世代にふさわしいやり方、トレンドをその都度キャッチアップし、変数として代入・実装していけばいいということになります。
それこそがジャパンズウェイの意義であって、その曖昧さは「どんなトレンドにも適合していける柔軟性」と同義なのだ、というのであれば、一定の筋が通っていると見ることもできます。以前の日本代表が目指していたように見える“スペイン風のボールポゼッション”も、森保監督が今回実施した(そして今後も実施するであろう)ハイ&ミドルプレスとローブロッキング、バーチカルなカウンター主体のやり方も、「日本人らしさを生かした」という枕詞を冠せば「ブレ」でもなんでもないということになります。
一方、この見方に拠るならば、日本サッカーは必要であればジャパンズウェイの上で、あらゆる変数──ゲームモデル、戦術、システム──を適時、常に、迅速に導入し、国際的な競争力を十分に持ちうるクオリティで実施可能な状態であるべき、ということになります。
それは現実的と言えるのか? という大きなクエスチョンが当然そこには生じるでしょう。そして、その実現可能性が怪しいのであれば、“定数としてのジャパンズウェイ“にもまた「本当に定数、基質足りうるのか?」という疑義が再度投げかけられることになります。
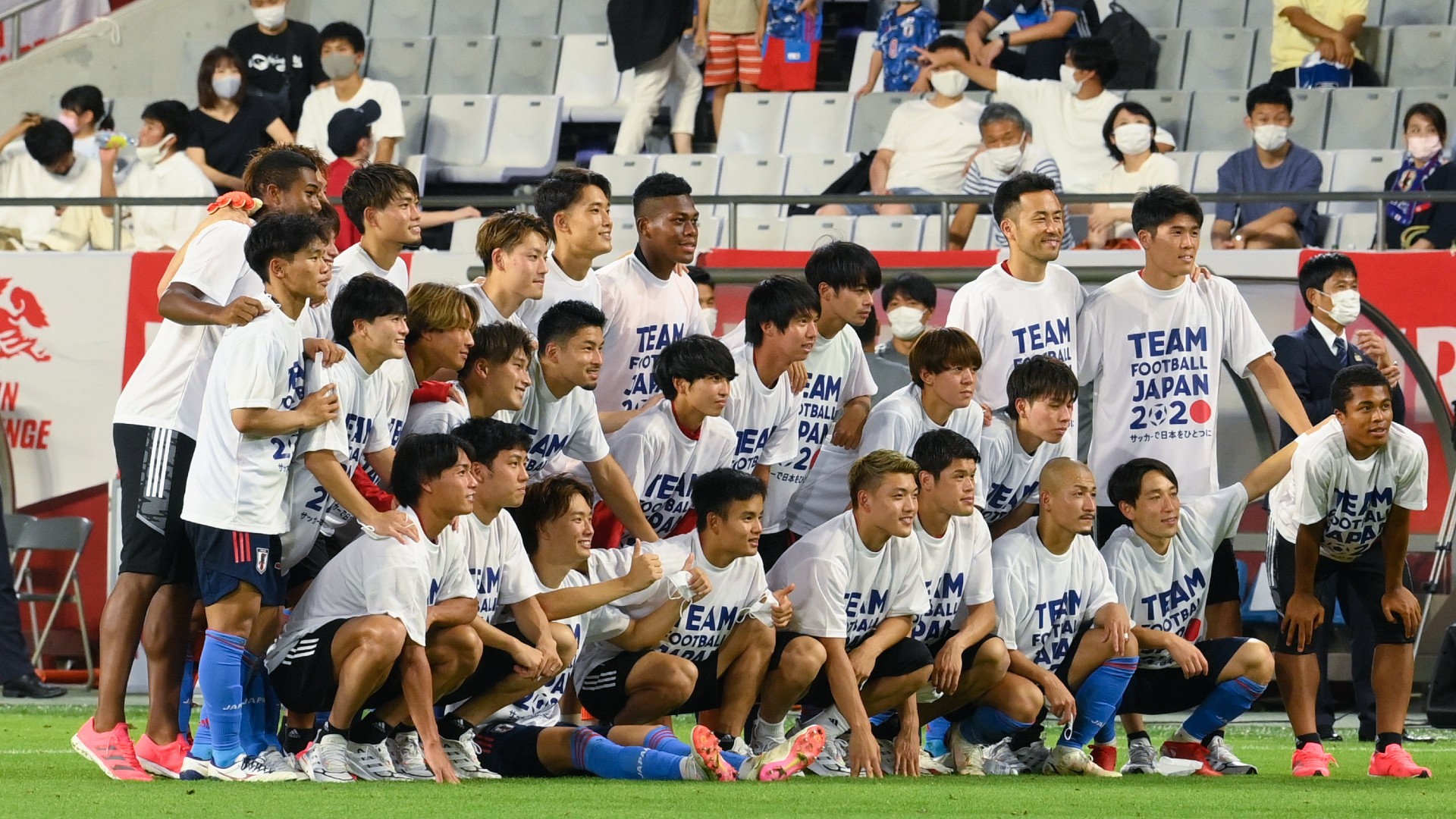
必要な“定数”は民族的・文化的な「らしさ」なのではないのではないか? 時代とともに変わるトレンド、様々な戦術・ゲームモデルを柔軟に受容可能とするために必要なのは、サッカーというゲームそのものに対する本質的な理解、知見なのではないか? と。
来年にはカタールW杯があります。日本サッカーにとって2020年代最大の目標の一つであった東京五輪での内容と結果を受け、サッカーを楽しみ、外側から支える私たちも、ロジカルで建設的な議論をますます盛り上げていく必要があると考えています。
▷分析家・五百蔵容の論考
- 2021.9.2|変数か、定数か。分析家が論じる、東京五輪に見る日本サッカー
- 2021.9.29|日本代表の弱点は、「試合が始まってから考えている」こと。
- 2021.11.10|柴崎のミスは、森保“委任戦術”の必然?変化に対して脆弱な日本
- 2021.11.11|森保監督は、「コンディション問題」を選手に解決させている?
▷分析家・五百蔵容へのインタビュー
- 2021.12.17|活路は“必然の誘発”にあり?日本代表の伸びしろと限界値
▷プロフィール
五百蔵容(いほろいただし)
1969年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部を卒業後、株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガゲームス)に入社。2006年に独立・起業し、有限会社スタジオモナドを設立。ゲームを中心とした企画・シナリオ制作を行うかたわら、VICTORY、footballista、Number Webなどにサッカー分析記事を寄稿。著書に「砕かれたハリルホジッチ・プラン 日本サッカーにビジョンはあるか?」「サムライブルーの勝利と敗北 サッカーロシアW杯日本代表・全試合戦術完全解析」(いずれも星海社新書/2018年刊)がある。
Twitterアカウント:@500zoo
Follow @ssn_supersports




