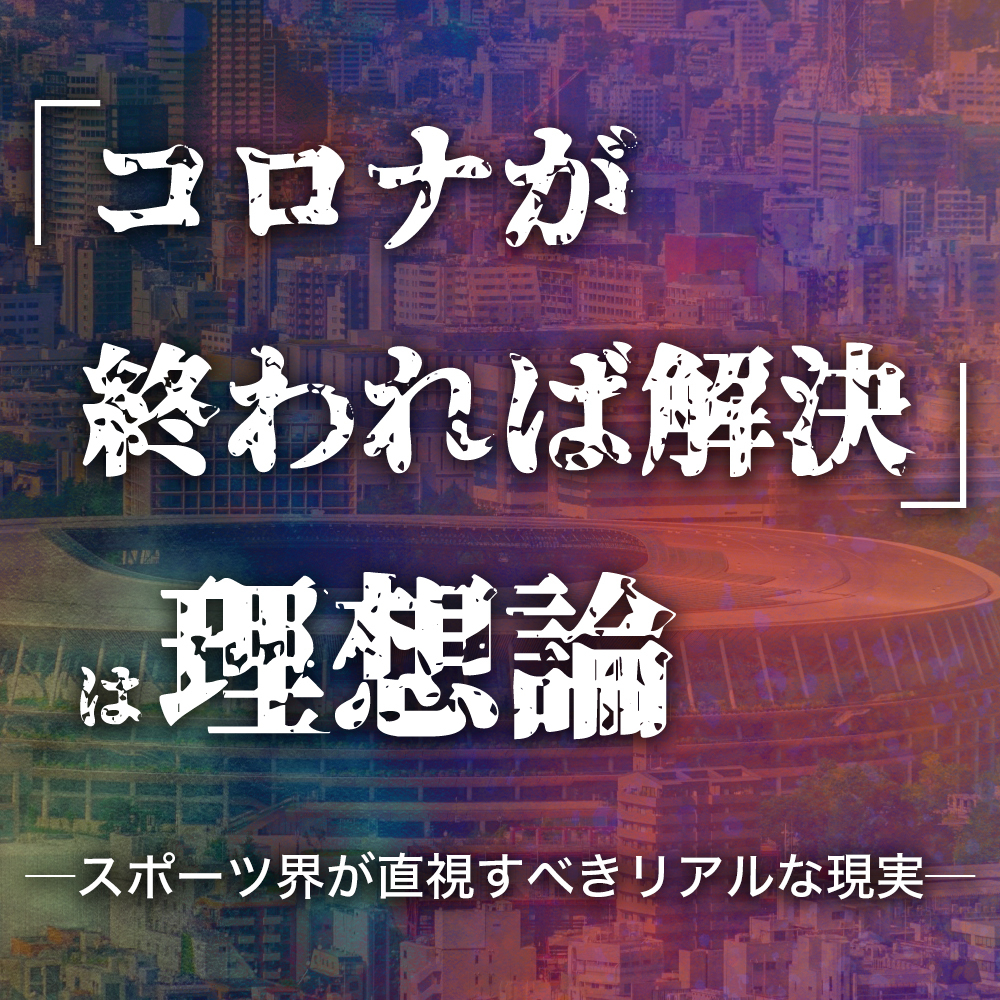
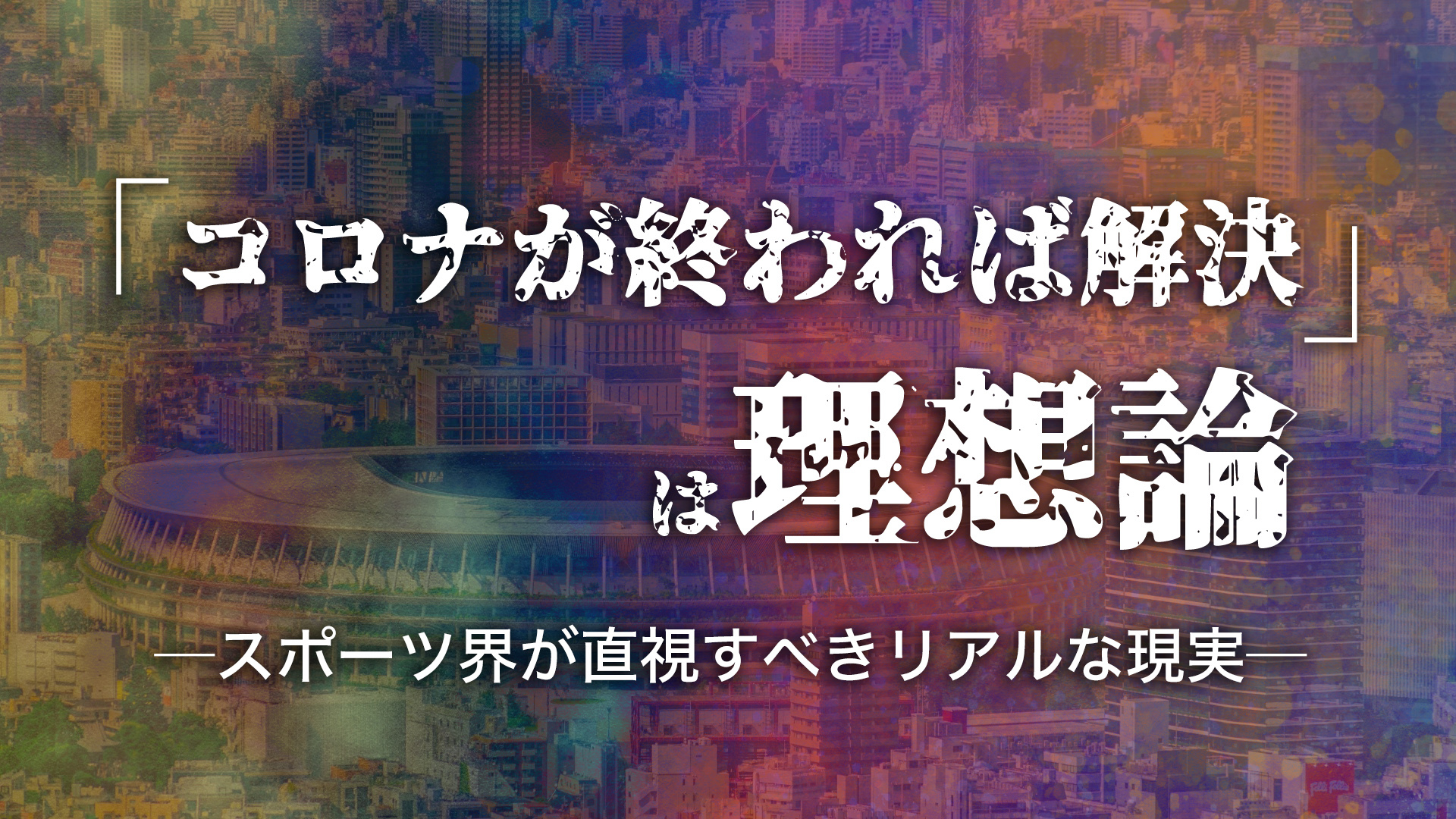
2022年のスポーツ界で大きなテーマとなりそうなのが「観客数制限解除」です。新型コロナウイルスの感染拡大に怯えて過ごしてきた2年間でしたが、Jリーグはついに新シーズンから観客数の制限を設けずに試合の開催を目指すことを発表しました。
満員のスタジアムで、仲間と一緒にチームを応援する光景が戻ってくるかもしれません。しかし、日本で数少ないカジノの専門研究者である木曽崇氏はこの見方に警鐘を鳴らします。
「コロナが終わればお客様が戻ってくるというのは理想論」という、木曽氏に日本スポーツ界の未来を伺いました。
■目次
・日本で開催された五輪でも4割は興味なし
・観戦はライブからオンラインに移行
・ビジネスモデルを変えるタイミング
・オンラインで代替可能な業界を生き残るためには?
日本で開催された五輪でも4割は興味なし

──木曽さんはYouTubeチャンネルで“スポーツ観戦率”の調査をされていました。これは何を検証するために行なっているのでしょうか?
木曽崇(以下、木曽) 東京五輪という大きなイベントが、スポーツ観戦に与える影響を調査することが目的です。五輪を誘致する際に、さまざまな論争がありました。その1つである経済効果については、無観客開催となったため思い描いていた結果は実現していません。
もう1つ言われていた「五輪を開催することでスポーツに対する興味、関心が高まる」という部分が、本当なのかは誰も検証していません。そこをもう少し数字で見ていきたいなというのが調査の目的です。
──調査の結果、五輪開催の影響はありましたか?
木曽 2020年との比較で、何かしらのスポーツ競技を観戦した方が15%増加しました。これはスポーツ業界にとっては大きな成果だといえます。
──どういったスポーツの観戦率が増加したのでしょうか?
木曽 主に五輪で扱われるようなマイナースポーツの観戦率が、メジャー競技と比べて顕著に上がっています。アマチュアスポーツの祭典と言われる五輪ならではの現象です。また、野球やサッカーなど、五輪がない通常の年でも観戦率が高い競技も、ベースが上がっています。
──なかでも印象的だった競技はありますか?
木曽 観戦率が18.2%だった卓球です。日本のスポーツ界は、2020年のデータが示すように野球(20.5%)、サッカー(14.7%)、相撲(11.3%)の順番で観戦率が高い。しかし2021年は、卓球が相撲(12.0%)を上回りました。
他にも水泳(14.4%)、陸上(16.0%)、バレー(13.4%)など、アマチュアスポーツであり、五輪でメダルの期待が高い競技が、相撲を大きく上回る結果になりました。
──メジャー競技の野球とサッカーは、もともとの高い数字からさらに伸ばしています。この2競技の分析はいかがでしょうか?
木曽 データを見ていると、サッカーよりも野球がうまくやっている印象です。それは野球に関する好材料が多かったためです。
昨年はセ・リーグはヤクルト、パ・リーグはオリックスと、前年に最下位だったチームがそれぞれ優勝しています。また、メジャーでは大谷翔平選手が活躍しましたし、五輪では金メダルを獲得しました。高校野球を見ても2020年は交流試合でしたが、2021年は甲子園が復活しました。このような好影響が、いい数字が出ている要因だと思います。
一方でサッカーは、Jリーグが奮わない。観戦率はマイナスではないですが、野球の国内リーグの増え方と比べると、横ばいに近いです。サッカーの五輪代表については、観戦率が5%増加しています。しかしそれが国内リーグへの興味・関心に繋がっていません。
ただ、これはあくまでも野球との対比。今年は野球が出来すぎているので、サッカーにとってはかわいそうな結果でもあります。
──野球とサッカーで差ができた要因は?
木曽 2021年の野球は、出来すぎです。話題になるようなニュースがたくさんありました。その野球と比べてしまうとサッカーはかわいそうですが、一方で構造上の問題もあると思います。
野球の五輪チームは、国内リーグの選手たちから選ばれて結果を残しました。しかしサッカーは基本的に海外組です。五輪代表が活躍しても、日本で彼らの活躍を見る機会が少ないため、観戦に繋がりにくい。五輪代表に興味ある人が、国内リーグの視聴に移る可能性はかなり低くなってしまいます。
──スポーツへの興味・関心が増加したなかで、現地での観戦はどの程度増えたのでしょうか?
木曽 野球とサッカーについてさらに分析している段階ですが、残念ながら会場に足を運んだ方は増えていません。実際に会場へと足を運んだ方は、サッカーは全体の4%、野球は全体の5%となりました。
この数字は、2020年も2021年も変わっていません。どちらの年も、観戦に対して大きな制限があったので、このような低い数字になったのだと思います。
──東京五輪を経て、アマチュアスポーツはマスメディアで取り上げられる機会が増えました。一方で今後は露出が低下し、競技情報がユーザーに届きにくくなることが予想されます。
木曽 それは多くのアマチュアスポーツが抱える問題点です。水泳、卓球、バレーは、五輪の好影響で顕著に観戦率が増えました。ただ、継続的に見る環境があるかといえばそうではない。ほとんどのアマチュアスポーツ競技は、放送そのものがありません。五輪に興味を持った方々が、2022年も同じように観戦するかといえば、難しいと思います。
それに五輪は4年に1回行なわれているスポーツの祭典。しかし2020年の時点で、45.4%の人たちしかスポーツを観戦していません。2021年はそれが60.7%にまで上昇しましたが、今後の数年で低下する。そしてまた五輪で上がるといったことを繰り返しているのです。
──日本で行なわれた五輪でも、およそ6割しか観戦していなかった事実に驚きました。
木曽 いずれかの競技を観戦した方は6割で、日本開催でも4割は関心がない。そういうものだと改めて思いました。
観戦はライブからオンラインに移行

──2022年に入り、さまざまなスポーツが新シーズンを迎えています。先日行なわれたサッカーの日本代表のアジア最終予選では、観戦者に2回のワクチン接種証明か72時間以内のPCR検査結果を求めていました。このような施策は、今後のスポーツ観戦で必要なものとなるのでしょうか?
木曽 正当性を持ってイベントを開催していい根拠として、必要になってくると思っています。
コロナの感染再拡大が始まり、しばらくは何かしらの制限下でやっていかなければいけません。エンタメ業界などの集客業種が、イベントを行なえない状況が続くと産業は潰れてしまいます。
そうならないためにも、感染対策に配慮していることを客観的に証明するものが必要です。ワクチンパスポートや日本代表戦のような施策が、今後は大事になってくると思います。
──木曽さんは前々からワクチンパスポートの普及を呼びかけています。
木曽 感染拡大が、必ずまた起こるという前提があるからです。われわれは一歩ずつ前に進んで、今の環境に適応する必要があります。
残念ながら今はずっと同じことを繰り返している。コロナの感染が治まってくると気持ちが大きくなり、感染が拡大するとみんなが落ち込んでしまう。それを繰り返すだけでは産業が潰れてしまうので、螺旋階段のように少しでも上に発展していくことが大事です。
今の環境にいかに適応するか。そのなかで、ワクチンパスポートを代表とする手段が必要になってくると思います。
──今回の日本代表戦の観客は、1万1753人でした。日本代表の不人気もあると思いますが、一方でワクチン接種証明やPCR検査結果の提示など、観戦するための壁が大きくなっています。スポーツ産業が元通りになるには高い壁のように思います。
木曽 おっしゃる通りで、元通りになるのはかなり難しいと思います。コロナ禍により、視聴はオンラインへと移行しました。スポーツ産業だけでなく音楽産業も、お客様が戻ってこない状況が続いていて、他の産業でも問題になっています。
コロナが治れば、足を運んでくれていたお客様が現場に戻ってくるだろうと、多くの人たちが考えていました。しかしそれは理想論であって、現実的には戻ってこない。その前提での準備が必要です。これはライブエンタメ業界全体で、準備をしなければいけないことだと思います。
──コロナ禍により、自宅での視聴体験を経験したことで新たな選択肢ができました。ワクチンパスポートなどの壁を越えてまで、現地に行かなくてもいいという消極的なマインドを感じます。
木曽 コロナ禍だからなおさら現地に足を運びにくい。そんなコロナ禍もいつか明けます。その先に、ライブエンターテイメント側が思い描くようにお客様が戻ってくるかといえば、そうではないでしょう。
実は、音楽エンタメ系のアンケートではそれが見え始めています。お客様たちは、大体のことがオンラインでできると知りました。これまでライブで体験をしていた人たちが、オンラインを経験したことで、今後は「オンラインで視聴する」と答える比率が高まっています。現地ではなくてもオンライン視聴による満足度が高まっているわけです。
ビジネスモデルを変えるタイミング

──ライブエンターテイメント産業にとっては大打撃です。
木曽 これはどっちが良い悪いの話ではありません。私自身が産業側の人間なので、お客様たちに足を運んでもらう方が嬉しいですが、オンライン配信のビジネスモデルが確立できていれば問題ないと思っています。
スポーツにしても音楽にしてもコンテンツです。われわれは会場やスタジアムを通して、お客様にそのコンテンツを届けることが一番だと思っています。しかしお客様側が、オンライン視聴を求めているのであれば、ビジネスモデルを変えるしかない。オンラインでの視聴を求められているのであれば、それに合わせることが自然な流れです。
コロナ禍が明けて、お客様のニーズがどう変わるのかを注視して、変わっていくならわれわれも変わる必要がある。このままライブエンターテイメントを行なうことがダメと言う風潮でいくなら、消費に合わせてわれわれも変わる準備をしなければいけないということです。
──コロナ前を上回るためには、コロナ前に戻すことではなく、トータルで成長していけばいいという発想ですね。
木曽 コロナ前に戻すという発想があってもいいと思っています。戻りたいという思いは当然ですが、戻らない場合に変わる必要があることをわかっていないといけません。トータルで見てスポーツ産業の市場規模が大きくなれば、そこに関与している人たちは幸せに生き続けられます。
また、これからのスポーツ産業はスタジアムで5Gの敷設が始まることで、大きく変わっていくと思います。マスメディアに取り上げられなかったスポーツ競技が、インターネットを介して配信できるようになっていきます。
そこにコロナ禍が重なったことで、スポーツの配信サービスが加速しています。今後はオンラインが主流になる可能性を念頭に置いて、現場とオンラインの両方でビジネスモデルを作らないといけません。「コロナ前に戻るんだ」という思いはいいですが、それだけに固執してはいけません。
──これまでもアリーナを満員にしてきたようなメガアーティストや競技団体ならば、コロナ後も満員にできるかもしれません。そうではない人たちは、アリーナ規模を小さくしながらも配信をやる。2つのマネタイズポイントを作ることが大事になりますね。
木曽 お笑い芸人たちは、そういう動きをしています。地上波に出るところがゴールで、そこに至らない人たちは、劇場にお客様を集めてパフォーマンスを見せていました。しかし今は、劇場の運営ができない。だから、彼らはYouTubeの個人チャンネルで配信するようになりました。
スポーツや音楽の人たちも、そうならざるを得ない。今までのメジャースポーツのゴールは、マスメディアに放送してもらうことでした。しかし今は、限られた少ない枠を争うのではなく、インターネットメディアで何ができるかを探すべきです。
どんな業界でも、集客できないのならばビジネスモデルそのものを変える必要があると思います。
──大きな分岐点ですね。しかしリアルからオンラインに変わることで体験価値が下がるのでは?
木曽 そこは上がる部分と下がる部分があると思っています。ライブ感や場の雰囲気を含めた感動は、会場で体験する方が大きい。一方で、会場でしか見られなかったものが、手元のPCやスマホで恒常的に見られるようになっていく。これはまた別の価値があると思っています。リアルとオンラインでは、違うものを提供していると考えるべきです。
コロナ禍当初は、スタジアムでの観戦価値をそのままオンラインに置き換えようとしました。アバターを作って、仮想空間のスタジアムに座らせていました。しかしリアルの価値を、そのままオンラインに移行するのは無理です。違う価値を作るべきでしょう。
──リアルにはリアルの良さ、オンラインにはオンラインの良さがあると?
木曽 その通りです。なので、現在のスポーツ放送に違和感があります。今見ているものは、マスメディアが流しているものと同じです。われわれは、テレビで以前から見ていたものをオンラインでも見ている。オンライン前提で考えた場合は、違うやり方があると思います。
F1や競馬、競輪では、いろいろな視点での放送が、試験的に行なわれています。F1なら、コックピットを見たい人は、そこからの映像を見られるようになっています。
そのほかのスポーツは、今までマスメディアが放送していたものと同じ形になっている。オンラインならではの価値を作る必要があります。オンラインは、スタジアムで見るリアルと、マスメディアで見るものとの間にあります。リアルかマスメディアに寄せるのではなく、オンライン独自の配信を追求した方がいいです。
──オンラインがスタジアムでの観戦やマスメディアでの観戦よりも優れている部分とは?
木曽 例えば、オンラインは尺の規制がないところがウリです。劇場やライブハウスには1時間や2時間の尺があります。マスメディアも同様に、放送枠という尺の中に効率的に収まる放送をしています。
でもオンラインには尺がない。メイン配信をする傍ら、くだらない楽屋での裏トークが延々とあってもいいわけです。むしろそれがウリで、スポーツ競技の配信については、もっと何かができるのではないかと思います。
──しかしオンラインに移行すると成立しなくなる産業もあります。例えばスタジアムグルメなどは、スタジアムにくるお客様が減ると営業が難しくなります。
木曽 おっしゃるように、これまでとは別物になることでシュリンク(縮小)する人たちがいます。なので一方ではコロナ前の状態に戻す可能性は持っているべきで、既存の産業を守りたいという気持ちは必要でしょう。
この話は、コロナが収まっていない今だと、まだ少し早いかもしれません。しかしお客様を連れ戻すために、スタジアムに来る価値を高めることを考えなければいけません。それはスポーツ観戦を総合エンターテイメント化することに尽きます。
オンラインで代替可能な業界を生き残るためには?

──スタジアムでの観戦価値を高めるための施策?
木曽 そうです。スポーツを見ることは、オンラインでも可能だとわかりました。よって観戦の外側にどれだけの付加価値をつけるか。そのためには1つの統合体験にすること。オンラインのビジネスモデルを考えることと並行して、スポーツ観戦の総合エンターテイメント化も考えておく必要があります。
これはカジノ業界も同じ。われわれはコロナに関係なく、2000年代半ばからオンラインカジノに取って代わられている業界です。ギャンブルのゲームを提供するだけなら、オンラインで可能となっています。
だからこそ、カジノ業界はこの15年ほどで統合型リゾート化を進めています。つまりはギャンブルの外側の整備です。
──シンガポールのマリーナ・ベイ・サンズなどは、カジノを中心とした複合型エンターテイメント施設が並んでいます。
木曽 まさに、滞在の価値を高めた結果があの形です。ゲームを提供するだけではなく、遊びに行く人たちが何を求めているのかを考えて作られています。宿泊施設、食事をする場所、ゲーム以外のエンターテイメントなどが加わり、今ではショッピングセンターやリラクゼーション施設も併設されています。
──オンラインでは味わえない価値を提供していくことが大事ですね。
木曽 今は、どの業界もオンラインで代替される恐怖を持っています。われわれもしかり、出版業界もそうでしょう。これまで紙で出していたコンテンツが、デジタルに代わっている。どの業界でも起こり得ることです。
そのなかでカジノ業界は、ゲームの外側に価値を作り出しました。同じようにスポーツ業界も、観戦の外側にどれだけ価値を作れるかだと思います。そこを本気で考えなければ、オンラインが手軽になるに連れて、リアルで見る価値はなくなっていくでしょう。
──観戦の外側の価値創造は、徐々に日本のスポーツ界でも出てきていると思います。北海道日本ハムファイターズがやろうとしているボールパーク化はその例なのでは?
木曽 日本ハムもですし、そもそもはDeNAが横浜スタジアムでやり始めたことです。そこから、広がっていき、日本の野球ではモデルができつつあるように思います。サッカーはもう少し頑張らないといけません。その他の競技はまだまだですね。
──スポーツを見るだけなら、家で手軽に見られるオンラインに置き換えられてしまいますね。
木曽 このコロナ禍で、観戦はオンラインで可能だということがわかってしまいました。「それでいいや」と思われないようにしなければいけません。
ライブにはライブにしかない価値があります。みんなで観戦し、応援して、感動する。そういった特別な価値がありますが、それに甘えてはいけない。どんどん外側に向かって価値を増幅させる。そのためになにが必要かを考え続けないといけません。そうしなければ、オンラインに取ってかわられるでしょう。
■プロフィール
木曽崇(きそ・たかし)
日本で数少ないカジノの専門研究者。ネバダ大学ラスベガス校ホテル経営学部首席卒業(カジノ経営学専攻)。米国大手カジノ事業者グループでの会計監査職を経て、帰国。2004年、エンタテインメントビジネス総合研究所へ入社し、翌2005年には早稲田大学アミューズメント総合研究所へ一部出向。2011年に国際カジノ研究所を設立し、所長へ就任。2014年9月26日に新刊「日本版カジノのすべて」を発売。
■関連記事
- 「東京五輪は、何を犠牲にしたのか」今こそ知ってほしい。ある専門家の独白
- 日本のスポーツ観戦が元通りになる日は来るのか?木曽崇(国際カジノ研究所)
Follow @ssn_supersports




