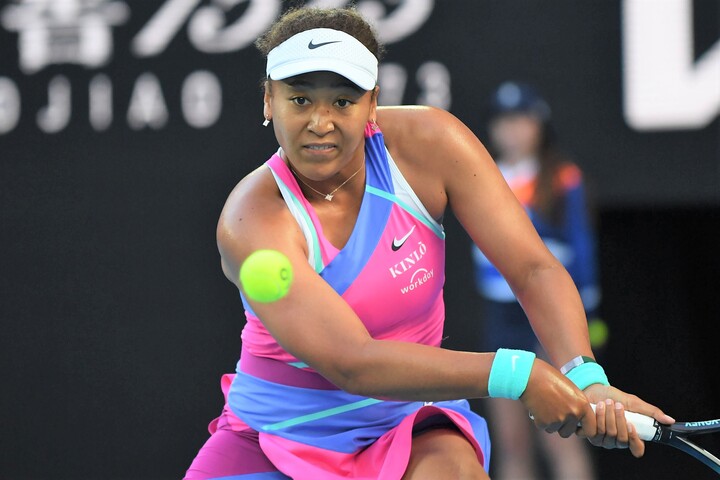「自分のピークは20代後半」有言実行となった全豪オープン。ダニエル太郎は独自のテニス人生を歩む「自分は芸術家だ、と信じたい」<SMASH>

191センチの長身に乗る小さな顔は、10代の頃とあまり変わらぬあどけなさを残す。短く切り揃えた髪が、童顔をさらに若く見せていた。
ただそんな彼も、今年の1月27日で29歳を迎える。初めて立つ全豪オープン3回戦の舞台でネットを挟む相手は、20歳にして世界の10位につけるヤニック・シナー。このイタリアの俊英を筆頭に、昨今の男子テニス界では、20歳前後の大躍進が相次いでいる。その趨勢のなかではダニエルも、年齢だけを見れば、ベテランの領域だ。
アメリカに生まれ、日本とスペインで育った多様な文化的背景にも根差す資質だろうか。ダニエルは物事を多様な視点でとらえ、咀嚼し、言語化する能力に長けた青年だ。そんな彼だからこそ、これまでにも個性的で、時に哲学的ですらある“テニス人生観”を数多く語ってきた。とりわけ印象に残っているのが、22歳の頃に口にした長期的ビジョンである。
「まだ身体が出来ていないので、毎年2キロずつ筋肉をつけて、5年後に10キロ増やしていたい。そのころには、テクニックや経験もそろってくるだろうから」
身体が資本のアスリートにとって、5年という年月は、長い。ましてやテニスプレーヤーは、グランドスラムという究極の舞台を、年に4度のハイペースで戦うのだ。だからこそ多くの選手は、早急に結果を求めやすい。
ところがダニエルは若い頃から、「自分のピークは20代後半。もしかしたら30歳を超えてから来るかもれない」と、どこか悠揚と構えていた。そして自身の言葉通り、28歳となった今、彼は確実に新たなステージへと歩みを進めている。
ダニエルが、期は満ちたとばかりにスベン・グレーネフェルトをコーチに招いたのは、27歳を控えた2019年末のことだった。
「僕は、あと10年くらいはテニスをできる自信はある。ただ27歳になり、タクティク(戦術)やテクニックを改善する一番のチャンスは今かな、と思ったんです」。実際にダニエルは、新コーチと共に多くの変革に取り組んだ。
ラケットを短くし、早いタイミングでボールを捉えることで、相手の球威も生かしボールを飛ばす技術を習得。その上で、ボールを左右に動かし、チャンスを見ては前にでる攻撃的なプレーを志向する。
今大会で大きな結果を出したために注目を集めたが、変化は昨年から見られていた。目指すテニスが一層の精度で噛み合い、結果がさらなる自信と勝利を生んだのが、今回の躍進の真実だ。
シナー戦のダニエルは、アンディ・マリーに勝ったのが決して運や偶然ではないことを、詰めかけた観衆の前で示した。
立ち上がりで3ゲームを続けて落としたのは、緊張というより、スタジアム特有の環境のため。今年からお披露目になったKIAスタジアムは、ショップやステージが並ぶ“お楽しみ広場”の隣に位置する。そのため試合中にも、客席の椅子が揺れるほどの音量で音楽が聞こえるのだ。それら外界の騒音が、打球音と実際の球速の間にズレを生んだという。
「相手が強いボールを打っていても、あまりそういう風に聞こえなくて。ポワッと聞こえるのに強いボールがきて、それに戸惑った」。その戸惑いを実体験で埋めるにしたがい、スコアの差も縮まっていく。特に第2セットでは、多くの局面でダニエルが世界10位を圧倒した。
ショートアングルで相手を追い出すと共に踏み込んで、返球をすかさずストレートに叩き込む。あるいは、相手の強打をフォアのスライスでストレートに流し、ネットに出てくる相手を呆然とさせた。ダニエルが5ゲーム連取の猛攻を見せた時、アリーナの客席から、「タロー」コールが沸き起こる。それは、リスクを恐れず攻める勇気が、見る者の心を震わせたから。
「彼のニックネーム、Doc Taro(太郎博士)はどうかしら?」。 客席の一角では、そんな声も囁かれた。
「第2セットでの彼(ダニエル)は、全てで僕より上を行っていた」。シナーは後にそう述懐し、ダニエルに最大級の敬意を表した。ただ、ダニエルがシナーの強さの深淵を知ったのは、直後の第3セットだったという。
予選から5試合戦ってきたダニエルが、多少の疲れを見せたその時、シナーは、一気にプレーの質を上げてきた。
「あの時にシナーが上げたレベルはすごかった。僕も疲れていたけれど、すっごいレベルを落としたとは思わなかった。でも彼がバーッときたので、なんじゃこれと正直思っていて」
真のトップ選手が発する威圧感は、対峙した者しか感得できない空気の変化なのだろう。その圧力を覚えるなか、第8ゲームでダニエルは3連続のブレークの危機に瀕するが、「マックス・リスクのプレーでデュースにした」。
そして、次のポイント——。203キロのファーストサービスは、ネットに掛かる。続く、セカンドサービス。全力でセンターに叩き込んだサービスに、電子音の「フォールト」の声が飛ぶ。電光掲示板の速度計には、205キロが表示された。
この時のブレークポイントはバックのウイナーでしのぐも、その後は同じようなポイントパターンで、決めにいったバックを連続で外す。
結果的にはこのゲームが、試合のターニングポイントになっただろう。第3セットを奪ったシナーは、一度アクセルを踏み込んだ足を浮かすことなく、一気に勝利まで走り抜けた。
「あのゲームは、デュースからまたマックス・リスクで攻めたら、ミスがでちゃった。でも、あれはあれで良かった」。熱戦の結末から、約1時間後。試合の分岐点となったゲームを、ダニエルは淡々と振り返った。
「次に上位の選手とやった時に、相手が『こういう場面で太郎は絶対に粘ってくるんだ』と思っている中で僕がダブルファースト(セカンドでも速いサービスを打つこと)をすれば、取れるかもしれない。あの場面でポイントを取るためだけに、取ったリスクではない。今後にも続くリスク」
それが、ダブルフォールトに込められた思い。観ている者も痺れるあの状況下で、彼は目先のポイントよりも将来を見据え、勝負を仕掛ける経験値を選んだというのだ。そのようなこちらの驚きを、察しただろうか。
「あれを取れていたら、展開が違っていたかもしれないので残念ですが……へっへっ、しかたないです」。そう言い彼は、照れたように笑った。
テニスの上達を人生観と重ねる彼の視座は、今も昔と変わっていない。
「自分は芸術家だ、と信じたいなと思っていて。ハードワークというより、自分がやりたいからやるというテニスキャリアと人生にしていきたい。そういう風にとらえていけば、勝っても負けても……もちろん勝ちたいですが、そういう風に思っています」
芸術家とは、自己表現こそを最大のモチベーションとする生き方のメタファー(比喩)なのだろう。キャリア最大の大舞台をも自己表現の一部ととらえ、この先もダニエルは確かな足取りで、独自のテニス道を歩んでいく。
現地取材・文●内田暁
【PHOTO】全豪OPで快進撃を演じたダニエル太郎の厳選フォトギャラリー
Follow @ssn_supersports