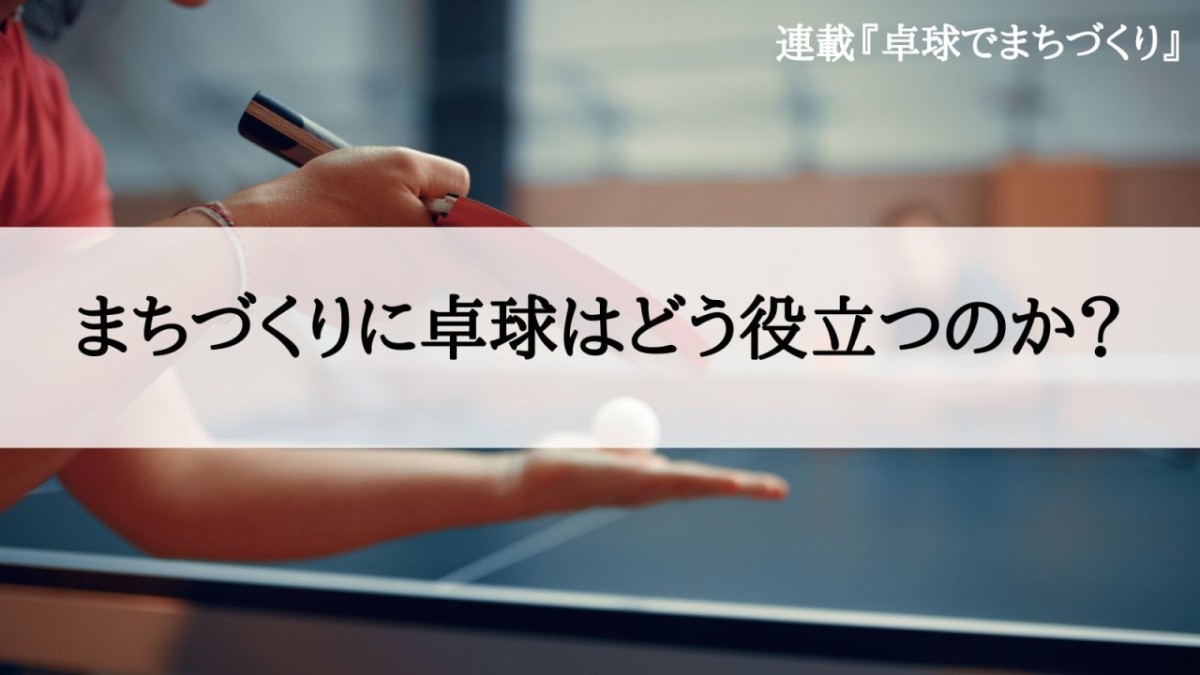
はじめまして。
NPO法人日本卓球療法協会理事長の長渕晃二と申します。
私は長年、介護・福祉やまちづくりに携わってきましたが、そのいずれにも卓球が活きることはたくさんありました。
そこで本連載「卓球でまちづくり」では、わたしのこれまでの経験などを交えながら、卓球を通じた地域活性の可能性を全4回にわたって探っていきます。
第3回では、「まちづくりを行ううえで卓球は役立つのか」というテーマでお話しさせていただきます。
>>シニア世代からの卓球入門 第1回:卓球のおもしろさと連載のねらい
なぜ卓球でまちづくりか
集団競技ではない点から、初対面の人どうしでも知り合いやすい卓球。他にも、様々な面からまちづくりへの活かしやすさがあります。
以下を参考に、ぜひ「まちづくりに卓球は役立つ」ということを広めていただければと思います。
まちづくりにおける卓球の長所

まずは、まちづくりにおける卓球の長所を紹介します。
取りかかりやすさ
卓球は、天候に左右されず、スペースをあまり取らず、用具費用を抑えられ、ケガの危険が少なく、年齢幅が広く(長くでき、高齢になってからもできる)、世界中に普及しているため、まちづくりへの活用がしやすいと言えます。
障害・言語を問わず
用具・方法の工夫により、障害・疾患があってもできる運動です。
意思疎通が困難な聴覚障害者と視覚障害者どうしでもできます。
集団が苦手な人にもできる方法があります。
言語が異なる者どうしでも打ち解けやすいという面もあります。
多様に活用できる用具
また、卓球の用具は多様に活用できることでも知られています。
災害時も卓球用具は活躍
セパレートタイプの台は、診察・相談・着替えコーナーのパーテーションになります。
防球フェンスには寝袋になるタイプのものもあります。
そのため、「災害時のためにも卓球用具を取り入れよう」という首長や議員もいます。
作品展やコンサート
セパレートタイプの台は、展示の際に活用でき、声楽家コンサートでは反響板にもなります。
そのような多機能さを示せば、卓球台を導入してくれる施設も出てきます。
将来に役立つ卓球
さらに、卓球は将来に役立つ側面もあります。
進学や就職・転職
学生にとっても社会人にとっても卓球は「人脈を作りやすい」ということがあります。
また、福祉・医療・教育に進学・就職・転職したい人は、卓球経験を活かした実践の可能性があります。
福祉・人権教育
卓球を通じてボランティアをすると、福祉・人権の学びになります。
コミュニケーション技術や福祉制度など、ご家族の介護の際にも役立つかもしれません。
健康づくり
人とのつながりは健康づくりには重要です。
さらに、卓球は「視覚・聴覚・触覚刺激」や、「高速の思考と反復運動」ほかにより、脳血流は1.5倍になり、気分・感情の改善効果もあります。
脳の活性化により認知症の予防や、健康寿命を伸ばすことにもつながります。
筆者プロフィール:長渕晃二(ながぶちこうじ)

NPO法人日本卓球療法協会理事長。NPO法人日本ピンポンパーキンソン理事。明治学院大学大学院修了(社会福祉学修士)。短大・専門学校での教員・卓球顧問や福祉施設での卓球経験あり。現在有料老人ホーム、デイサービス、介護予防サロン、メンタルクリニックで卓球療法を行う。著書は『コミュニティワーカー実践物語』(筒井書房)、『卓球療法士テキスト』『卓球療法入門』(サイドウェイズ)ほか。
Follow @ssn_supersports



