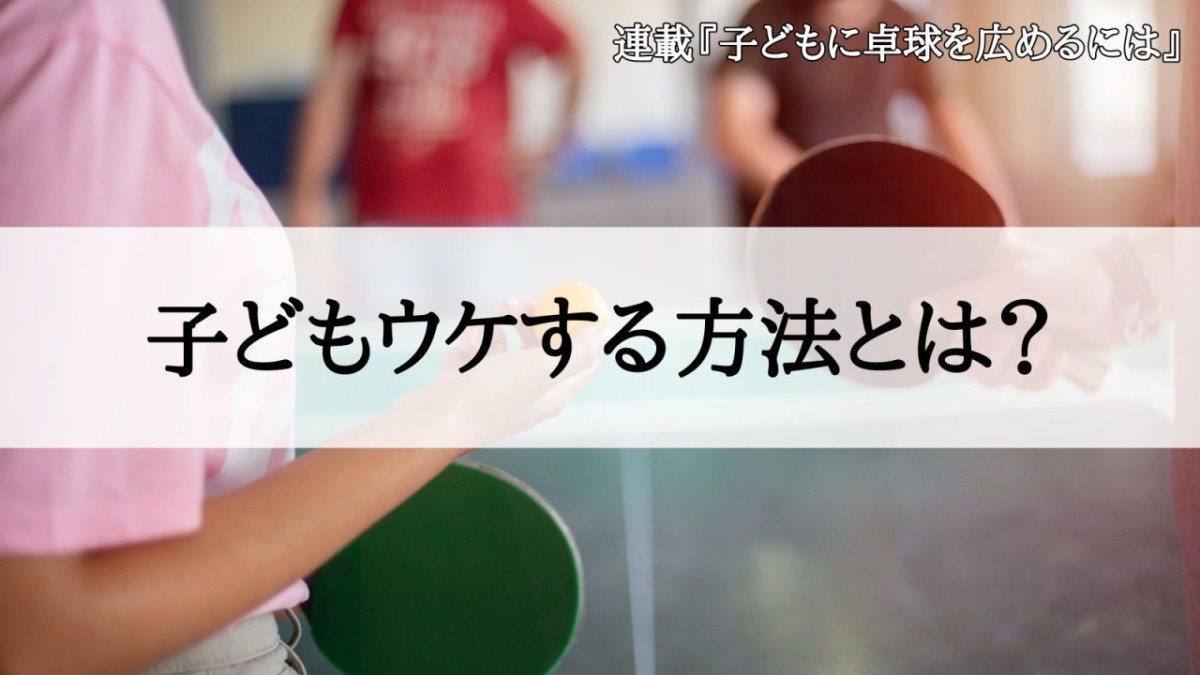
はじめまして。
NPO法人日本卓球療法協会理事長の長渕晃二と申します。
私は長年、介護・福祉やまちづくりに携わってきましたが、そのいずれにも卓球が活きることはたくさんありました。
そこで本連載「子どもに卓球を広めるには」では、わたしのこれまでの経験などを交えながら、どうすれば子どもに卓球を広められるのかを全4回にわたって探っていきます。
第4回では、「子どもウケする方法」というテーマでお話しさせていただきます。
>>シニア世代からの卓球入門 第1回:卓球のおもしろさと連載のねらい
子どもウケする方法

下記の10の方法のように、子どもが楽しめる方法はいろいろ工夫できます。
対象・会場・用具に応じて、いずれか1つに絞るか、あるいは複数のブースを設けてやってみましょう。
的あて

卓球マシンか、球出しによる球を、的めがけて打ちます。的は空き缶ほかいろいろ工夫してみましょう。
点数や景品でも良いでしょう。
障害がある子によっては、サウンドボールを転がして、どの点数の的にストップできたかという「的いれ」のほうが適切な場合があります。
球いれ
籠を2つ用意し、白球組とオレンジ球組に分かれ、球をラケットで当てて籠に入れます。
2組に分けず、1人ずつチャレンジするのも良いでしょう。
卓球バレー
台の周りに、複数名に分かれて座り、ネットを上に上げて球がくぐるようにし、ネット下を転がし、打ちあいます。
イベントの人数やブースの回り方により、臨機応変な方法で行いましょう。
人数が多い場合は、球を2つや3つにすると、カオスな卓球バレーになります。
ハンドベルを両手に持って打ちあう卓球バレーにすると、丸いので打ちにくいのがおもしろく、音がにぎやかになります。
卓球ホッケー
卓球バレーと似ていますが、双方の台の中央にゴールポストがあって点数を競います。
4つのコーナーに箱を置いて行う施設もあります。
野球盤
野球が好きな子がいる場合は、台上に塁やアウトやヒット・ホームランなどのコーナーを作り、後攻が先攻に対し、サウンドボールを転がし、先攻が打つという野球盤のようなゲームをすることがあります。
数人で回る卓球

3人で台の周りを時計回りに回って打つラリーを見せ、4~5人くらいでやってみていただきます。
おもしろラケット
ミニラケットや特殊なラケットや竹ラケット(TAKETTO)、あるいはまな板や図鑑をフライパンを両手で両側を持ち打つなど、いろいろなラケットで打ってみます。
いろんな球で
エレファントボールやスポンジボールなどで打ちあってみます。
記憶力ゲーム
まずはペンやスプーンや消しゴムなど、何種類かの物を見せ、フタをします。
続いてラケット上に球を置き、落とさないよう台の周りを1周します(落としてもそこから再開)。
戻ったらフタの下に何があったかを思い出して当てます(いくつ正解かを競う)。
ラリー回数チャレンジ
初心者にはバックショートのラリーだと「目と球とラケットが近い」ので当てやすく、続きやすいのですが、背の低い子だと顔の前にラケットになってしまうので、その子に応じてやり方を考えておきましょう。
うまい子の場合、ジャンケンしながらラリーや、両手にラケットを持ち交互に打つなど、難易度を上げてみるのも良いでしょう。
筆者プロフィール:長渕晃二(ながぶちこうじ)

NPO法人日本卓球療法協会理事長。NPO法人日本ピンポンパーキンソン理事。明治学院大学大学院修了(社会福祉学修士)。短大・専門学校での教員・卓球顧問や福祉施設での卓球経験あり。現在有料老人ホーム、デイサービス、介護予防サロン、メンタルクリニックで卓球療法を行う。著書は『コミュニティワーカー実践物語』(筒井書房)、『卓球療法士テキスト』『卓球療法入門』(サイドウェイズ)ほか。
Follow @ssn_supersports



