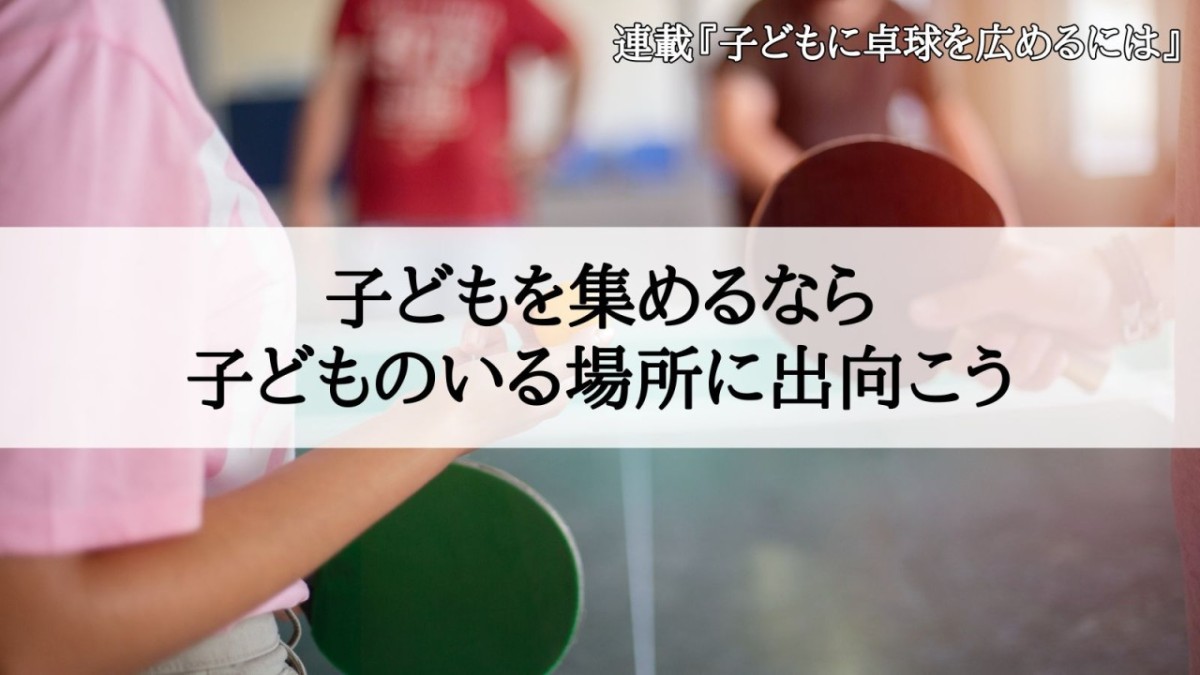
はじめまして。
NPO法人日本卓球療法協会理事長の長渕晃二と申します。
私は長年、介護・福祉やまちづくりに携わってきましたが、そのいずれにも卓球が活きることはたくさんありました。
そこで本連載「子どもに卓球を広めるには」では、わたしのこれまでの経験などを交えながら、どうすれば子どもに卓球を広められるのかを全4回にわたって探っていきます。
第2回では、「子どもを集めるなら子どものいる場所に出向く必要がある」というテーマでお話しさせていただきます。
>>シニア世代からの卓球入門 第1回:卓球のおもしろさと連載のねらい
子どもを集めるよりも子どものいる場所に出向く
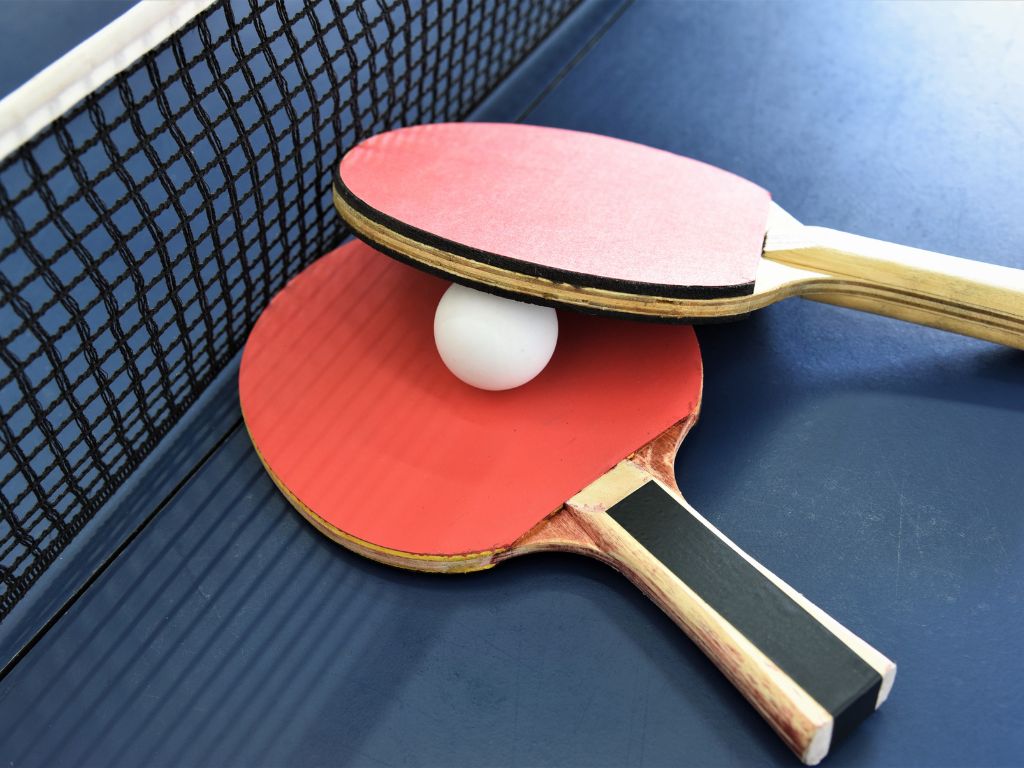
まずは、子どものいる場所に出向くことの長所と短所を紹介します。
出向くことの長所・短所
啓発活動の常套手段の一つに、集客するより出張するという地道な方法があり、利点としては以下があります。
- 全く関心のない人にも参加いただける。
- 広報や会場手配の手間がいらず、あまり予算もかからない。
- 参加者はお互いにある程度は顔見知りなので気安さがある。
- やりようによっては継続的な活動に発展する可能性がある。
- 相手側の事業や教育内容の充実に協力できる。
- 集合調査により感想を集約しやすい。
欠点としては以下があります。
- 会場や用具が適切でない場合がある。
- 相手側の時間の制約がある。
- 大規模なイベントができない。
集めるイベントは、卓球場や卓球団体によるものが以前から行われていますが、今後は出向くイベントももっとあると良いと感じています。
どこへ出向くか
人数、時期、時間帯、時間は、それぞれ異なりますが、まずは以下が思い浮かびます。
保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校、PTA行事、子供会、児童館、学童保育(放課後児童クラブ)、放課後等デイサービス、児童養護施設、子ども食堂、塾、フリースクール。
地域によっては、他にも子どもが来る場はいろいろあると思います。
まずは人脈づくり
上記の各所でのイベントを企画するには、そこに関わる人と知り合っておくとスムーズに企画できます。
首長、教育委員会、教員、福祉職、子ども関係団体役員、民生委員児童委員、その他、地域にはさまざまなキーパーソンがいるので、あらかじめ相談しておくと良いでしょう。
これらの人と知り合うのは、普段の卓球を通じてや、知人の紹介など、身近なところからやっていくのがおすすめです。
筆者プロフィール:長渕晃二(ながぶちこうじ)

NPO法人日本卓球療法協会理事長。NPO法人日本ピンポンパーキンソン理事。明治学院大学大学院修了(社会福祉学修士)。短大・専門学校での教員・卓球顧問や福祉施設での卓球経験あり。現在有料老人ホーム、デイサービス、介護予防サロン、メンタルクリニックで卓球療法を行う。著書は『コミュニティワーカー実践物語』(筒井書房)、『卓球療法士テキスト』『卓球療法入門』(サイドウェイズ)ほか。
Follow @ssn_supersports



