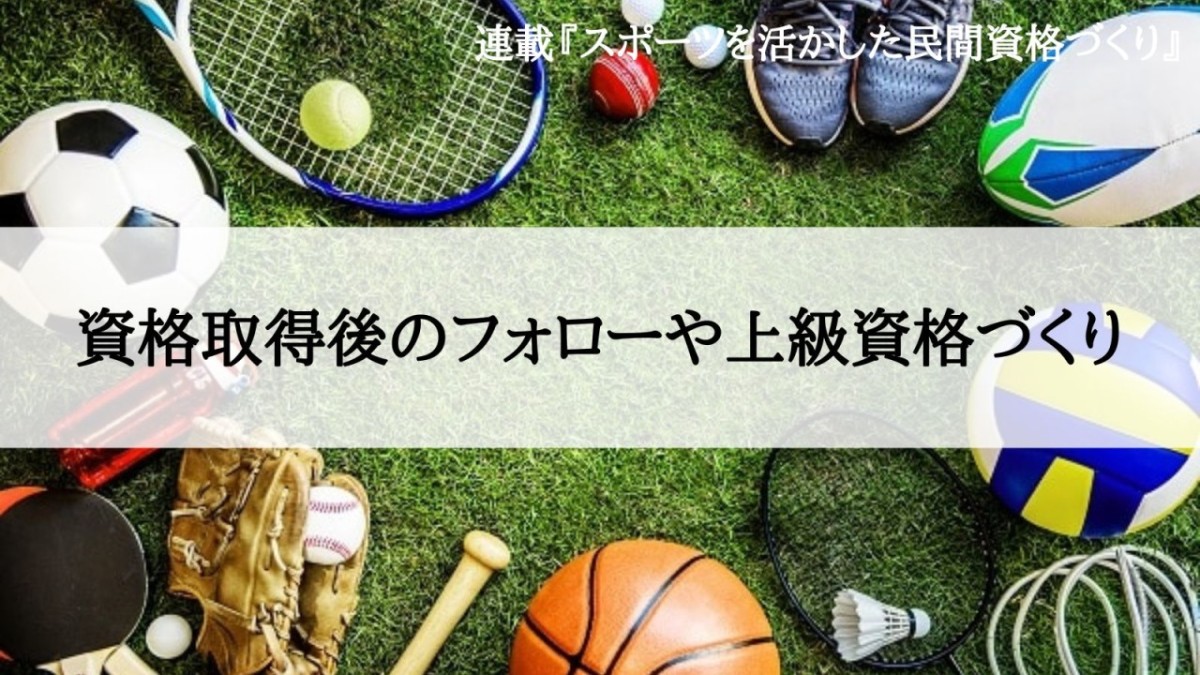
はじめまして。
NPO法人日本卓球療法協会理事長の長渕晃二と申します。
私は長年、介護・福祉やまちづくりに携わってきましたが、そのいずれにも卓球が活きることはたくさんありました。
そこで本連載「スポーツを活かした民間資格づくり」では、わたしのこれまでの経験などを交えながら、スポーツを活かして民間資格をつくることについて全5回にわたって探っていきます。
第4回では、「資格取得後のフォローや上級資格づくり」というテーマでお話しさせていただきます。
>>シニア世代からの卓球入門 第1回:卓球のおもしろさと連載のねらい
資格取得後のフォローや上級資格づくり

情報提供や再受講
ご年配の方だと「郵便やFAXが良い」、若い人だと「SNSが良い」など、伝達方法の多様化により、情報提供は行き届かないことがあります。
メールアドレスや携帯など連絡先の変更、メールをあまり開いていない人、特定のSNSしかしていない人など、なかなか難しいと感じています。
再受講や会員交流、学会参加など、積極的に参加される人には、よく情報が届き、会員相互の交流もでき、ご意見も入るので、フォローしやすくなっています。
情報格差は課題の一つです。
上級資格や講師養成
入門・基礎の資格講習は比較的受講しやすいものにし、徐々に広がってきたら、会員のニーズに合わせてより専門的な講習を検討し、順次開講していきます。
卓球療法士ではインストラクター資格として、①身体疾患・認知症、②精神疾患、③パーキンソン、④児童の講習を設けています。
会員から「福祉についてもっと深く学びたい」という要望があり、①福祉専門課程を設け、続いて②医療専門課程も開講し、現在は③卓球専門課程を検討中です。
講師養成については、インストラクター資格の修了後、理事長が監督のもと卓球療法士講習の講師をやっていただきます。
そこで特に問題なければその後は単独でやっていただき、テキスト改訂後には再受講していただくという方式にしています。
多様な相談
福祉施設・機関や医療機関からの相談は、①入所・通所者の活動への導入、②地域住民の介護予防、③講習の開講希望など。
教育関係からは、①特別支援学校での活動、②部活動での発達障害児の対応、③大学等の授業や課外講座など。
卓球指導者からは、パーキンソン病や障害児の方への指導法。
自治会・管理組合からは、住民の交流や介護予防での卓球療法の取り入れ。
当事者からは、疾患・障害に応じた参加の方法、用具など。
企業からは卓球療法に関わる製品の営業方法の相談、卓球指導者からは福祉施設への卓球療法導入の営業方法の相談。
個人からは、普段の実践の相談や、卓球療法士講習講師になる方法についての相談。
以上のように、実に多様な相談が入ってきており、これらに応じることで、活動が活発になっていきます。
つながりづくり
前述した再受講や上級資格における会員交流のほか、交流が主目的の機会を作っていけると良いでしょう。
組織づくりにもつながる会員交流は、地域別交流会や職種別交流会で、さらに必要があれば年代別交流も考えられます。
内容は卓球交流、懇親会、研究会、イベントなどで、このうち懇親会・研究会はオンライン開催も可能です。
卓球療法協会では卓球療法学会も開催しており、たいへん貴重な交流機会となっています。
筆者プロフィール:長渕晃二(ながぶちこうじ)

NPO法人日本卓球療法協会理事長。NPO法人日本ピンポンパーキンソン理事。明治学院大学大学院修了(社会福祉学修士)。短大・専門学校での教員・卓球顧問や福祉施設での卓球経験あり。現在有料老人ホーム、デイサービス、介護予防サロン、メンタルクリニックで卓球療法を行う。著書は『コミュニティワーカー実践物語』(筒井書房)、『卓球療法士テキスト』『卓球療法入門』(サイドウェイズ)ほか。
Follow @ssn_supersports


