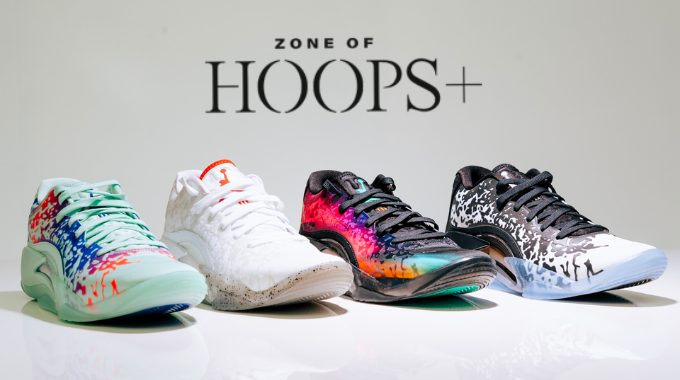移籍した選手が、移籍直後に輝く――。
どのプロスポーツでもよくある話だ。これまでのチームに与えられた役割ではなく、新たな役割がフィットしてその選手本来が持つ良い味を出すことができるようになる。逆も然りで、新しいチームで与えられた役割が上手くハマらず、なかなか移籍後に輝くことができない。地元チームのファンにとって、選手の移籍は寂しいものがあるものの、次の場所で輝いてくれることで嬉しい気持ちになったり、また移籍先のチームを応援するキッカケにもなったりするだろう。
いずれにしても「人の移動」によって、このようなことが起こっている。実は「移籍」は、選手にとっては良い成長のチャンスであり、さらに言えばリーグが成長するチャンスでもある。そして、実は選手の出入りが多いリーグほど、リーグは成熟しているとも言われているのだが、あなたはその事実をご存じだろうか。
今回はその理由を、NBA(アメリカ)、Bリーグ(日本)、NBL(オーストラリア)、ユーロリーグ(欧州)のそれぞれの特徴を紹介しながら裏付けを記載していければと思う。
前回記事:
「もしかして好きかも…?」きっとあなたも好きになる、タイプ別オススメのバスケリーグ - 世界プロバスケリーグ比較 vol.5.5 -
リーグの成長は“出入りの多さ”で決まる理由
国際バスケットボール連盟の「FIBA」の「International Basketball Migration Report(※1)」によると、2023-24シーズンでは13,149件の国際移籍(プロ/アマ問わず18歳以上)を記録した。その前の2022-23シーズンでは、11,787件という数字も出されている。
この数字を見るとわかる通り、「選手が国境を越えて移籍している」ことを証明しているわけだが、国境を越えて移籍すると一気にその国での知名度は上がる。
バスケットボールの世界で言うと、たとえばNBA Gリーグのインディアナ・マッドアンツに所属していた富永啓生が今年日本のレバンガ北海道に移籍したわけである。富永を一目見たい新規ファンが増えたのはもちろん、そもそもGリーグのマッドアンツでチームメイトだったジャリル・オカフォーも一緒にレバンガ北海道に入った。オカフォーはそもそもドラフトの1巡目3位でNBA入りしたスーパースターであり、コアなファンも非常に多かった。日本のNBAファンの中でも「Bリーグは見たことないけど、オカフォーを見てみたい」という「NBAだけ見ていたファン」がBリーグに興味を持つキッカケになったことは間違いない。
このように、国を超えて移籍することで、リーグ自体の「価値」が上がること、また上記の例でいえば「オカフォーを一目見たい」というレバンガ北海道のファンもしくは純粋なオカフォーファンが、Bリーグのチケットを買って観戦に行ったことだろう。そしてそれは今も起きていることであろう。
※手に持っているのはバスケットボールです🏀
北海道#22 オカフォーの個人技が光る!@JahlilOkafor @levangakousiki📡バスケットLIVEで生配信中https://t.co/8ePzVoSN4I#Bリーグ #りそなグループ pic.twitter.com/lw0MbBTv5M
— B.LEAGUE(Bリーグ) (@B_LEAGUE) October 18, 2025
このように、今まで見ることができなかった選手を見ることができる。日本を軸にすれば海外で活躍した素晴らしい選手が来日することで、リーグが成長すると考えられているが、簡単にまとめると以下の通りである。事項からは、各リーグの特徴とともに紹介していく。
| 経済的理由:ストーリーが「商品」になる | 選手が移籍・昇格するたびに「新天地での挑戦」「恩師との再会」「ライバルとの再戦」といった物語が生まれる。これがニュースやSNS投稿、ドキュメンタリー、広告キャンペーンなどのコンテンツ素材になり、そのまま広告露出の燃料になる。 → 例)八村塁がワシントン・ウィザーズからロサンゼルス・レイカーズに移籍した際、NIKEやNBA Japanの投稿エンゲージメントが通常の5〜10倍増になった |
| 心理的理由:人が動くと「応援したい動機」が生まれる | ファンは選手単体を追いかける傾向が強い。移籍・昇格・海外挑戦があると、選手単位で新しいファンの導線が生まれる。
例)- ラメロ・ボールがNBL経由でNBA入りしたとき、オーストラリア国内のNBA視聴率が跳ね上がった(※2) |
| メディア構造的理由:ニュースバリューが高い | 「移籍・昇格・留学」は一番報道しやすいスポーツニュース。成績や試合結果よりも短く、感情を動かしやすい。また、メディアは“変化”を好むため、選手の出入りが多いリーグは露出機会が増える。
結果)スポンサーも「露出が読めるリーグ」に広告投下しやすくなる |
▼サラリーキャップ比較
| NBA(アメリカ) | 上限は約230億円 |
| Bリーグ(日本) | 上限8億円(2026-27シーズンから制度誕生) |
| NBL(オーストラリア) | 上限約2億円(※4) |
| ユーロリーグ(欧州) | 制度なし (2025-26シーズン以降導入検討中/上限約18.5億円を想定)(※5) |
NBA――人材循環の頂点に立つ、完結型エコシステム
NBAは世界中のプロリーグの最終到達点であり、最も整備された人材循環システムを持っている。リーグ全体のサラリーキャップ(2025-26シーズン:約230億円)は、チーム間の格差を防ぎながらも、トレード市場の活性化を促しているとも言えるだろう。これによりスター選手の移籍やロールプレイヤーの入れ替わりが頻発し、リーグ全体に「動き」が生まれるのだ。昨年ルカ・ドンチッチが、ダラス・マーベリックスからロサンゼルス・レイカーズに移籍したように、スターが移籍すればリーグの構造もチームの収入も大きく変わっていくものだ。
さらに、NBAはドラフト制度+Gリーグ連動が、育成から昇格へのルートを明確にしている。Gリーグは単なる下部組織ではなく、NBAと一体化した育成インフラとして機能しているため、近年はGリーグ上がりのNBA選手が活躍しているが、この辺りの仕組み化が非常に優秀でもある。具体的にアレックス・カルーソ(オクラホマシティ・サンダー)やオースティン・リーヴス(ロサンゼルス・レイカーズ)など、Gリーグ経由で成功をつかんだ選手が年々増加している。
世界中を巻き込む“人材輸出産業”
近年のNBAは特に、世界から才能を吸収する一方で、世界へ人材を発信するプラットフォームでもある。セルビア出身の二コラ・ヨキッチ(デンバー・ナゲッツ)、スロベニア出身のルカ・ドンチッチ(ロサンゼルス・レイカーズ)など、ユーロリーグをはじめ各地でスーパースターとして活躍した選手がNBAでも活躍している結果、国際的スターが次々に誕生。選手のルーツが多様であるほど、ファンの裾野も国際的に広がっていることがわかる。
リーグ単体で人材循環が完結し、経済・メディア・文化を巻き込んでいく――
NBAはまさに「完結型エコシステム」として、世界のモデルとなっているのだ。
Undrafted out of Texas A&M in 2016 and now 2x NBA CHAMPION in Year 8... Alex Caruso! pic.twitter.com/dm3YBnrRtt
— NBA (@NBA) June 23, 2025
Bリーグ――アジアからの流入拠点、次なる“輸出国”を目指して
Bリーグの成長に拍車をかけているのは、「アジア特別枠」という独自制度にある。現在Bリーグの選手登録は、外国籍3名+アジア特別枠1名(もしくは帰化選手)を組み合わせることができるため、アジア全域からの人材流入が一気に進んだ。レバンガ北海道のドワイト・ラモス(フィリピン)や茨城ロボッツのヤン・ジェミン(韓国)など、各国のスターがこぞって参加してきている。
このように、韓国、台湾、フィリピンなど各国のスターが続々とBリーグに参戦していることで、SNSや配信を通じて国境を超えたファンの往来が起きている。そもそもBリーグは昨今の成長によってNBAやNBL、ユーロリーグへのステップアップにつながる可能性が高いと考えられているだけではなく、母国よりも年俸が高いケース、また生活や環境面も整備されていることで、アジアの選手が挑戦したいと思うのは当然のことともいえる。よって現在「アジアの交差点」として機能しはじめており、今後参加する選手は年々増えていくことであろう。
育成の次は“輸出”のフェーズへ
日本国内ではユース・大学・プロのラインが整備されつつあるが、海外挑戦の仕組みはまだ途上段階。2024年1月に、両リーグの繋がりを深めることを目的としたパートナーシップを提携し、今年「Bリーグ選抜vsNBL選抜」の試合が行われたりもしたが、まだまだ交流段階で「輸出」までは届いていない。
ただし今後、BリーグからNBLやユーロリーグへ人材が“輸出”されるようになれば、リーグの評価は劇的に変わる。「アジア発→世界行き」ルートのハブとしての立ち位置を築けるかが、次の成長曲線の鍵になる。八村塁や河村勇輝など、「日本→NBA」のルートも見え続けていることから、ここはBリーグが掲げる「世界で2番目のリーグになる」という目標に向けて、よりアクセルを踏んでいきたいところだ。
本日のMVP!
フィリピンの至宝!レバンガの宝!#ドワイト・ラモス 選手のヒーローインタビューを丸っとお届けします!!💎🎥「点数が離れた展開から追いつく試合が続いていますが、このようなタフな試合を勝ち切ることができてうれしいです。… pic.twitter.com/p16ZrML7sZ
— レバンガ北海道 (@levangakousiki) October 26, 2025
NBL――NBAへの“踏み台リーグ”として確立されたブランド
オーストラリアのNBLは、近年「世界で最も戦略的な2番手リーグ」と呼ばれている。ちなみに、彼らはその位置を狙って確立しているため、自ら「1番」になることを良い意味で目指していない。この「2番手リーグ」として呼ばれる理由が、2018年にスタートした「Next Stars」制度だ。
「Next Stars」制度が変えた人材循環の概念
この制度は、NBAドラフト候補クラスの若手を、NBLが1シーズン限定で受け入れる仕組みである。大学進学ルートでは得られないプロ経験とNBAスカウトへの露出を保証することに加え、年俸10万ドル(約1,000万円)+住居や食事など生活サポートが用意され、選手はリスクなくプロの舞台を経験できる。
実際にラメロ・ボール(シャーロット・ホーネッツ)やジョシュ・ギディー(シカゴ・ブルズ)がこの制度を経てNBA入りを果たしている。
最後に、NBLは優秀な選手が流出することを「損失」ではなく「成果」と定義していることもユニークである。理由は明確で、NBAドラフトでNBLチーム名が紹介されることは、何よりの広告になると考えているから。ラメロ・ボールがNBAドラフトで紹介されたときは「イラワラ・ホークス」の名前やロゴが大型ビジョンに表示された。
これを彼らは旨みと感じているため、リーグ全体が“NBAへの踏み台”としてのブランドを確立した。観客・スポンサー双方にとって、「次のスターが見られる場所」という期待感を醸成していることが、彼らの最大の狙いでありNBLの魅力と捉えプロモーションを行っている。
🚨 NO. 3 OVERALL PICK 🚨
LaMelo Ball is drafted by the Hornets #NBADraft
Lonzo and LaMelo Ball are the first pair of brothers ever to each be drafted in the Top-5 of the NBA Draft. pic.twitter.com/njU9RyWylL
— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) November 19, 2020
ユーロリーグ――育成と囲い込みを両立する熟成モデル
ユーロリーグはNBAとは異なり、クラブ中心の経済モデルで成立している。これは大陸横断リーグという、他の「自国で運営するリーグ」とは異なるモデルだからこその形。ユーロリーグでは、育成・移籍・収益が密接に結びついているのも特徴だ。
また、ユーロリーグは育成が強い。レアル・マドリードやバルセロナ(スペイン)、フェネルバフチェ(トルコ)などの名門クラブは、自前のアカデミーで若手を育成し、移籍金で収益化する仕組みを確立している。
リーグ内完結型の“高密度循環”
現時点ではサラリーキャップが設けられていないが、移籍金とレンタル制度により、リーグ内外での流動性が保たれている。選手がステップアップ移籍を繰り返しながらも、欧州内でキャリアを完結できる点が特徴だ。
具体的には、スペイン→トルコ→イタリアなどの移籍が頻発し、リーグ間での人材循環も非常に活発。所属するリーグは変わらないものの、住む国が変わることで、国をまたいだブランディングにつながっていることも、ユーロリーグのユニークなところだろう。このように、ヨーロッパ内での「囲い込み型の循環」を成熟させたモデルがユーロリーグであり、あえて世界市場に飛び込んでいないことも特徴。NBAほどのグローバル拡張はないが、ヨーロッパという経済圏内で持続可能なエコシステムを築いているのだ。
Luka Dončić is the first Laker EVER to start a season with two consecutive 40 point games ⭐️
(h/t @mcten) pic.twitter.com/ooWycPbZzh
— Bleacher Report (@BleacherReport) October 25, 2025
総括
リーグの成長を測る指標は、単なる収益や観客動員ではない。
具体的な数字には見えにくいが、どれだけ「人が動き、育ち、次の場所へ行ける仕組み」を持っているかが非常に大きいのだ。
NBAが世界を吸収し、NBLがNBAへ送り出し、Bリーグがアジアを繋ぎ、ユーロリーグが欧州内を循環させる……。その構造の違いこそ、各リーグが描く成長曲線の“個性”だろう。最後に、各リーグの特徴をまとめて、この記事を締めくくればと思う。
| リーグ | 循環タイプ | 主な仕組み | 主な出口 | 特徴 |
| NBA(アメリカ) | 完結型 | サラリーキャップ/ドラフト/Gリーグ | 世界全体 | 世界の人材を吸収・輸出する頂点 |
| Bリーグ(日本) | 流入型 | アジア特別枠制度 | アジア・欧州 | アジアのハブとして成長期 |
| NBL(オーストラリア) | 踏み台型 | Next Stars | NBA | 流出をブランド化した成功例 |
| ユーロリーグ(欧州) | 内循環型 | アカデミー/移籍金 | 欧州内・NBA | 育成と囲い込みのハイブリッド |
【参考文献】
(※1)https://about.fiba.basketball/en/regions/americas/news/2024-migration-report-highlights-ongoing-surge-in-international-transfers
(※2)https://www.foxsports.com.au/basketball/nbl/one-million-people-in-the-united-states-watched-lamelo-balls-nbl-debut/news-story/a14a5e7d93f14324eae5f94c24cb4d4f
(※3)https://www.sportsbusinessjournal.com/Daily/Issues/2023/01/17/Leagues-and-Governing-Bodies/nba-japan-yuta-watanabe/
(※4)https://www.espn.com/nbl/story/_/id/44522652/nbl-salary-cap-moves-north-2-million-2025-26-season-sources
(※5)https://basketnews.com/news-208153-euroleague-reportedly-eyes-an-expansion-salary-cap-from-2025-26-season.html
Follow @ssn_supersports