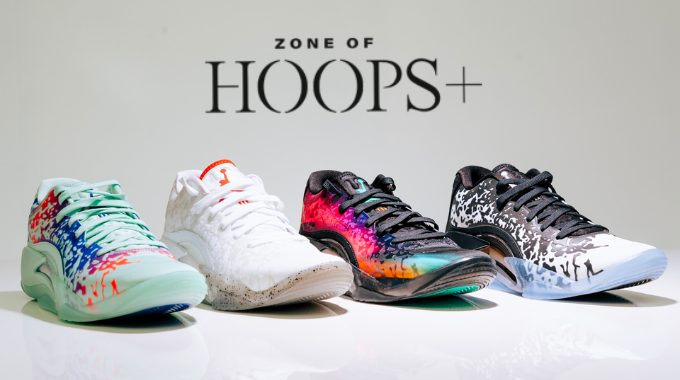バスケットボールという競技における、世界各国のリーグの現在地を比較していくシリーズ「世界プロバスケリーグ比較」。前回の記事では、「NBA(アメリカ)」「NBL(オーストラリア)」「ユーロリーグ(ヨーロッパ)」「Bリーグ(日本)」のそれぞれでどのくらいの入場者数があるのか。また、どのような戦略を持ってチケットを販売しているのかなどを比較して紹介していった。どこのリーグも「無料招待」を実施し、はじめて来場される人に対してもハードルを低く見せるための工夫も非常にユニークであった。
チケットや来場客数について触れたところで、今回はこのシリーズで出している4大リーグ「NBA(アメリカ)」「NBL(オーストラリア)」「ユーロリーグ(ヨーロッパ)」「Bリーグ(日本)」のそれぞれのアリーナについて紹介していこう。
アリーナのキャパシティ
まず前回の平均入場者数について、改めて紹介したい。
| リーグ | 平均入場者数 | 補足 |
| NBA(アメリカ) | 約17,000人前後 | 各チームホームアリーナ収容率約90%前後 |
| Bリーグ(日本) | 約5,000人前後 | B1クラブ中心。アリーナ規模によって変動 |
| NBL(オーストラリア) | 約4,000人前後 | 2チーム体制で小規模アリーナ中心 |
| ユーロリーグ(欧州) | 約9,000人前後 | Aライセンスクラブ中心。バルセロナ、マドリード、イスタンブールなど大都市クラブは1万前後 |
それぞれのリーグの平均値は上記の表の通りであるが、この数字はこれだけの人を収容できるアリーナがあることと同義である。視点を変えれば、アリーナのスケールはリーグの成熟度を映し出す鏡のような存在とも言える。大人気コンテンツなのに少ない収容人数の箱であれば、ビジネスチャンスを逃していると言っても過言ではない。もちろん、だからと言って大きな箱を作ることも非常に難しいのも事実。アリーナを作ってから試合がない日にどうやって箱を運用していくかが非常に難しく”持て余す”こともできるだけ避けたいところである。
一方で、そうならないようにNBAやNBLでは都市再開発プロジェクトと連携する事例も増えており、アリーナは単なる競技場ではなく、「地域の経済ハブ」として再定義されつつあるのが昨今の流れでもある。こうした流れは、特にコロナ禍以降のアフターコロナ時代から活発になってきている。やはり地域の人が集まって感動体験を生み出せる場所は重要であると、自治体をはじめとする関係各社が再認識しているのだ。だからこそ、現在日本でもBリーグが先頭に立ち、全国各地で新アリーナの建設が進んでいる。先日開業した「トヨタアリーナ東京(東京・青海)」や「IGアリーナ(愛知・名古屋)」などがその象徴とも言えるだろう。
NBLやユーロでも同様に「地域経済のハブ」としてアリーナは存在感を放っているが、現時点でそれぞれの最大規模のアリーナについて紹介したい。
| リーグ | アリーナ名 | 所在地 | 収容人数(約) | 主なホームチーム | 補足 |
| NBA (アメリカ) |
Crypto.com Arena(旧 Staples Center) | ロサンゼルス | 約19,000人 | L.A. Lakers / Clippers | 世界屈指の多目的アリーナ。NBA・NHL・音楽イベントを多数開催 |
| Bリーグ (日本) |
Lala Arena Tokyo Bay | 千葉県船橋市 | 約10,000人 | 千葉ジェッツ | 2024年竣工の最新アリーナ。日本の“NBA型”アリーナの先駆け |
| NBL (オーストラリア) |
John Cain Arena | メルボルン | 約10,500人 | Melbourne United | テニス全豪オープン会場としても有名。観客動員数はNBLで最大級 |
| ユーロリーグ(欧州) | Štark Arena | ベオグラード(セルビア) | 約19,000人 | KK Partizan / Crvena Zvezda(共用) | 欧州最大級。試合日は“狂気的”な雰囲気。満員時はNBA並みの熱気 |
NBAでも最大規模。ロサンゼルスにある「Crypto.com Arena(旧 Staples Center)」は、NBAのレイカーズ&クリッパーズだけではなく、NHLやWNBA、またアーティストのライブなどでも活用されている
New heights for the annual Open Air Game. 😍🎆
Illuminating the events capital with a dazzling display. pic.twitter.com/NtUxqSWufi
— John Cain Arena (@JohnCainArena) December 23, 2023
オーストラリアにある「John Cain Arena」。オーストラリア随一のハイブリッドアリーナとして、天候の良い日はオープンエア状態でバスケットの試合を実施することもある
セルビアにある「Štark Arena」。ホームチームのPartizan Belgradeはヨーロッパ随一の熱狂的ファン集団で、試合前から発煙筒・太鼓・チャント・スタンディングオベーションの嵐
NBAは完全に「エンタメ複合型施設」として振り切っている。収益面でもアリーナ内のVIPスイート、パートナーシップ、グッズ販売が極めて重要であり、訪れるファンにどれだけの体験を提供できるかを重視していると言っても過言でないほど。
オーストラリアはイベント兼用型で、スポーツ以外の収益構造(コンサート・展示会)が強い。屋根が開く仕組みも、バスケット以外にサッカーやテニスなどでも使えるようにしたことが理由であるが、結果的にそれぞれのスポーツでの常識を覆す良い取り組みになっている。
ユーロリーグは「都市単位の文化イベント」として位置づけられ、アリーナが“街の象徴”となっている点が特徴。動画をご覧いただければわかる通り、応援の熱気も半端ではない。歌うのもサッカーのような雰囲気を感じさせる。
日本ではLala Arenaが本格的な“チーム所有型”アリーナとして注目を集めている。演出・照明・音響・座席構造もNBA水準を意識されているが、IGアリーナやトヨタアリーナ東京も同様に、今後日本ではNBA水準のアリーナが次々に建設されていく。
アリーナにおける最先端事例
大きな規模のアリーナに限った話ではないが、全てのリーグ・全てのアリーナで「観客の没入体験+ストレス削減+収益最大化」が最大のテーマである。これを実現していくために、小さい工夫をすることからお金をかけて最先端のテクノロジーを導入することまで、さまざまな企画を実施しトライ&エラーを繰り返している。
アリーナ来場客が感じやすいストレスとして、顧客体験の向上に向けたソリューションを提供している「Wavetec」によると、ストレス要因と想定できるのは以下の3つと考えられている。記事には、これらの戦略を組み合わせることでファンの満足度を高め、アリーナへの再来場を促すことができると記載されている。
▼アリーナで来場客が感じやすいストレス要因(※1)
| インフラと施設 | 快適な座席(クッション、座席の広さなども含む)や清潔なトイレなど、施設内の設備が使いやすく綺麗であることが最低条件。必須ではないがフードのバリエーションは豊富であると尚良い |
| 入退場時の混雑と待機時間 | セキュリティチェックやチケット確認の際、長時間の待機や混雑が発生すると、来場客のストレスが増加する。モバイルオーダーや混雑状況の表示など待機時間を短縮する仕組みは必須 |
| 通信環境の不安定さ | Wi-Fiやモバイル通信が不安定な場合、SNSの利用や試合情報の取得に支障をきたし、フラストレーションが溜まりやすい。行き帰りの道中でも通信環境が悪くなるとリピート率が下がりやすい |
上記がストレス要因として挙げられているが、1万人規模のアリーナで全員のストレスを無くすことはそう簡単なことではない。ただ、逆に言えばストレス要因は「施設利用の不便さ」「待機時間が長い」「通信が不安定」が大部分を占めていることから、これらを解決することで、リピート率が高まると言っても過言ではない。
そこで、今回は世界が先駆けて行っているユニークな事例をいくつか紹介したいと思う。
顔認証システム(※2)
ロサンゼルス・クリッパーズの新アリーナ「Intuit Dome」では、顔認証を活用した「GameFace ID」システムが導入されている。ファンは専用アプリで顔写真を登録することで、チケットの提示や入場時のQRコード表示が不要。専用タブレットに顔を表示させることでスムーズな入退場が可能。顔認証システムはアメリカではNBAだけではなく、NFLやMLBでも導入されており、昨今の当たり前にもなってきている。なお、2025年現在ではアメリカの企業でもオフィスの「入館証」として顔認証システムを導入している企業も年々増えてきている。
ゴミ捨て効率化システム(※3)
MLB:ニューヨーク・メッツの本拠地「シティ・フィールド」に導入されたAI駆動型スマート廃棄物管理プラットフォーム「Pello」は、Recycle Track Systems(RTS)社が開発した、AIとセンサー技術を活用した廃棄物管理プラットフォーム。
2025年にこのシステムを導入し、スタジアム内のゴミ箱に設置されたセンサーがリアルタイムでゴミの量や分別状況を監視する。
AIは、ゴミ箱の満杯状態や不適切な分別を検出し、運営チームにアラートを送信。これにより、ゴミの収集タイミングを最適化し、無駄な収集を減らすとともに、リサイクルの精度向上を実現した。ちなみに「Pello」自体の設置は通常15分以内。アリーナ運営の効率化とコスト削減が期待されている、注目のサービスである。
デジタル体験向上の取り組み
NFL:ボルティモア・レイブンズのホームスタジアムである「M&Tバンク・スタジアム」では、来場者の視覚体験を向上させるために、LGと提携し、スタジアム内に12,000平方フィート以上のデジタルサイネージを導入している。これには、216フィートの大型ビデオディスプレイや、クラブエリア、コンコース、ホスピタリティエリアに設置された高解像度のディスプレイで、試合の映像や統計情報、スポンサーコンテンツなどをリアルタイムで表示している。スマホを見なくても、ある程度の周辺情報であればモニターでキャッチアップできる。
アリーナ全体の運営をAIが管理
ワシントンD.C.の「Capital One Arena」ではアメリカのテクノロジー企業である「Cisco」と提携し、ファン体験や会場運営、チームパフォーマンスを統合的に管理する「Cisco Command Center」を導入している。これは、wi-fiなどのネットワーク管理からチケットスキャン端末の安定化、データ分析による各種混雑状況(チケット待機列、トイレや売店など)の把握と共有、ライブ映像の配信管理、セキュリティ管理など、アリーナ運営の全てをデジタル化してリアルタイムで管理するシステムである。
日本ではある程度「人」で管理していることが、もうすでにアメリカではAIによって管理されている。
アリーナ体験向上企画から見る今後の展望
4大リーグいずれも、「ファン体験の没入度向上」と「ストレスフリー化」を両立させるテクノロジーの導入が、今後の発展のカギになっていくことは間違いない。ただ、現時点でも当然ながら差はある。
NBAは想像通り、アリーナテクノロジーの最先端をとにかく走っていて、VR・ロボット・ARなど総合的に導入している。公式のVR体験も非常に充実している。清掃ロボットをはじめそもそもアリーナの運営をAIが管理し初めているのもユニークだ。
ユーロリーグでは歓声と連動した光(LED)の演出が行われている。NBLはコンパクトな運営を行っているため、そこまで最新テクノロジーに手を出してはいない。
では、Bリーグはどうか。完全キャッシュレスに移行しているアリーナがほとんどであり、アプリと連動した簡易AR演出なども行われている。VRや自動化などはまだまだ浸透し切ってはいないものの、NBLやユーロに比べればテクノロジーを活用し発展しているとも言えるだろう。今後、日本は特にアリーナが全国的に建設されることから、どのようにテクノロジーと組み合わせて素晴らしいアリーナ体験を提供していくのか。今から非常に楽しみである。
NBAが提供するVR体験。自宅がアリーナになりつつある
リトアニアで行われた試合前のファンによるLEDライト演出
(※1)https://www.wavetec.com/blog/how-to-improve-fan-experience-at-sports-stadiums/
(※2)https://www.wicketsoft.com/
(※3)https://www.rts.com/pello-smart-waste-technology-launches-at-citi-field-to-advance-sustainability-and-fan-experience/
Follow @ssn_supersports