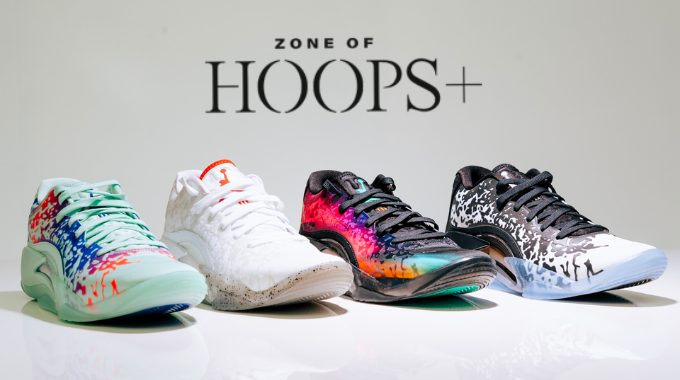バスケットボールという競技における、世界各国のリーグの現在地を比較していくシリーズ「世界プロバスケリーグ比較」。初回となったvol.1では、このシリーズでピックアップしていく4つのリーグ「NBA(アメリカ)」「NBL(オーストラリア)」「ユーロリーグ(ヨーロッパ)」「Bリーグ(日本)」について、それぞれの現在地とビジネスとしてのスケールを紹介した。
今回は、それぞれのリーグの立ち位置を改めて明確にした上で、目指している方向と、今後の発展に欠かせないアクションなどを考察していきたい。
それぞれの現在地
NBA、NBL、ユーロリーグ、Bリーグ。この4つが、それぞれの国でどのくらいの存在感を放っているのか、簡単に数字で比較していければと思う。
| 国 | バスケ | その国で一番人気のスポーツ |
| アメリカ | NBA(約2兆円規模) | NFL(アメフト/約3兆円規模) |
| オーストラリア | NBL(約60億円規模) | NRL(ラグビー/約750億円規模) |
| ヨーロッパ | ユーロリーグ(約700億円規模) | プレミアリーグ(サッカー/約1兆円規模) |
| 日本 | Bリーグ(約550億円規模) | NPB(野球/約2,000億円規模) |
やはりスポーツ大国でありスポーツ最先進国とも呼び声が高いアメリカは、スポーツリーグの規模が文字通り桁違いである。一番人気のNFL(アメフト)は、NBAと約1兆円もの差があるほど圧倒的人気を誇っている。とはいえ、バスケットボールは国民的スポーツとも言われており、アメリカ国内では大学バスケ(NCAA)も非常に人気である。
オーストラリアもスポーツ国家ではあるものの、ラグビーやクリケットが国民的スポーツであり、バスケは近年成長中のコンテンツである。これは地元選手であるジョシュ・ギディー(シカゴ・ブルズ)やベン・シモンズ(ロサンゼルス・クリッパーズ)、またNBLを通じてNBAに行ったラメロ・ボール(シャーロット・ホーネッツ)など、自分たちとの距離が近い選手たちがNBAで活躍していることもあり、特に若年層や都市部で人気が拡大しているとのこと。
ヨーロッパは言わずもがなサッカー一強。イングランド国内リーグである「プレミアリーグ(Premier League)」やスペインの「ラ・リーガ(La Liga)」、ドイツの「ブンデスリーガ(Bundesliga)」、イタリアの「セリエA(Serie A)」など、数千億円から約1兆円規模まで、圧倒的に人気を誇っている国民的スポーツであり、もはや”大陸的”スポーツと言っても過言ではないかもしれない。
その中で、スペインやリトアニア、ギリシャなどでバスケットボールの人気も増えてきている。例えばスロベニア代表でもあるルカ・ドンチッチの存在や、少し前でいえばスペイン代表のツインタワーであったガソル兄弟など、オーストラリア同様に自分たちとの距離が近いNBA選手が出るたびに、人気がコツコツ増えつつある。また、ユーロリーグとは別のFIBA主催の国際大会である「ユーロバスケット(欧州選手権)」はヨーロッパ各国でも人気が増えつつあり、また今年に関してはどの国もNBA選手を多く擁していたこともあり、日本でも非常に人気コンテンツとして注目の的であった。
最後に日本は、野球とサッカーが古くから人気スポーツである。地上波での放送も非常に多く、多くの人が当たり前のように野球やサッカーは「見たことがあるスポーツ」でもあると言って過言ではないだろう。特に野球に関しては地上波での放映があるために、放映権ビジネスとしても成り立っている部分があり、圧倒的に露出も多いことから人気も高い。そんな中で、バスケットボールは「新興スポーツ」として2020年以降にかけて圧倒的な成長を続けている。NBA選手の輩出はもちろんではあるが、野球やサッカーと違って「コートと客席の距離」が非常に近いため、「近くで大迫力のスポーツを観戦できる」こと、さらにイケメン選手に会いにいく「推し活」としても非常に人気になっている。発展途上ではあるものの「令和はバスケ」とも言われる中で、どこまで国民的スポーツに近づけるかに注目が高まっている。
New update just dropped for the FIBA World Ranking, presented by Nike! 🏆
Who's trending upwards? ✍️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/pVxzg21Iwu
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 18, 2025
ユーロバスケット出場国の最新版FIBAランキング
各リーグが目指しているもの
前段の通り、残念ながら各国で「1番」になれない競技でもあるバスケットボール(※リトアニア、フィリピンではバスケットボールが国技でもある)。1番ではないが、ここ数年は日本のみならず各国で大きく成長している競技とも言えるのがバスケの特徴だ。世界4代リーグは、何を目指しどのように活動しているのか。簡単に以下にまとめる。
| リーグ | 目指す方向性 | 今後の取り組み |
| NBA | 世界的なエンターテインメント産業の中で、スポーツの“完成形モデル”を維持・拡張 | ・国際市場のさらなる拡大(特にアジア・アフリカ) ・メディアテクノロジー(AR/VR、ストリーミング)の先導 ・女子バスケ(WNBA)やGリーグの収益モデル確立 |
| NBL | “世界へのゲートウェイリーグ”として、NBAへの登竜門ポジションを確立 | ・若手育成と輸出(「Next Stars」プログラムなど) ・アジア市場との連携(日本、中国との試合・中継) ・地域クラブの経済的安定と持続的ファンベース拡大 |
| ユーロリーグ | サッカーの巨大経済圏の中で、「戦術・育成・クラブ経営」の知的スポーツモデルを深化 | ・安定的なリーグ運営(FIBAとの対立緩和・財務透明化) ・欧州内のテレビ放映権収益の再分配 ・サッカーと共存する“地域総合クラブ”としての機能拡張 |
| Bリーグ | 若年層・デジタル世代を中心に、スポーツエンタメの新モデルを構築 | ・SNS・配信・VTuberなど“デジタルネイティブ層”との接点創出 ・女子バスケ・3x3などの多層的発展 ・地域と企業の協働による「クラブ×まち」モデルの成熟 |
NBAはすでにアメリカ国内ではスポーツ・エンタメ文化の頂点とも言えるような位置付けになっていることからも、よりグローバル展開に注力していく流れが取られている。ただ一方で非常に難しい話で、NBAは1チーム当たり82試合あるが、NFLは1チーム当たり17試合のみで週に1度。この辺りの希少性がNFLにはあるため「絶対この日は見なきゃ」となっている。逆に82試合という多さがグローバル展開では足枷になっているのかもしれない。
NBLはBリーグ同様に圧倒的に成長を続けており、NBAへの選手輩出など若手育成プログラムを売りに成果が出ている。NBLというリーグそのものを海外に広げるというよりは「NBLから何人NBAに輩出できるか」にフォーカスしていることもあり、特に育成に注力している傾向が強い。オーストラリア国内で見ると規模はラグビー等と比較すると小さいかもしれないが、根強い人気を誇っていることも同時に言える。
ユーロリーグはさまざまな国の強豪チームが鎬を削っていることもあり、戦術面に優れている。大袈裟にいえば、個人の身体能力だけで解決できるのがNBA。頭を使って戦術的に得点しようとするのがユーロである。あくまで大袈裟に言ってはいるものの、見たことのないバスケットのスタイルや戦術の引き出しを見ることができるのもユーロバスケの特徴である。スペイン、セルビア、フランスなど、オリンピックで「2位」の国は、大体ヨーロッパなのだ。国際大会のルールを理解した上で戦術を構築できるのもヨーロッパの特徴。「戦術を学びたい」というプレイヤーや指導者に対しては最高だが、初心者が見るには少しハードルが高いのかもしれない。
最後に日本のBリーグは、現在大注目を集めている新興リーグである。元NBA選手やアジアのトップスターたちも入ってきており、世界のトップ選手たちと日本バスケの競技レベルの向上によって、成長段階であることは間違いない。今まさに、日本全国にアリーナが建設されて「アリーナ収益の最大化」が求められつつあるが、リーグ・クラブが一枚岩となってどう最高の箱をマネタイズしていけるかに注目も集まっている。
📸🏟️🔴#GRITUP #覚悟を決めろ https://t.co/0r3yoF4rUG pic.twitter.com/VTiLDrFbJx
— アルバルク東京【ALVARK TOKYO】 (@ALVARK_TOKYO) October 3, 2025
Bリーグ10周年の開幕戦の舞台でこけら落としとなった、アルバルク東京のメインアリーナ「トヨタアリーナ東京」
今後の発展に欠かせないことは?
全てのリーグも非常に注力している4つを改めて整理して紹介したい。
| デジタル化 | SNS・配信コンテンツを最大化 |
| 地域密着と国際展開の両立 | 国内ファンを固めつつ海外市場へ発信 |
| スター選手の露出強化 | スターを軸に話題化・認知拡大 |
| 多層的ファン層の獲得 | 男女・若年層・家族層・都市/地方 |
若年層・Z世代はテレビ視聴よりスマホ・ネットで情報取得する割合が高い。これは肌感覚でもわかることでグローバルスタンダードになりつつある。伝統的放映権だけでは新規ファン獲得が難しいため、SNSやショート動画による低コストで国際的認知度を向上していくことは欠かせない。
とはいえ、デジタル施策は国際展開のみならず、地域に対しても良い影響がある。当然だが、地元チームや所属するスター選手が世界中に知れ渡れば「一目見たい」とその場所を訪れることはよくある話である。そのように、デジタル施策だけではないが、まずは国内・地元ファンを固めることでスタジアム動員・スポンサー契約・地元メディア露出の安定収益を確保することは必須事項になる。海外市場での展開は、まず国内を固めてからでも良いだろう。
さらに上記でも記載の通り、スター選手をどう作っていくかは非常に大切なこと。スターは話題の中心になり、SNS、ニュース、広告、イベントでの露出で地域のアイコンとして活躍してくれる存在だ。「誰もが知るスター選手」の存在は、メディア契約やスポンサー獲得をも後押ししてくれるはず。
スター選手の存在はファンを獲得していくことにも非常に有意に働くことが多い。そもそも初めてバスケットを見る人に対して、戦術云々を伝えても全くわからない。スポーツに限った話ではないが、シンプルに「あの選手が上手い」「あの選手がカッコいい」から入ることが多いため、まずはスターの魅力をチームやリーグがどのように発信していくかが大切である。その上で、男女・家族・若年層・地方ファンまで幅広く巻き込むことが今後の発展には間違いなく欠かせないこと。最初は友達と、次は家族と、といった具合で、一緒に連れて行く人を増やしたくなる「プラス1」の戦略も非常に重要だ。多層ファンの存在は、リーグ全体の安定収益・地域浸透・国際発信力にも直結するとも言えるため、こうした地道な努力を欠かさず行っていくことは間違いなく大切である。
それぞれのリーグで取り組んでいることは、当然ながら違いがある。BリーグとNBLが「地域密着×成長志向」モデルで伸びているが、今、全く同じようなスキームでNBAが事業拡大をしているとは限らない。逆も然りである。昨今NBAが放映権をAmazonに売ったように、そのリーグがなぜそこに権利を売ったのか、どのような狙いがあるのかまで見ていくと、今まで以上にリーグのことを面白く感じ取れるかもしれない。
Follow @ssn_supersports