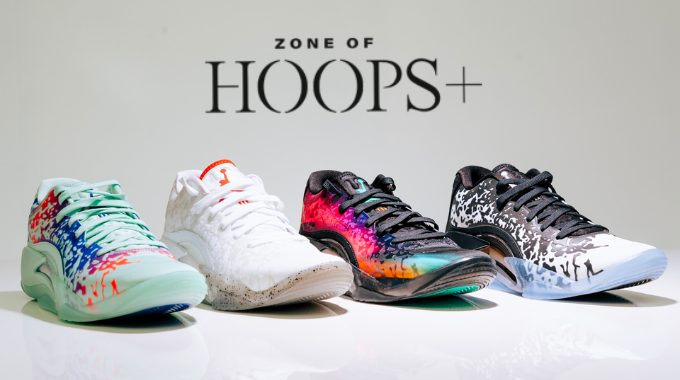スクリーンに対する守備対応は、バスケにおけるディフェンス力を測る大事なポイントです。
その中でも「アンダー」は、相手シューターや状況に応じて選択される戦術の一つです。
本記事では、そんなアンダーの基本的な意味と使われる場面を解説します。
| 知っておきたいバスケ用語 |
| ピック:スクリーンの一種で、味方のために相手ディフェンスの進路を妨害する動き。 |
| スクリーン:味方の選手を助けるために自分の体を壁のように使い、相手ディフェンスの進路を妨害するプレー。 |
| ファイトオーバー:ディフェンダーが スクリーンの上(表側)を回り込んでマークマンを追いかける動き。 |
| マークマン:ディフェンスが守るべき相手選手(担当する相手)。 |
| ボールハンドラー:オフェンスで実際にボールを持って攻撃を展開する選手。 |
| ドライブ:ボールを持った選手がディフェンスを突破してゴールに向かって積極的に攻め込むプレー。 |
バスケのアンダーとは?
バスケットボールにおける「アンダー」とは、スクリーンに対するディフェンスの方法のひとつで、スクリーンを仕掛けてくる相手選手の下側(ゴール側)を通って守る動きを指します。
通常、スクリーンに対しては「ファイトオーバー」のようにマークマンに密着して上から追随する守り方もありますが、アンダーはあえて距離を取り、スクリーンの下をくぐるように動くのが特徴です。
この戦術は、相手が3ポイントシュートをあまり得意とせず、外から打たれても脅威が小さい場合に有効です。
逆にシューターに対して安易にアンダーを選択すると、フリーで外角シュートを許してしまうリスクが高まります。
つまりアンダーは「相手の特徴を見極め、失点リスクを抑えるために使い分ける守備方法」と言えるでしょう。
アンダーのメリット・デメリット
続いて、バスケのアンダーのメリットとデメリットをそれぞれ解説します。
メリット
バスケにおけるアンダーの最大のメリットは、スクリーンにかかるリスクを減らし、エネルギーの消耗が少ない状態でディフェンスを続けられる点にあります。
ファイトオーバーのように相手に密着する戦術は体力の消耗が大きく、スクリーンに捕まる危険も高くなりますが、アンダーならスクリーンの下を通ることで接触を最小限に抑えられます。
また、相手が外角シュートを得意としていない場合には、アンダーを選択することで「敢えて距離を取り、ドライブを警戒する」守備が可能になります。
これにより、ペイントエリアへの侵入を防ぎやすくなり、チームディフェンスとしてゴール下の守備を固められる効果も期待できます。
デメリット
バスケでアンダーを使う最大のデメリットは、シューターにフリーで外角シュートを打たれやすくなる点です。
スクリーンの下を通るため、どうしてもマークマンとの距離が一瞬広がり、その隙に3ポイントやロングシュートを狙われる危険があります。
特に外角シュートの精度が高い選手に対してアンダーを選んでしまうと、大量失点につながるリスクが大きいのです。
また、距離を空ける分、相手に余裕を与えてしまい、シュートフェイクやドライブへの対応が遅れる場面もあります。
加えて、スクリーンを利用されて相手のガードにゲームメイクの主導権を握られる可能性も高まります。
まとめ:バスケのアンダーを使いこなそう
アンダーは、スクリーンに対する守備方法の一つであり、スクリーンの下を通ることで省エネルギーで守れる反面、シューターに外角シュートのチャンスを与えてしまうリスクもあります。
アンダーを理解し、メリットとデメリットを把握しておくことで、観戦では戦術の意図が分かりやすくなり、プレーではより効果的なディフェンス判断につながるでしょう。
Follow @ssn_supersports