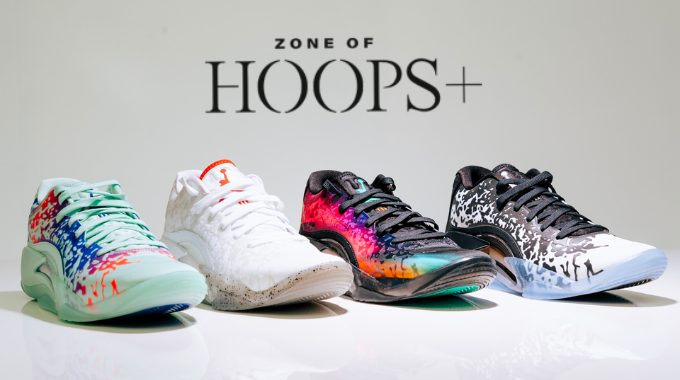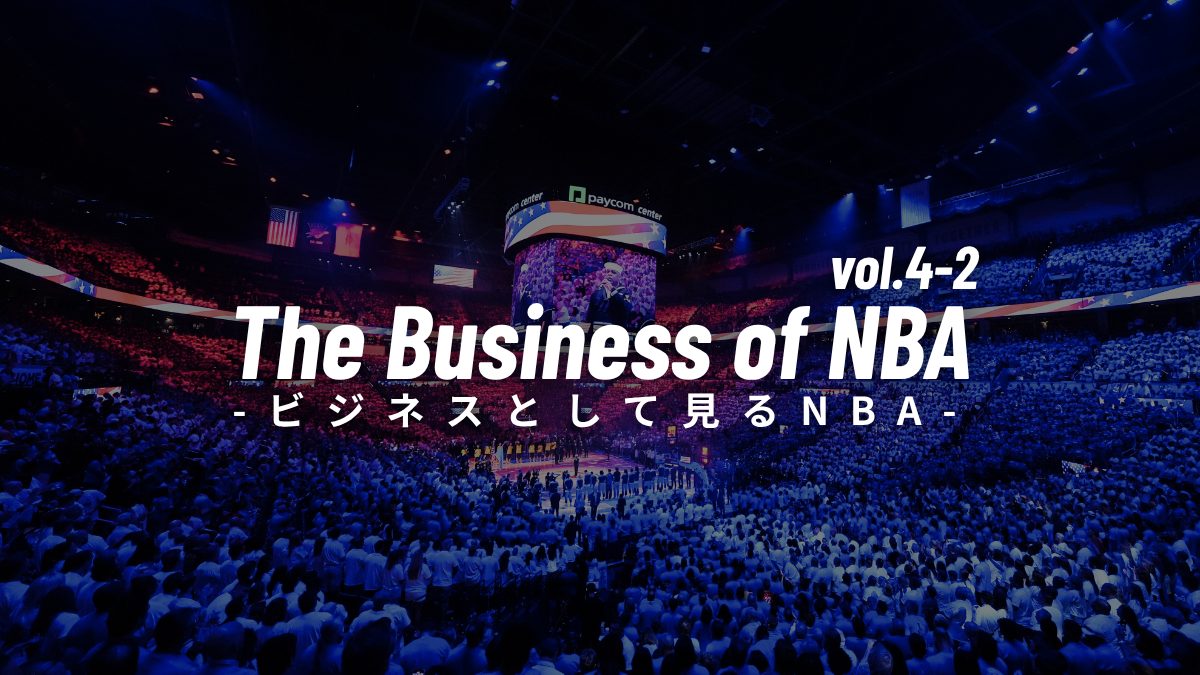
NBAをビジネス視点で深掘りする企画「ビジネスとして見るNBA」。
前回の第4弾は前編として、NBAの30球団の中でどのチームが一番選手契約にお金を使い実際にいくら支払っているか。また一番お金を使っていないチームはどこか。などを比較しながら紹介していった。また、サラリーキャップという上限があるにも関わらず、その上限を超えて契約する方法やその代償についても触れた。
今回の後編では、前編の最後に触れた一部の特例について、実例を用いながら紹介していきたい。
また、前編ではサラリーキャップを中心としたチーム全体の作り方にフォーカスしたが、今回は選手個人によりフォーカスして紹介していく。具体的に、先日シカゴ・ブルズと2way契約を結んだ河村勇輝がいるが、この2way契約とはなんなのか、といった具合に。今回はそのような具体例も織り交ぜながら、選手の契約について見ていこう。
マックス契約とスーパーマックス契約の違い
| マックス契約 | スーパーマックス契約 | |
| 対象選手 | 多くのスター選手や重要選手 | オールNBA、MVP経験者などエリートのみ |
| 支払額の上限 | NBAのキャップと例外ルールに基づく | マックスより約30%高い年俸 |
| 契約期間 | 4年(5年目オプションも多い) | 5年(最終年はプレイヤーオプション) |
| 目的 | チームの主力確保 | チームのトップスターの囲い込み |
まずこの表にある通り、マックス契約とスーパーマックス契約は大きく異なるものである。ただ、マックス契約の延長線上にスーパーマックス契約はあるため、いきなりスーパースターをトレードで獲得してスーパーマックス契約を結ぶことはできない。スーパーマックス契約を結ぶためには「最低でもそのチームに4年所属をしていること」「NBAで8年以上活躍していること」「オールスターやMVPに選出されていること」が条件としてあるのだ。
よって、どんな選手もまずは「マックス契約」を目指して努力を重ねる。そしてマックス契約を勝ち取った後は活躍を続けて「スーパーマックス契約」を掴み取るために再び努力をする。スーパーマックス契約はいわば「そのチームの顔の選手」であることの証であると同時に、チームやNBAとしても移籍させないための仕組みなのだ。
わかりやすい例として、ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフェン・カリーは、マックス契約からスーパーマックス契約にステップアップした良い例であるため、以下にまとめる。
| 契約年 | タイプ | 内容 | 年俸(日本円) | 備考 |
| 2012 | 通常マックス(控えめ) | 4年$44M | 約16.4億円 | 足首の怪我で格安契約 |
| 2017 | スーパーマックス | 5年$201M | 約60億円 | MVP受賞後、リーグ最高額 |
| 2021 | スーパーマックス延長 | 4年$215M | 約81億円 | 史上初、2回目のスーパーマックスでリーグ最高年俸選手へ |
カリーの場合は完全な成功例である。2012年10月のマックス契約の時、カリー自身はまだ今ほどの活躍ができていなかった。しかしウォリアーズとしては、2012年の3月にエースガードだったモンタ・エリスを放出して「カリーで優勝する」と心中を決めた年であり、カリーを信じて2012年の10月にマックス契約を結んだ。まだ、本当にカリーがここまで化けるともわからなかったのに。足首の怪我に苦しんでいたカリーに対するリハビリやその対応等々を徹底的に仕込んだ結果、カリーはここまで覚醒し、また5回の優勝に導くリーダーになったことは間違いない。
2017年のスーパーマックス契約の時。その前年にレブロン率いるクリーブランド・キャバリアーズにNBA FINALSで大逆転負けをしたカリーは、なんとしても汚名返上をするために尽力した。2015、2016と2年連続でシーズンMVPを受賞していたカリーは、スーパーマックス契約を結ぶ前にもう一度優勝をしたかった。そしてケビン・デュラントを迎えて優勝を勝ち取り、スーパーマックス契約をチームとしても個人としても納得いく形で結ぶこととなった。
そして2022年に再び新たな布陣でウォリアーズは優勝することになるが、これは優勝したから2回目のスーパーマックス契約をしたわけではなく、優勝する年が始まる前に「カリーはもうウチで選手生涯を過ごしてもらいたい」というフロントの熱い思いで2回目のスーパーマックス契約を結ぶことになった。そしてその年に優勝を勝ち取り、カリーは自身初となるファイナルMVPを受賞することができた。
2022年のNBA FINALSで初のFINAL MVPを受賞したカリーのハイライト
カリーはあまりにも綺麗なストーリーであるが、一方でスーパーマックス契約には代償が伴う。以下は失敗した事例について紹介していく。
ジョン・ウォール/ワシントン・ウィザーズ
ウォールは4年1億7,000万ドル(年俸約60億円)のスーパーマックス契約を結んだが、契約直後にアキレス腱を断裂し、さらに膝の怪我で長期離脱を余儀なくされた。4年間毎年60億円を支払わないといけない選手が、NBAの82試合・2年間で164試合もある中で、ウォールは2年間で40試合未満の試合出場に留まった。1/4程度しか試合に出られない選手に対して超大金を支払ったものだから、チームのお財布にとってはかなり重荷になった。高額年俸すぎてトレード市場でも引き取り手はおらず、最終的には契約バイアウト(残りの契約金の一部を払って契約解除)をする運びになったため、ウィザーズからすると完全に負債になってしまったのだ。
もちろん怪我による影響のため、一概に選手が悪いとは言い切れないが、大型契約だからこそ、このような「失敗」と呼ばれてしまうリスクは常に付きまとう。以下はスーパーマックス契約に付きまとうリスクについて簡単にまとめたものだ。
| 問題点 | 内容 |
| 高額固定給 | 年俸の急騰でサラリーキャップが圧迫され、他の選手に使えない |
| 怪我のリスク | 契約中に選手がケガをすると、チームの数年が無駄になる |
| トレードの難しさ | 巨額契約ゆえ、トレード相手が見つからない(処理が困難) |
| 成績に見合わない | MVP級のパフォーマンスが出せないと単なる高給取りに |
2WAY(ツーウェイ)とエグジビット10
| 契約名 | 目的 | 主な特徴 | 年俸の目安 |
| 2WAY契約 | NBAとGリーグの兼任選手確保 | NBA出場45日まで、Gリーグ中心 | 約50万〜80万ドル |
| Exhibit 10契約 | トレーニングキャンプ用、Gリーグ誘導 | 解雇時Gリーグ加入でボーナス最大5万ドル支給 | NBA最低年俸(約100万ドル以下)の日割り |
先日シカゴ・ブルズと2WAY契約を結んだ河村勇輝がパッと思い浮かぶが、そもそも2WAY契約はとても大変である。河村自身もラジオで話していたが、GリーグとNBAのシーズンのスケジュールは異なるからこそ、深夜に電話で「明日はNBAの試合の方に来てくれ」と呼び出されることもしばしばある。Gリーグの次の試合のために準備やトレーニングをしていたのに、NBAの試合に呼び出されてしまったのでコンディションの調整が難しい。その上で、結果を出さないといけない。
そのようなセルフコントロールが非常に求められる契約であると同時に、NBAから見れば大した額面の契約でもない。解雇もいつでもできる契約であるため、2WAYの選手はまずはなんとしてもNBAの本契約を勝ち取りにいきたいところだ。
先ほどのマックス契約と打って変わって、こちらは保証がないのだから、それほどまでに大きな差があることが一目瞭然であろう。また、2WAYは基本的に単年契約であるため、まずは本契約で複数年契約を勝ち取ることが一番近い目標。そして次はローテーションに入って試合に出ること。そして次は多くのプレータイムをもらい主力として活躍すること、と、目標は大きくなる。
もちろん、NBAには2WAY契約からチャンスを掴んで現在に至る選手も多い。オクラホマシティ・サンダーのアレックス・カルーソは、元々ロサンゼルス・レイカーズで2WAY契約の選手だったが、現在はサンダーで4年8,100万ドル(年俸で約31億円)で契約をしている。2020年にレイカーズで、そして今年サンダーで優勝をしたため、2WAY契約から成り上がってNBAで2回も優勝をした数少ない苦労人といえよう。カルーソのようになれる選手は確実に一握りであるが、目指すべきはそこであるはず。
Alex Caruso: NBA CHAMPION 🏆 pic.twitter.com/PN26FjXN3Y
— OKC THUNDER (@okcthunder) June 23, 2025
ちなみに「エグジビット10」について触れておくと、これはNBAのチームのスカウトなどが「彼はトレーニングキャンプで一度試してみたい」と思った選手に対して、トレーニングキャンプに参加させるための短期契約と言っても過言ではない。ドラフト外の選手や怪我から復帰した選手、ポテンシャルがありそうな選手に対して使うケースが非常に多く、当然ながらNBA入りの足がかりの契約とも言える。キャンプで実力を発揮できれば、2WAYなどに結びつく可能性もある。
2024年に現役を引退したがかつてブルックリン・ネッツで活躍したジョー・ハリスは、元々ドラフト外の選手でエグジビット10契約でトレーニングキャンプに参加しNBA契約を勝ち取った。スリーポイントシューターとして、キャバリアーズやネッツで活躍をし、また2019年のワールドカップではアメリカ代表選手としても活躍をした。
カルーソやハリスのように、入り口は王道ではなかったかもしれないが、最終的にはNBAで成功を収めた例はいくつもある。河村にもチャンスは絶対に来る。ここからの活躍に期待だ。
サマーリーグで大活躍を見せ、見事に今年も2WAY契約を獲得した河村のハイライト
プレイヤーオプションとバイアウト
| 項目 | 意味 | 主な特徴 | 主な利害関係者 |
| プレイヤーオプション | 選手が契約継続を選べる権利 | 選手に有利、契約延長かFA移行か選択可能 | 選手 |
| バイアウト | 選手とチームが契約を合意解除、解約金支払いで終了 | チーム・選手双方が合意、自由移籍が可能 | チーム・選手双方 |
最後に「プレイヤーオプション」と「バイアウト」の話をしたい。
そもそもNBAは複数年契約を結ぶことが多いのだが、例えばあと1年契約が残っている状態でトレードをした際に、最後の1年の契約金はどうなるのか、など細かいところも話していこう。
まずプレイヤーオプションとは、選手自身が「契約延長するか、チームとの契約を解約するかを選べる」という意味である。当然ながらチームオプションもある。例えば、4年契約の選手の最終年にプレイヤーオプションが付いた契約の場合は、4年目が始まる前に契約を続けるか、契約終了してフリーエージェントになるかを選手自身が選べるというもの。
「よりよいオファーが他のチームがある」となれば、契約終了して当該チームと契約することも多いし、そこまで良いオファーがなければ「契約延長」を選択できる選手ファーストの契約である。逆にチームオプションの場合は選択権がチームにあるため、シビアに見られることが多い。ちなみに渡邊雄太は、当時フェニックス・サンズと2年契約を結んでおり、2年目はプレイヤーオプションだった。彼はこのオプションを破棄したことで日本に帰国し千葉ジェッツと契約することができた(一説によるとBリーグ市場最大規模の年俸4億円規模の契約とのこと)。
今後もしNBAの契約周りを見る機会があれば、プレイヤーオプションもしくはチームオプションがついているか、また何年目にそれがあるかを見ておくと、より選手の動向がわかるようになるのでオススメだ。個人的にはNBAでそこまで活躍できていない選手の契約をみて「来年日本に来ないかな」などと妄想をして楽しんでいる。
もう一つ、バイアウトについて紹介したい。
冒頭にジョン・ウォールのスーパーマックス契約に関してバイアウトで着地したと記載したが、まさにその内容である。要するに、複数年契約している選手との契約を途中で打ち切るために、合意された金額をチームが選手に支払って契約解除をするという仕組みである。
通常は年俸の残りの一部のみを支払うため、例えば最後の年が1,000万ドルだとしたら、バイアウトで300万ドルだけ支払う。チームとしてはサラリーキャップの圧迫を抑えられる上で、選手としては心機一転、プレーする機会を求めて新天地へ移籍するチャンスを得ることができる。実際に、ラッセル・ウエストブルックなど再建中のチームにトレードされてリーダーとしての活躍を期待されたが上手くフィットできずにバイアウトで契約解除され、次のチームで再び輝いたケースなどもある。
ただ一方で、バイアウトの後に契約を勝ち取れなかったケースも少なくない。選手からすれば実質クビのようなものでもあり、バイアウト後にどこからも契約されずにシーズン終了&NBAキャリアの終了になった例もある。その場合は海外リーグに挑戦したり、3x3に挑戦したりするなどでプロバスケットボール選手としてのキャリアを継続するケースもあるが、そこからNBAに復帰することは容易ではない。実際のところ、アメリカでバイアウトの契約は「自由であり崖っぷちである」とまで称されている。改めて、NBAは狭き門であり、また入れ替わりも激しい。生き残れる選手は本当に一握りなのだ。
Follow @ssn_supersports