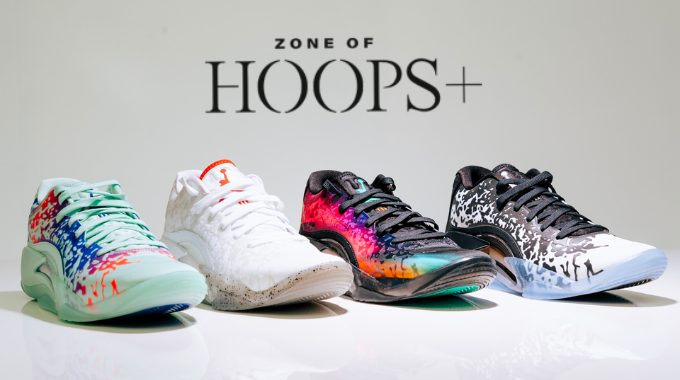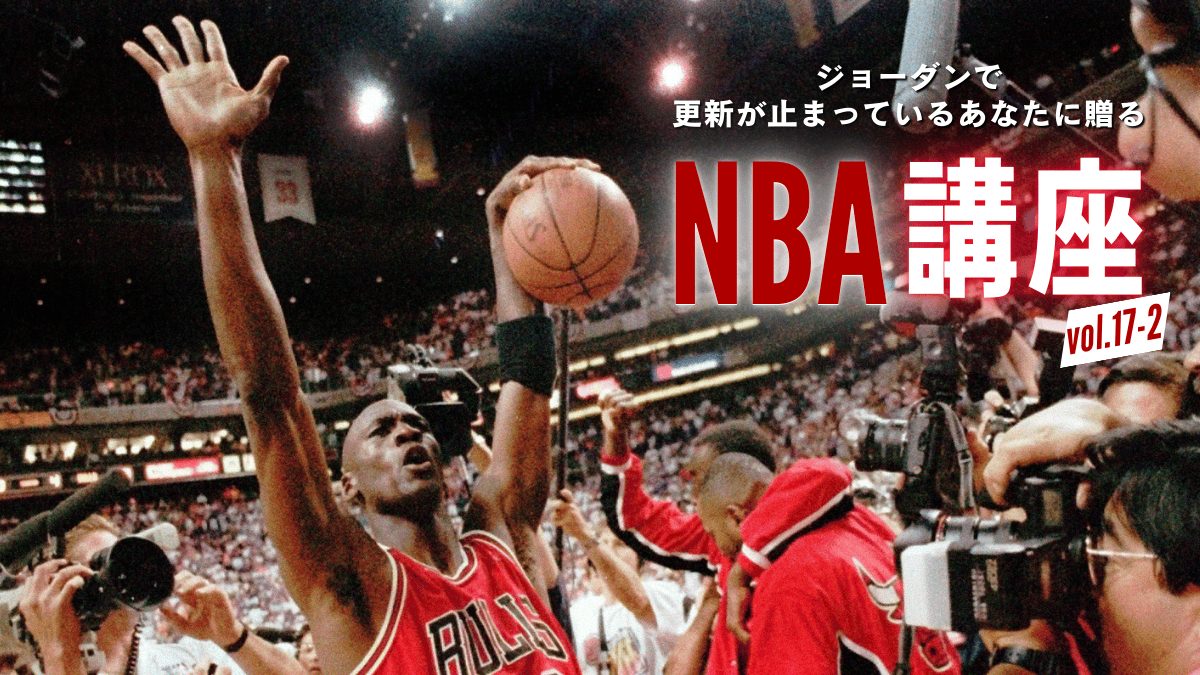
マイケル・ジョーダンの時代で大きい出来事と言えば、やはり1992年のバルセロナ五輪はその1つとして挙げられるだろう。バルセロナ五輪はこれまで禁止されてきたNBA選手の出場が解禁になり「アメリカのバスケが凄い」と世界中に知れ渡った大会である。この時のアメリカ代表は、ジョーダン、マジック、ラリー・バードなどNBAのレジェンドが名を連ね、準決勝のリトアニア戦で51点差、決勝のクロアチア戦で32点差と圧倒的な点差をつけたことから「ドリームチーム」とも名付けられた。ちなみに、この時にエースとして出場していたジョーダンは背番号「9」を着用したが、以来、アメリカ代表では「9」がエースナンバーにもなった。
1992 Dream Team vs 2024 Avengers ⚔
Who would win this game? 🔥 pic.twitter.com/sO4vvhvSgQ
— FIBA Basketball (@FIBA) August 29, 2024
1992年のオリンピックから約30年が経った今。アメリカと世界の差はここまで広いものではなくなった。その年の最強チームを組まなければ、アメリカは金メダルを取ることも非常に難しいと言われているほど、世界のバスケットの競技レベルは向上している。
今回は、ジョーダンの時代で止まっているあなたに向けて、世界のバスケットがどのように進化してきたか。その広がりと戦術について紹介していく。
オリンピックのメダル変遷
まず、NBA選手の出場が解禁された1992年のバルセロナ五輪以降の成績を以下にまとめたい。注目すべきはアメリカ以外。伝えたいことは「アメリカが強い」ではなく、「2位・3位」の国についてである。
| 年 | 開催地 | 決勝スコア | 金 | 銀 | 銅 |
| 1992 | バルセロナ | 117-85 | アメリカ(ドリームチーム) | クロアチア | リトアニア |
| 1996 | アトランタ | 95-69 | アメリカ | ユーゴスラビア(当時) | リトアニア |
| 2000 | シドニー | 85-75 | アメリカ | フランス | オーストラリア |
| 2004 | アテネ | 84-69 | アルゼンチン(黄金世代) | イタリア | アメリカ |
| 2008 | 北京 | 118-107 | アメリカ(Redeem Team) | スペイン | アルゼンチン |
| 2012 | ロンドン | 107-100 | アメリカ | スペイン | ロシア |
| 2016 | リオ | 96-66 | アメリカ | セルビア | スペイン |
| 2020(2021) | 東京 | 87-82 | アメリカ | フランス | オーストラリア |
| 2024 | パリ | 98-87 | アメリカ | フランス | セルビア |
2004年のアテネオリンピックでアメリカが3位に終わったことは、アメリカ国内でも「事件
」として扱われ「国の恥」とも言われた、アメリカにとっては最悪の年になったが、一方でバスケットボール界全体で見ると、遂に勢力図が崩れた年でもある。
そもそも、その前の2000年のシドニーオリンピックで、アメリカはフランスに「たった10点差」しかつけることができずに金メダルを獲得したが、これはフランスがシンプルに強かったからである。
そもそもヨーロッパのバスケットは”学習型”と言われており、フランスはその筆頭である。2000年のシドニーは、後にNBAでもレジェンダリーな活躍をするトニー・パーカー(元サンアントニオ・スパーズ)ら未来のスーパースターたちの若かりし頃であり、才能の片鱗を存分に見せつける大会だった。パーカーを始めとする若きスターは、まさに学生時代マイケル・ジョーダンを見て育った世代であり、NBAがジョーダン人気で国際化を広げたことでテレビでジョーダンの試合を見ることができたことが背景にある。NBAのトッププレーを見て育った。2000年のシドニーは銀で終わったが、実際に金を獲得した2004年のアテネのアルゼンチンは、まさに「国際化の波」が一気に始まった年でもあると言えるだろう。
国際化の波を作ったフランスのトニー・パーカーのハイライト
以降はヨーロッパの各国が必ず上位にランクインしている。2008年と2012年はスペインが銀メダルだが、スペインにはガソル兄弟というNBAでも活躍した210cmオーバーの2人と、ルディ・フェルナンデスというシューターを軸に上り詰めた。特に2008年のアメリカは「Redeem Team」という「2004年のアテネの惨敗から立ち上がる」と、改めてスーパースターを結成した年だったが、それでも11点差しかつけられなかったことが、世界のレベルが上がっていることを物語っている。
ちなみに、1990年代はジョーダンの人気で国際化が進んでいった、NBAにとっても非常に良いターニングポイントであるが、これはあくまで「売上を伸ばす」ためにやったことだったが、皮肉にもNBAの国際的な人気が世界各国のレベルを上げ、アメリカから金メダルを奪うという結果にも繋がった。
もし、ジョーダンの時代で止まっているあなたが見るならば、2004年のアテネオリンピックをアルゼンチン目線でぜひ見てほしい。この五輪が、時代が変わるターニングポイントであるから。
ルール緩和と戦術の違い
そもそもNBA選手は、NBAの独自ルールに慣れすぎていることもアテネで金メダルを取れなかった時に「言い訳」の1つとして語られた。NBAは1Q12分で計48分だが、FIBA主催のW杯や五輪は国際ルールに則って1Q10分。3Pラインの距離もNBAとFIBAでは違うし(NBAの方が遠い)、NBAでは禁止されていた「ゾーンディフェンス」もFIBAはOKしていたため、初めてのゾーンディフェンスに苦戦する場面も非常に多く見られた。
これらの「不慣れさ」を理解していたヨーロッパが徹底的にそこを突いた結果がメダルに繋がっていることも事実である。特に2004年のアルゼンチンのゾーンディフェンスをアメリカは全く攻略できていなかったし、「意外と」時間が短いことに気づくのが遅く、エンジンがかかることに時間を要したことも大きい。さらに言えば、ファウルの基準もNBAとFIBAでは異なったため、アメリカが適応できていなかったことも要因である。
以下、異なるルールをまとめたものである。
| 項目 | FIBA | NBA | 備考 / 影響 |
| コートサイズ | 28m × 15m | 28.65m × 15.24m(94ft × 50ft) |
NBAの方がやや広く、スペース感覚が変わる
|
| ゴール高さ | 3.05m | 3.05m | 同じ |
| クォーター時間 | 10分 × 4 | 12分 × 4 |
NBAは長いためスタミナ配分が重要
|
| ショットクロック | 24秒(攻撃権リセットは14秒の場合あり) | 24秒 |
攻撃テンポが微妙に変わる
|
| 3ポイントライン | 6.75m(約22.15ft) | 7.24m(約23.75ft) |
NBAの方が遠く、3Pシュート難易度が高い
|
| フリースローライン | 4.60m | 4.57m | ほぼ同じ |
| ペイント内制限(3秒ルール) | 3秒 | 3秒 |
NBAはゾーン解禁後も制限あり
|
| ゾーンディフェンス | OK | 2001-02以前は禁止、解禁後は3秒ルールなど制約あり |
国際チームは昔からゾーン戦術が可能
|
| タイムアウト | 5回(延長は2回) | 7回(延長は1回) |
NBAの方がタイムアウト多め
|
| 24秒ショットクロック違反リセット | 14秒(攻撃リバウンド後) | 14秒(攻撃リバウンド後) |
ほぼ同じルールだが、適用タイミングに差がある場合あり
|
| フリースロー判定 | 接触に敏感 | 比較的緩い |
NBAスターはフィジカルプレイが許容されやすい
|
| ボールサイズ | 男子:7号(FIBA公式) | 男子:7号 | 同じ |
| ジャンプボール | ゲーム開始のみ | 毎回紛糾した場合はジャンプボール |
NBAはトラブル時にジャンプボール導入
|
加えて戦術も大きく異なるものだった。2000年のシドニーオリンピックの決勝でアメリカvsフランスが素晴らしい好ゲームだったことが非常に戦術的にわかりやすい。アメリカはNBA選手らしく「個人技」を中心にした戦術だったが、フランスは「ゾーンディフェンス+スクリーンからのピック&ロール+パスゲーム」という対照的なバスケットだった。単なる個人技頼みのバスケットとは違い、スーパースターがいなくても組織力でアメリカと競えることを証明したのもこの年である。
そして2004年のアテネで敗れてからは、アメリカもゾーンディフェンスを使ったりスクリーンを活用したりしたことで、個人技+チームプレーを覚えて実践していった。ルールへの適応と戦術・組織力で歴史を変えたわけだが、以降もアメリカを苦しませ続けているのは、シンプルにヨーロッパの個人のスキルレベルが高まっているからである。
ヴィンス・カーターの「人超えダンク」が出たのもフランス戦だが、点差はそこまで大きくなかったことは意外である
アメリカは弱くなったのか?
NBA公式のプレスリリース(※1)によれば、開幕戦のロスターに名を連ねた「アメリカ以外の出身選手」は135名で、ヨーロッパ出身選手は71名だった。2000年以降、国際化が進んだNBAでは、各国にNBAのスカウトが頻繁に足を運ぶようになり、ドラフト自体も国際的なイベントになったことで、年々アメリカ国外の選手たちが増えていくようになった。
これは「フランスと大接戦をしたから」でも「アルゼンチンに負けたから」でもなく、「ジョーダンの人気爆発で放映権を世界に販売しているついでに各国のバスケを見ていったら、各国に素晴らしい才能がいることを発見した」からである。このようにして、NBAが目をつけていた世界の若き才能たちがオリンピックなどの国際大会で素晴らしい結果を残し、NBAに入ってくる流れになった。NBAが国際化に動いたタイミングと、世界が結果を出したタイミングが非常に近いため混同されがちではあるが、あくまで「国際化に向けて動いた直後に結果を出した」と考えて問題ない。
ちなみに、ジョーダンがルーキーだった1984年には、なんとヨーロッパの選手は1人もいなかったことも判明している。翌年の1985年に西ドイツ出身の選手が2名NBA入りしているが、以降もそこまで多くはない。先述の通り、一気に増えたのは2000年以降で、ジョーダンのプレーを見て育った当時の10代である。トニー・パーカー(フランス)、マヌ・ジノビリ(アルゼンチン)、ダーク・ノヴィツキー(ドイツ)、スティーブ・ナッシュ(カナダ)などなど、アメリカ以外のスターが2000年以降は特に頭角を表し、さらに現在のNBAでスーパースターと言えば、ルカ・ドンチッチ(スロベニア)、ニコラ・ヨキッチ(セルビア)、ヤニス・アデトクンボ(ギリシャ)、ヴィクター・ウェンバヤマ(フランス)、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー(カナダ)など、アメリカ以外の選手が非常に目立つ。
一方で、アメリカが弱くなったわけではない。直近のパリ五輪では金メダルを獲得しているが、レブロン、カリー、デュラントなどベテランのスーパースターを初め、テイタム、ブッカー、AE、ハリバートンなど若きスターたちも活躍した。
現在はNBA自体がグローバルな存在になっているだけに、世界各国からスーパースターが集まり、オリンピックや W杯などナショナルチームで活動する時に「自国へ帰る」形がほとんど。NBAで学んだことを自国に落とし込めることも強みであるため、おそらく今後ますます世界のバスケットの競技レベルは上がっていくだろう。すでに「アメリカ一強」の時代は終わっている。ジョーダンの時代で止まっているあなたが今のNBAを見るならば、これまで記載した戦術的な部分はもちろんだが、ジョーダンのような「個人技」で打破できる若い選手を見つけることも非常に面白いかもしれない。
プレースタイルがジョーダンと非常に似ているAEことアンソニー・エドワーズ。ジョーダンと同じく左手にリストバンドをつけている。ジョーダンが好きな方は、まず彼を見てみることをオススメしたい
※1:https://pr.nba.com/international-players-2025-26-nba-rosters/
Follow @ssn_supersports