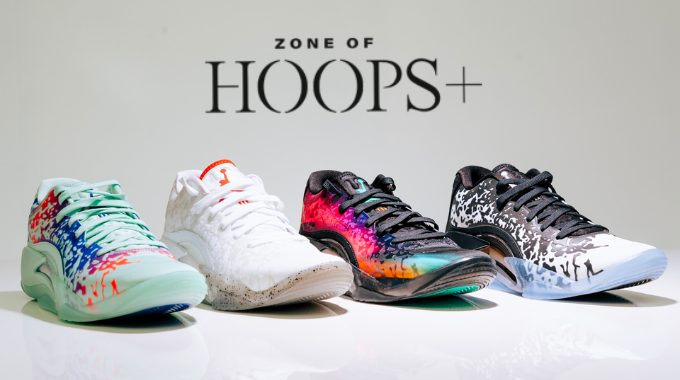日本で唯一であり、男子バスケをプレーする全ての人が目指す場所。それがB.LEAGUE(以下Bリーグ)。10月から始まる2025-26シーズンでBリーグは10周年を迎え、いよいよ次のフェーズである「B革新」による構造改革が実現される見込みだ。
昨今、人気急上昇中のプロバスケ・Bリーグが、なぜここまで人気になったのか。この企画では、近年日本のバスケを好きになった方に向けて、過去の歴史や活躍したスターなど、さまざまな角度で紹介していく。
第1弾は王道だが、男子日本バスケの歴史についてお届けする。
日本バスケの年表
まずは簡単に、男子日本バスケがここまでどんな道を歩んできたかを年表にしてまとめる。ここで全体のイメージを掴んだ上で、次の章に移ってほしい。
| 1947年〜2000年頃 | JBA(日本バスケットボール協会)発足、実業団が人気 |
| 2005年〜2016年 | 実業団「JBL」とプロリーグ「bjリーグ」で分裂 |
| 2016年〜2019年 | 統一リーグの「B.LEAGUE」が発足・成長 |
| 2019年〜現在 | 八村塁が日本人初・NBAドラフトで指名される。以降、海外とのパイプが拡大中 |
実業団時代
まず、日本におけるバスケの歴史については1947年に日本バスケットボール協会(JBA)が設立されたところから伝えたい。
そもそも1945年に第二次世界大戦が終戦するまで、当たり前ではあるが全ての文化的な活動は止まっていた。終戦を機に「もう一回色々と立て直そう」と、GHQが教育や文化振興の一環としてスポーツを推奨し、野球やサッカー、バスケ、バレーなど各スポーツの団体の設立を進めたことから全ては動き出す。要するに「戦後の復興」だ。
その一環としてJBAが設立されるがもう少し深掘りをすると、戦後の日本は「国際スポーツ界」から除外をされてしまっていたため、FIBA(国際バスケットボール連盟)に加盟するために国内協会(=JBA)が必要となったことで立ち上がってもいる。ちなみに、日本のスポーツの中で戦後に一番最初に協会を作ったのはバスケであった。
このようにして戦後の復興と国際スポーツ界への復帰を果たし、また国内でも天皇杯がスタートしたことで、戦後の日本バスケが本格稼働していく。
とはいえ、最初の天皇杯はわずか8チームほどが出場する小さな大会。優勝も慶應義塾大学が果たしていた。これは完全に戦争の影響である。企業はバスケをしている場合ではなく、とにかく復興で手いっぱいだったのだ。このように最初は「学生スポーツ」の側面が強かったものの、1950年以降になると高度経済成長を経て経済的な余裕が出てきたいくつかの日本企業が「バスケは野球やサッカーに比べて場所を取らないし屋内でできるから良いね」といった具合で人気を集め「実業団」として取り組み始める。具体的には三菱電機(現:名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)や、東芝(現:川崎ブレイブサンダース)などだ。
また企業として実業団スポーツを行っていることは、当時の日本社会において非常に大きな宣伝活動や社会的信用を作ることで役立ったため、年々実業団チームが増えていった。
1967年には、日本の実業団・社会人トップリーグとしてJBL(日本バスケットボールリーグ)が設立された。リーグも企業のスポンサードによって運営されていたこともあって、参加するチームは企業名が基本とされた。現在の川崎ブレイブサンダースが、当時「東芝ブレイブサンダース」だったように。
このようにして基盤を作ったJBLであったが、時代が進んでいくに連れて日本でスポーツは人気のコンテンツにどんどん成長した。その成長に対してバスケットは、なかなか世界で勝てなかったことで人気コンテンツにはなれなかった。同時に「実業団でやっている限り、世界では戦えない」という批判すら集まった。
一方でJBLは日本のトップリーグとして機能はしていたものの、あくまで「会社のチーム」という側面が強かったためマニアックなコンテンツとなってしまい、またリーグも企業からの出資で成り立っていたため企業側の意向を受け入れる他なかった。トップリーグと謳いながらも「プロ」ではない。しかし「プロ」としての道を選ばないことにはファンも増えないし世界で戦えない。人気が上がらない…。
そんな問題を解決に導けないJBLに嫌気が刺した一部の人が集まって「 JBLがやらないのなら自分たちがプロリーグやります」と立ち上がったのが、2005年の「bjリーグ」である。
分裂
この頃になるとJBLは「実業団依存」とまで言われるほどの体制になっていた。ただJBLとしては前途の通り、あくまで企業チームが中心のコンテンツが大前提のため、極端ではあるがリーグ運営は「企業満足度向上施策」の1つであった。言い過ぎかもしれないが当時バスケの試合は「社内イベント」くらいのものであったため、世の中に広がることはほぼなく、メディア露出も少なければチケット収入はほぼない状態だった。よって、試合にくるのは社員や選手の家族。上司やパパの頑張る姿を見て笑顔になる。素敵なことではあるが、その選手たちが日本を代表して世界で戦うとなると話は変わってくる。
あくまで彼らは実業団であるため、仕事をしながら働いていた。練習時間は仕事終わりの短い時間だけ。コンディションは個人に委ねる形。その人たちが世界大会に出場して、最初は応援されていたが、いつまでも勝てない結果を見てしまうと「実業団だから勝てないんだ」と言われてしまうことも増えた。
そんな状況に、ついに耐えられなくなった一部の人たちによって結成されたのが「bjリーグ」である。bjリーグが決定的に違ったのは「選手契約」。JBLのような社員雇用ではなく、完全プロ契約として、選手をバスケットに集中できる環境を整えた。またサッカーのJリーグのように地域密着型のクラブ運営を目指し、観客を増やすためにオープンに情報を発信し試合もエンタメ重視で運営を行った。これによって、徐々に成長していったbjリーグではあったが、JBA(日本バスケットボール協会)の許可を得ていない「非公式」のリーグであったため、JBAはもちろん、これまで唯一無二の存在だったJBL側からの反発も異常なほどだった。
JBL側からするとbjリーグが立ち上がった2005年には、もうリーグが始まってから40年近い歴史があったため「安定」があった。JBLの選手は社員でバスケ選手という、給与も環境も保証された状態で満足度も高かったため、bjリーグの「革新的」で「挑戦的」で「不安定」な思想を持っている彼らのことを「これまでやってきた方法を否定されているのではないか」「自分たちの権限をbjが奪うのではないか」と敵対視した。これまでの常識が壊される気がしてならなかったからだ。変わることが怖かったJBLは、このような背景もありbjリーグを「無視」または「敵対視」した。
ここから「国内2リーグ」へ分裂していくわけだが、日本バスケットボール協会の協力を全く得られなかったにも関わらず、bjリーグはどんどん規模を大きくしていった。ただ、結果的に部分的には成功し部分的には失敗に終わる。
成功したところは間違いなく地域密着のクラブを作れたこと。これはJBLだけでは不可能だった。またbjリーグのビッグカードの試合では観客動員が3,000人〜4,000人規模まで増えた試合もあり、純粋なバスケファンがふえていったのも事実。今の「秋田ノーザンハピネッツ」や「琉球ゴールデンキングス」ができたこと、また地方でもバスケットボールが人気コンテンツであり続けているのは、間違いなくbjリーグの功績であろう。
ターキッシュ エアラインズ bjリーグ。本日、bjリーグとしては最後となる開幕前のプレスカンファレンスが行われました。海外遠征中の富山を除き、23チームの選手が集まり、新シーズンへの意気込みを語りました。 pic.twitter.com/4MDq0BTcmS
— プロバスケ 2nd SEASON (@bj_league) September 17, 2015
一方で失敗に終わったのは経営の不安定さと日本代表全体の強化。
そもそもbjリーグは「プロ」と言いつつも、不安定な経営により給料未払いなどの問題が発生したことや運営体制の甘さなど悪目立ちしてしまう部分が多かった。赤字によって、チームそのものがなくなってしまうところもあった。加えて、結局のところJBLとbjリーグの2つのリーグがあることで、かつJBLの方が経営的にも安定していたこともあったため選手も多く流れた。これによって結果的にはbjリーグの選手が代表に選ばれないことも多かった。
このようにして、「JBL」と「bjリーグ」という、国内に2リーグある分裂状態が続いたことと、その状態にありながらも国際大会で全く勝てなかったことがキッカケで、FIBAは2014年に「日本のトップリーグが統一されるまで国際大会の出場資格を剥奪する」と制裁を与えた。
日本バスケ界は「変わるのが怖い」でお互いを歪みあっている場合ではなく「変わらないと日本からバスケがなくなる」という状態に入ったのだった。
※JBLはbjリーグが立ち上がる前に「NBL」とリーグ名を変えて新たにプロ化に向けてポーズを取ったが、実際は名前が変わっただけでほぼ何も変わらなかった。次章からJBLはNBLとして登場する
Bリーグ発足
2014年にFIBAが与えた制裁によって、日本バスケは大きく動き出す。
「NBL」と「bjリーグ」の2つのトップリーグが存在していること、またそれぞれの対立関係を解消できないことに対して「1つのリーグに統一するまで国際大会には出しません」とJBAに制裁を与えた。正式に「出場資格停止処分」がFIBAからJBAに届いたのは、2014年11月26日のことだった。
この「出場停止処分」は、アジア杯やW杯、オリンピックなど、ありとあらゆる国際大会が対象。よって、リーグを統一しないことには日本のバスケットの発展はあり得ないこととなった。
また、FIBAからは「改善案を翌年の2015年6月末までに提出せよ」という期限付きの改善命令が出されたため、本格的に動かなければいよいよ目前に迫っている「リオデジャネイロ2016オリンピック」本戦はもちろん、本戦出場権をかけた「オリンピック予選」の出場権も得ることができない。
この問題はJBAという協会だけではなく、文部科学省やスポーツ庁まで影響が及んだ。当然、国内リーグの歪みによってオリンピック出場権ではなく出場をかけた予選大会への「参加権」を得られないことは国としてあまりにも不名誉なこと。なんとしてもオリンピックへの「参加権」を獲得するために、FIBAと国が行動に移した。
有名な話ではあるが、白羽の矢がたったのが川淵三郎氏である。Jリーグを創設した張本人であり、日本サッカーを大きく変えた人物で、FIBAやスポーツ庁からの信頼が厚かった。一方でJBAは、NBLとbjリーグの内乱を止めることに精一杯で身動きが取れなかった。FIBAも「JBAにはこの改革を実行する能力はない」と批判されたいたこともあり、政府・FIBAご指名で川淵氏を招聘した。
川淵氏がJBA改革タスクフォースを発足させたのが2015年1月。
ここから川淵氏は、まるで嵐のように、今までの出来事をなかったかのように、一気に改革を進める。NBL、bjリーグ首脳陣と会談を繰り返し、どのようにしていくことがお互いのためになるか、そして日本バスケ界のためになるか、と。そうして会談を繰り返し正式にタスクフォースが決定した「新リーグ構想」は、以下の通りである。
| 項目 | 内容 |
| 統一リーグ名 | 仮称「JAPAN NEW LEAGUE」 → 後の「B.LEAGUE」 |
| 発足時期 | 2016年秋(翌シーズン)開幕 |
| 方式 | 3部制(B1・B2・B3)のライセンス制導入 |
| ライセンス | 経営状況・アリーナ・地域貢献などでクラブを審査 |
| bj・NBL・NBDLの全チームを統合 | 希望・基準クリアによって再編成される |
これを持って、2015年8月にFIBAは資格停止処分を解除した。リオデジャネイロ2016オリンピックへの出場権をかけた予選にも出場したが、残念がら本戦へ出場することはできなかったものの、これによって日本バスケの未来は一気に明るくなった。
B.LEAGUE 36クラブ 決起会
川淵会長と大河チェアマンの「いくぞ!」のかけ声に全36クラブの代表は力強く呼応しました!#Bリーグ pic.twitter.com/YOKzqnQMkB— B.LEAGUE(Bリーグ) (@B_LEAGUE) June 16, 2016
2015年8月以降は新リーグ準備期間として各チームにライセンスが付与されて粛々と進み、2016年9月22日、ついにBリーグが開幕した。対戦カードはNBL(実業団)で王者だった「アルバルク東京(トヨタ自動車アルバルク)」vs bjリーグで王者だった「琉球ゴールデンキングス」。こうして日本バスケは、NBLとbjリーグの双方の良いところを全て吸収して1つのリーグとして現在も運営がされている。「令和はバスケ」と呼ばれるほど人気コンテンツになっているのは、一概に川淵氏だけの功績ではなく、bjリーグという不安定な夢を持った集団のおかげでもあり、またNBLという基盤を作ったリーグがあったからでもあろう。
また、細かい話ではあるが、川淵氏はBリーグ創設のためのタスクフォースのチェアマンであり、Bリーグ初代チェアマンではない。初代チェアマンは大河正明氏が就任した。大河氏はJリーグ初期にも幹部として川淵氏を支え続けてきたいわば右腕的な存在であり、また金融出身で組織経営に強かったこともあり、リーグ初期の制度構築や経営実務を任せるに非常に適任とされ、川淵氏から直々の指名を受けてチェアマンとなった。
大河氏の功績もあり安定的に人気を伸ばしてきたBリーグだったが、2020年以降は「成長」「収益化」など「さらに大きくしていくため」の動きが必要だった。そこで、千葉ジェッツの代表でありクラブを大きくした張本人であり、デジタルマーケティングに長けた島田慎二氏に2020年にバトンを渡した。
そして島田チェアマンは2026年に新たな「B.革命」という取り組みを大きく打ち出している。次回は、この内容について紐解いていく。
【番外編】JBL出身、bj出身チームの一覧
<JBL(NBL)出身チーム>
| チーム名(Bリーグ) | 前身の所属リーグ | 当時のチーム名 |
| アルバルク東京 | JBL → NBL | トヨタ自動車アルバルク東京 |
| 川崎ブレイブサンダース | JBL → NBL | 東芝ブレイブサンダース |
| 宇都宮ブレックス | JBL → NBL | リンク栃木ブレックス |
| サンロッカーズ渋谷 | JBL → NBL | 日立サンロッカーズ東京 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | JBL → NBL | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋 |
| シーホース三河 | JBL → NBL | アイシンシーホース(三河) |
| 千葉ジェッツ | NBL(元bjだがNBL参加) | 千葉ジェッツ(NBL時代に転入) |
| 大阪エヴェッサ | bj→NBL | bj初年度創設、のちNBLへ移行(統一前) |
| 三遠ネオフェニックス | JBL2 → NBL | オーエスジーフェニックス → 浜松・東三河フェニックス |
| 越谷アルファーズ | JBL2 → 地域クラブ → B参入 | さいたまブロンコスが前身、JBL2経験あり |
| 佐賀バルーナーズ | JBL2 → 地域クラブ → B参入 | 旧:佐賀郡信用金庫クラブが前身(JBL2参加歴あり) |
| 西宮ストークス | JBL2 → NBL | 旧:兵庫ストークス(和歌山トライアンズと同系) |
| 熊本ヴォルターズ | JBL2 → NBL | 旧:オーエスジー熊本(前身:NBL) |
| 横浜エクセレンス | JBL2 → NBDL → B3 | 元東京エクセレンス、JBL2優勝歴あり |
| 東京ユナイテッドBC | JBL2系 | 旧:レノヴァ東京(JBL2短期参加) |
| 豊田合成スコーピオンズ | JBL2 → B3 | 純・実業団、JBL2からの参加歴あり |
<JBL(NBL)出身チーム>
| 琉球ゴールデンキングス | 2007年〜 | bjリーグ最多優勝(4回)/bjの強豪筆頭 |
| 秋田ノーザンハピネッツ | 2010年〜 | 地元密着でbj時代から人気/bj準優勝経験 |
| 仙台89ERS | 2005年〜 ※創設メンバー |
bj初期チーム/NBLを経てB1に昇格 |
| 新潟アルビレックスBB | 2005年〜 ※創設メンバー |
JBL→bjに移籍した特殊チーム/長い歴史 |
| 滋賀レイクス | 2008年〜 | 地域密着型/当時成績の波はあったが現在B1常連 |
| 大阪エヴェッサ | 2005年〜 ※創設メンバー |
bjリーグ初代王者(3連覇)/現在はB1西地区 |
| 青森ワッツ | 2013年〜 | bj後期の新規参入チーム/地域密着型 |
| 福島ファイヤーボンズ | 2014年〜 | bj最終期に創設/B2定着 |
| 群馬クレインサンダーズ | 2011年〜 | bj中期創設/現在はB1定着 |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 2011年〜 | bj中期創設/現在はB2 |
| 島根スサノオマジック | 2010年〜 | bj中期創設/現在はB1定着 |
| 熊本ヴォルターズ | 2013年〜 | bj終盤期に創設/現在はB2 |
| 鹿児島レブナイズ | 2013年〜 | bj後期参入/現在はB3 |
| 金沢武士団 | 2015年〜 | bj最終年参加/現在はB3 |
Follow @ssn_supersports