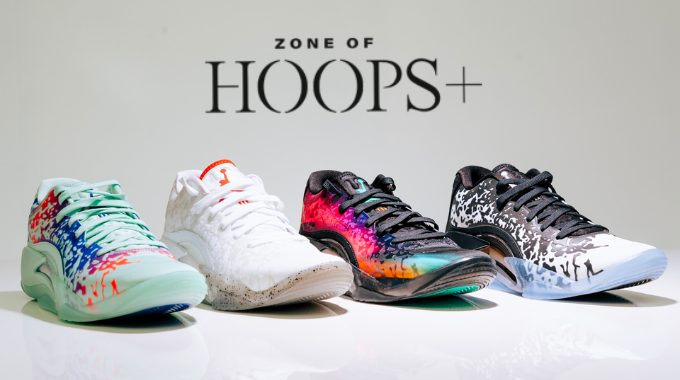バスケットボールでは、スクリーンプレーをめぐる攻防が試合の流れを左右します。
その中で重要な戦術の一つが「ファイトオーバー」です。
本記事では、ファイトオーバーの基本的な意味や使われる場面について解説していきます。
| 知っておきたいバスケ用語 |
| ピック:スクリーンの一種で、味方のために相手ディフェンスの進路を妨害する動き。 |
| スクリーン:味方の選手を助けるために自分の体を壁のように使い、相手ディフェンスの進路を妨害するプレー。 |
| アンダー:相手がスクリーンを仕掛けてきたときに、ディフェンスが スクリーンの下側(ゴール寄り)をくぐって回避する動き。 |
| マークマン:ディフェンスが守るべき相手選手(担当する相手)。 |
| ボールハンドラー:オフェンスで実際にボールを持って攻撃を展開する選手。 |
| ドライブ:ボールを持った選手がディフェンスを突破してゴールに向かって積極的に攻め込むプレー。 |
バスケのファイトオーバーとは?
ファイトオーバーとは、スクリーナー(スクリーンをかける選手)の上を通り抜けて、ボールハンドラーを追い続けるディフェンス戦術を指します。
ディフェンスがオフェンスのスクリーンに対処する際の基本技術の一つです。
ファイトオーバーを実施するコツ
続いて、ファイトオーバーを実施するコツについて解説します。
ディフェンス同士の掛け声
ファイトオーバーを的確に行うためには、ディフェンス同士のコミュニケーションが欠かせません。
特にスクリーンを仕掛けられる瞬間は視界が狭くなり、マークマン本人が気づけないことも多いため、味方からの「スクリーン!」「オーバー!」といった掛け声が大きな助けになります。
事前に声で知らせてもらうことで、ディフェンスは一歩早く準備ができ、スムーズにスクリーンを回避しやすくなります。
マークマンへの密着
ファイトオーバーを成功させるためには、マークマンとの距離感が大きなポイントになります。
スクリーンを仕掛けられる直前に少しでも間合いを空けてしまうと、簡単にブロックされて相手にシュートを許してしまいます。
逆に、常にマークマンに身体を寄せてプレッシャーをかけ続けることで、スクリーンの効果を最小限に抑えられるのです。
密着していれば、スクリーンを回り込む際も素早く追随でき、シュートやドライブに対しても遅れを取るリスクが減ります。
ファイトオーバーのメリット
続いて、ファイトオーバーのメリットを解説します。
継続してプレッシャーを与えられる
ファイトオーバーの最大の利点は、ボールハンドラーに対する守備強度を落とさずに済むことです。
元のマッチアップを維持できるため、相手のリズムを崩しやすく、特に優秀なスコアラーに対して有効です。
3ポイントシュートを抑制できる
アンダーディフェンスと異なり、ファイトオーバーは外角からのシュートチャンスを与えにくい利点があります。
現代バスケにおいて3ポイント阻止は極めて重要で、この点でファイトオーバーは戦術的価値が高いと言えます。
スイッチ時の身長差回避
ファイトオーバーをすることで、身長やスピードに大きな差がある選手同士のミスマッチを防げます。
例えば、ガードがセンターと対峙することを避け、本来の役割分担に従ってプレーできます。
ファイトオーバーのデメリット
続いて、ファイトオーバーのデメリットについて解説します。
フィジカル面でハード
ファイトオーバーにはスピード、敏捷性、持久力が必要で、フィジカル的にはかなりハードな技術です。
体力消耗も激しく、試合終盤での実行は困難になる場合があります。
ファウルのリスクが高まる
ファイトオーバーではスクリーナーとの接触が避けられないため、不必要なファウルを犯すリスクが他の手法より高くなります。
特に主力選手のファウルトラブルは致命的です。
ドライブ阻止が難しい
ファイトオーバー直後は一瞬の隙が生まれやすく、素早いボールハンドラーにドライブを許すリスクがあります。
特に1on1能力の高い選手には逆効果になる場合があります。
リバウンドが取りにくくなる
ファイトオーバーを実施するとディフェンス側は数的不利になりやすいため、リバウンドが取りにくくなります。逆に、アンダーディフェンスの場合はリバウンドが取りやすくなります。
まとめ:バスケのファイトオーバーを上手く活用しよう
ファイトオーバーは、相手のスクリーンを突破してマークマンに食らいつくための基本かつ重要なディフェンス技術です。
成功させるためには、マークマンへの密着や仲間との掛け声といった細かな意識が欠かせません。
ファイトオーバーを習得したい方は本記事を参考にして、ぜひファイトオーバーをマスターしてみてください。
Follow @ssn_supersports