

2月1日からの株式会社ミクシィによるFC東京の経営権取得が正式に決定した。
ミクシィは、ソーシャルネットワーキングサービスやゲームアプリなど、デジタルエンターテインメントを軸に事業展開する企業でありながら、スポーツ領域にも進出し、兼ねてからスポンサー契約を結んできたFC東京をはじめ、Bリーグ・千葉ジェッツふなばし、スケートボード金メダリスト・堀米雄斗とのサポート契約など、近年、スポーツ界における存在感を増してきた。
ソーシャルネットワーク分野において一時代を築いたミクシィは、スポーツ分野でなにを目指し、どのような変革を狙っているのか──。
稀代の経営者、ミクシィ・木村弘毅社長の真意に迫る。
■クレジット
取材=上野直彦、本田好伸
構成=原山裕平
写真=福田俊介
■目次
・学生時代にヒットを生む感覚はなかった
・XFLAGはミクシィと“ケタ違い”の熱量
・堀米雄斗が表現する若い世代の世界観
・木村社長はなぜスポーツにベットする?

学生時代にヒットを生む感覚はなかった
──木村社長は20代後半から30代前半の頃、電気設備会社や携帯コンテンツ会社などを経て株式会社ミクシィに入社されました。なぜミクシィに興味を持ったのでしょうか?
木村弘毅(以下、木村) 進路について一番強く考えたのは大学生のときです。「エンターテインメント産業で働きたい」という想いがなんとなくありました。そのなかで、究極のエンターテインメントってなんなんだろうと、考えていたんです。
大学生のとき、友達とゲームをやったり、一緒にスポーツをしたり、一緒に映画を見に行ったりすることが楽しかったんです。「遊ぶのって、なんでこんなに楽しいんだろう」と考えたときに、すべてに共通するのは『コミュニケーション』だな、と。友達と一緒にやっていればなんでも面白いということに気付きました。
でも、大学に入学した頃は、インターネットという概念自体がまだ一般的ではありませんでした。理系でしたけど、インターネットは学内インターネットを使う程度でしたから。ただこのインターネットというものが、これから多くの人をつなぐコミュニケーションの媒介になるのではないかと感じていました。
なので、将来はそっちの道に進むんだろうなと、おぼろげに思っていましたね。
──ただ、最初はインターネットとは別の業種で働かれていますね。
木村 学生時代に父親が倒れてしまい、会社をしばらく継ぐことになりました。27歳くらいまで続けてきて、「このままでいいのかな」という想いが、次第に強くなって。
ITの知識はまったくありませんでしたが、企画書を書いて、モバイルサービスを作っているプロバイダを何社か当たって、コミュニケーションサービスをやっている会社に入れました。
そこから別の会社に移ったときに、SNSのmixiというものがこの世に登場しました。僕はそれを見たときに「時代が変わる」、「絶対にSNSをやるんだ」と確信しました。
当時のmixiは、まだモバイル版を出していませんでした。前職の会社がモバイルのSNSを立ち上げるということでそちらにジョインして「打倒・mixi」で戦ってきました。ただ、敗戦濃厚になったので、僕はmixiの軍門に下ったわけです(笑)。
様々な原体験を伴って、コミュニケーションは人にとって欠かすことのできないものだし、商売としてもとんでもないパワーを持っているものだと理解しました。
──たしかに、コミュニティは今も昔も人々の生活に不可欠なものですよね。
木村 そうですね。ただ、専門的な区分で言うと「コミュニティ」と「ソーシャルネットワーク」はまったく異なるものなんです。僕は後者に大きく傾倒していきました。
──少し、その違いを教えていただけますか?
木村 数学的な構造上の違い、ですね。インターネットのコミュニティは、特定のクラスターが等しくつながっています。これは対称性のある人間関係。一方、ソーシャルネットワークは、どこかでポンと生まれたときに拡散を始めます。Twitterなどで「バズる」と言いますよね。この拡散性が構造上の強みです。これは非対称性の人間関係です。
コミュニティは、実際の家族や友人、知人のクローズドで狭い人間関係で、ソーシャルネットワークは、非対称でクローズドな人間関係という点で爆発的なパワーを持っています。ここがまさに、僕がハマっていった要因です。
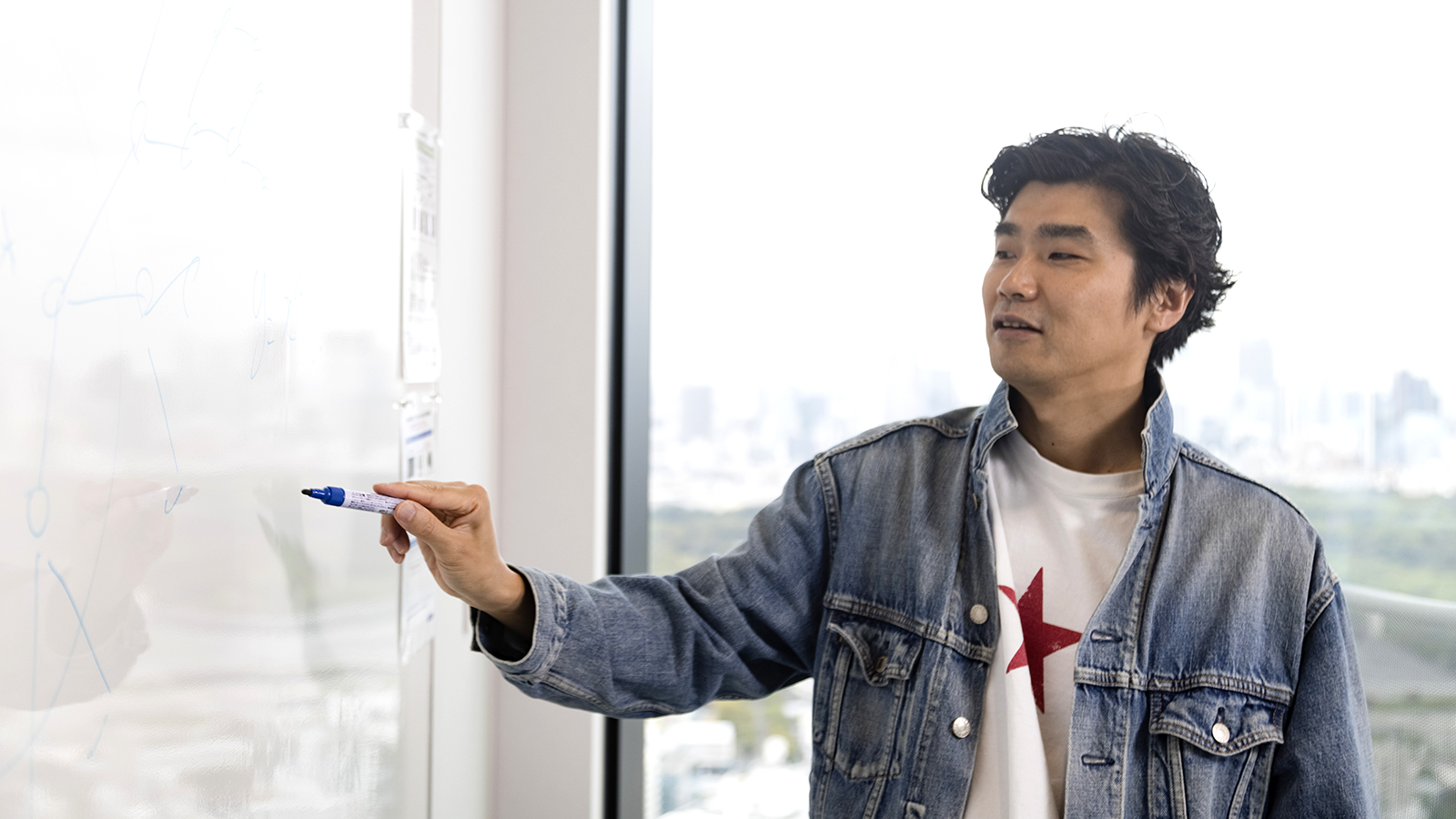
──「ソーシャルネットワーク」に可能性を感じた先見の明はどう培われたのでしょうか?
木村 先見の明かはわからないですが、僕の思考はトレーニングによって培われたように感じます。自分の趣味嗜好はいわゆる“普通”じゃないと思っているのですが(苦笑)、自分が好きなものは一般的に流行るものではないと、逆説的に思っていました。
──流行っていなくても「これは面白い」と思えばそこに進んでいける。
木村 そうですね。たとえば僕は、プライベートでもピンクが好きで、家の床もピンクですからね。中学の部活はバドミントン部で、ガットも全部ピンク。漫画は『リボン』しか読んでいませんでした。小さい女の子が僕の中にいるんだと思っていましたよ。今はだいぶ、おばちゃんですが(笑)。だからたぶん、先見の明ということではなくて、ひたすら尖っていた。そんなにヒットを生めるような感覚は持っていませんでしたね。
──学生時代はすごく勉強をされていたんですか?
木村 そこそこはしていたと思います。ただ、勤勉かと言われたら、またちょっと違って。勤勉じゃないのに塾に通ったうえ、家庭教師を2人もつけてもらったりして、自分を縛り付けていました。
──それはどうしてでしょうか?
木村 あえてやらなければいけない状況に追い込んでいました。なぜなら、やらないと成長できないので。だけど、1人だとサボることはわかりきっていたので(笑)。
親からは一度も「勉強しろ」と言われたことはないですが、小学生のときは週7日で習い事や塾に通っていました。今はないですけど、小学生のときは白髪がけっこうあったんですよ。追い込まれる環境に自分を置きたがるような性格でしたね。
XFLAGはミクシィと“ケタ違い”の熱量
──現在の事業にも、これまでの事業にも、まず「ソーシャル」があり、そこにゲームやスポーツ、スポーツベッティングを掛け合わせてきたような感覚ですか?
木村 おっしゃる通りですね。私はSNSの「mixi」の企画担当もしていましたけど、ソーシャルネットワークの上に、ソーシャルアプリケーションレイヤーがある概念です。アプリケーションレイヤーのところには、ゲームがあったりとか、カレンダーがあったりとか、様々な便利なコミュニケーションツールがある。
そのソーシャルアプリケーションの中に、友達と一緒に遊ぶ「モンスト」だったり、ソーシャルベッティングの「TIPSTAR(ティップスター)」があったり、あるいはみんなで一緒にスポーツを観戦できる「Fansta(ファンスタ)」というものがあったり。すべてがソーシャルアプリケーションという概念なんですよね。
──お話を伺っていると、いくらでも派生していきそうな感じですが。
木村 そうですね。最近だと、ネットワークレイヤーのところにも触手を伸ばしています。その一つに、「家族アルバム みてね」というサービスがあります。これはグローバルで1千万ユーザーまで来ているんですね。密かにどんどん増殖していっている状態です。
──「XFLAG」というブランド自体はどういった経緯で立ち上がったのでしょうか?(※)
木村 単純に、エンタメのパブリッシャーブランド、パブリッシャーレーベルを作りたいというのがありました。「ミクシィ」とエゴサすると、基本的にはソーシャルネットワークのmixiが一番上に出てくるわけです。
やはり「ミクシィ」というワードは認知度が圧倒的に高い。でも、SNSとしての認知度が高いだけで、スポーツとかエンターテインメントとか、熱量の高い系のものを表現するブランドとしては、ちょっとソフトすぎるかなというものがありました。
私の個人的なブランドイメージでは、ミクシィはスイーツ系。「XFLAG」はどちらかと言えば、背脂を使ったコテコテのラーメンみたいなものですね(笑)。
──だいぶイメージが違いますね。
木村 当時、ミクシィの社是みたいなのがあって、「全ての人に心地よいつながりを」というようなソフトな感じでやっていました。だけどXFLAGのほうでは「ケタハズレな冒険を。」と、だいぶ変えていました。
我々がサポートするBリーグ・千葉ジェッツが優勝しましたけど、スポーツは“ケタハズレ”なチャレンジをしないと、頂点には到達できないもの。堀米(雄斗)くんもそうですね。決勝でリスクを冒して、難易度の高い技にトライしなければ金メダルには届かなかったと思います。
そういう「ケタハズレな冒険をしよう」というブランドを作らないと、なかなかゲームやスポーツといった、激しい領域をカバーできないなと。
※mixiは2022年1月4日に「コーポレートブランドリニューアル」を発表。「心もつなぐコミュニケーション」を掲げる今回のブランディングの一環として、デジタルエンターテインメント事業やスポーツ事業領域のサービスを中心に「MIXI RED(ミクシィ・レッド)」のロゴを使用すると発表している。実際に、FC東京の胸にも昨シーズンまでの「XFLAG」ではなく、新シーズンから「MIXI RED」が刻まれている。

堀米雄斗が表現する若い世代の世界観
──堀米選手との出会いは、どういうきっかけで?
木村 エージェントさんからのご紹介です。「すごく有望なおもしろい子がいるよ」ということでお会いして、「すごいね」、「いいね」、「スケボーかっこいいな」と。東京オリンピックの活躍が象徴的ですけど、新しい若い世代にとっての“ソーシャルグッド”を体現してくれるアイコンだなと思いました。
──これまでのスポーツとは、方向性が違いますよね。
木村 若い子たちが「かっこいい」とか、失敗しても助け起こしたりとか、その感じに寄っていかないと、全然イケていないだろうな、と。
その世界観がこれからの時代に合っていると感じましたし、そういう人たちを応援したいなと。実際に関わってみると、やはり若い人への影響力はすごく強いと感じています。
──堀米選手に対しては、どんな印象をお持ちですか?
木村 それこそ、「本当に最近の子って真面目だな」と。純粋に競技を極め、うまくなりたいということだけにフォーカスしてやっているんですよ。しかもそれを、昔のスポ根的に眉をひそめながらやっているのではなくて、ひょうひょうとしていて、楽しくやっている感覚がすごいなと思いましたね。
もちろんそれは、天才的にヘラヘラと笑って、あっさりやってのけているという感じでもない。ひたむきだし、必死に、でも本当に楽しそうにやっているんですよね。
──他のことにとらわれず、純粋に競技に向き合っていますよね。
木村 そうですね。「いいトリックを決めたい」という想いを持っていますよね。もしかしたら彼が優勝しなかったとしても、他の人を讃えていたんじゃないでしょうか。純粋に、仲間もライバルも含めて、高いレベルをみんなで目指している感覚を受けますね。
──まさにXFLAGの目指すイメージを体現している選手のように感じます。堀米選手の金メダル獲得後はXFLAGへの注目も高まったと思いますが、変化を感じましたか?
木村 どこまであったかはわからないですけど、スポーツの印象がより強くなったかもしれないですね。今までだとFC東京や千葉ジェッツにロゴが入っていましたけど、それはゲームのパブリッシャーブランドとして、広告で入っているくらいの感覚が強かった。
でも、所属選手があのような成果を出してくれたことは、まるで違う意味を持ちました。他に主体があるなかの一つとしてスポンサーをしているのと、主体となって選手を輩出したのとでは、ブランドの持つイメージがだいぶ変わったように思えます。
木村社長はなぜスポーツにベットする?
──スポーツベッティングのお話も聞かせてください。XFLAGの流れからすると、どういう位置付けになってきますか?
木村 友達や仲間とワイワイ盛り上がれる場所や機会を提供するというのがmixiだったり、XFLAGだったりの役割です。それ対してスポーツベッティングは、スポーツの熱量に対して、自分の感情や熱量を“乗っける要素”が強いものだと思います。
今、アメリカでもブームが来ていますけど、日本のスポーツビジネスはいつもアメリカに先を越されて、本当に悔しい感情を持っています。totoのようなスポーツくじは先にやっていたわけですから、なぜ日本で先にできなかったのかと。
スポーツの楽しみ方にさらに彩りを加え、かつスポーツ財源としてフィードバックされていく。しかもmixiやXFLAG的にはワイドで盛り上がるということを、弊社のスポーツベッティング「TIPSTAR」で実現したいと強く思っています。
──いずれ、ベッティング事業の海外展開は考えていますか?
木村 もちろん、あり得ると思います。海外のベッティングサービスを研究していくなかで、僕らがやりたいソーシャルアプリケーションを担うサービスがまだないんですよ。
友達と勝った、負けたで一喜一憂するサービスがいまだにないので、そこにチャレンジしていきたい。コミュニケーションというものは、万国共通のニーズがありますから。
──スポーツベッティングの今後の具体的な展開、仕組みをどのように考えていますか?
木村 2つあります。一つは、「インプレイ」ですね。賭けの試行回数を上げないと売り上げは上がらないということです。たとえばtotoであれば、基本的に週1回しか賭ける機会はないですが、海外のベッティングは試合中に何回も賭ける回数があります。
やはり、試行回数を増やす「インプレイベッティング」は、日本のスポーツ関連のマネタイゼーションを考える人たちが共通してやらなければいけないと思います。
もう一つは、ソーシャルベッティングです。
私たちは1人で黙々と賭けに没頭する世界観をよしとしていません。それでは1人でパチンコ屋さんにいるのと変わらないので、本質的に進歩がないからです。やはり友達と一緒に賭ける体験ができるようになると、大きく変わるのではないかなと思っています。

──日本では、「スポーツビジネス」という言葉はあるのに、あからさまに「稼ぐ」という表現を加えると、途端に反発を受けやすくなる嫌いを感じます。日本において「スポーツで稼ぐ」という発想は、そもそも成り立つのでしょうか。今、世界的にも「未来はベッティングにある」と言われていますが、ほかにもアイデアがあるのでしょうか?
木村 その一つとして、「Fansta」みたいな、飲み屋に集まってスポーツ観戦をする場所、機会を提供したいと考えています。
特に注目したいのは、プロスポーツのアウェイ戦です。
アウェイ戦はものすごく熱量の高い人は観に行くかもしれないですけど、それ以外は自宅などで観ると思います。そういう人たちが集まって試合を観ることのできる機会を作れたら、アウェイ戦のマーケットがもう一つできるのかなと思います。
それに、スポーツチームの振興、集客、ファン獲得という観点で考えても、ユーザーとのタッチポイントとその時間を増やしていくことが重要だと思っています。
たとえばアウェイで7連戦の間は、ホームタウンがずっと静かになってしまいますよね。であれば、その期間中もホームタウンをお祭りにしてしまえば、スポーツの捉え方も変わってくるんじゃないかなと。
──その空間でスポーツベッティングも行なわれるのでしょうか?
木村 将来的にはそうですね。日本のライブビューイングのカルチャーを一緒に作っていきたいし、実際にそういうジャンルにも出資をしていたりするので。
──スポーツは、あれこれ考える必要がないくらい、本質的に素晴らしいものだと思います。だからこそ、企業としてそこに投資し、トライしていく価値があるのですね。
木村 間違いないですね。ただ日本人の場合、もしかしたらそこまでスポーツが好きな人は多くないかもしれないのですが……(苦笑)。
──オリンピックなどでも、盛り上がり方が瞬間的だったりしますからね。文化として根付いているものがあるかというと、まだまだ時間がかかるのかもしれません。
木村 そうですね。だからこそ、スポーツビジネスの難しさを本当に痛感しています。それこそコミュニティじゃないですけど、ある特定の、スポーツが好きな人たちの熱がグッと高まって、そこに集まって、ビジネスをしているような感覚はけっこうありますね。
僕が普段からかかわっているような人たちを含め、もっといろいろなビジネスパーソンがスポーツの世界に来てくれたらいいのにと思います。ただ、古参が集まっているコミュニティってなかなか入りにくいんですよね(笑)。
──だからこそ木村社長は、閉じられた「コミュニティ」ではなく、外に開かれた「ソーシャルネットワーク」に未来と可能性を感じてきたのですね。それで東京の真ん中から、「打倒・アメリカ」のような勢いでチャレンジを続けているように見えます。
木村 実は、「一番になりたい」という感覚はあまりありません。なにより「楽しい」を選んでいきたいので。でも、僕の周りにいるビジネスパーソンたちが「アメリカはこんなすごいぞ」と、自慢げに教えてくれるんです。それを見て僕は、「ああ、すごいな。悔しいな。でも、楽しそうだな」と思って、やっぱり楽しい道を探っていくんです。

■プロフィール
木村弘毅(きむら・こうき)
電気設備会社、携帯コンテンツ会社等を経て、2008年株式会社ミクシィに入社。ゲーム事業部にて「サンシャイン牧場」など多くのコミュニケーションゲームの運用コンサルティングを担当。その後モンスターストライクプロジェクトを立ち上げる。 2014年11月、執行役員就任。2020年4月より、代表取締役社長。
■関連記事
- 堀米雄斗のマネジメントに訊く! 金メダルを獲得した事務所のリアル
Follow @ssn_supersports


