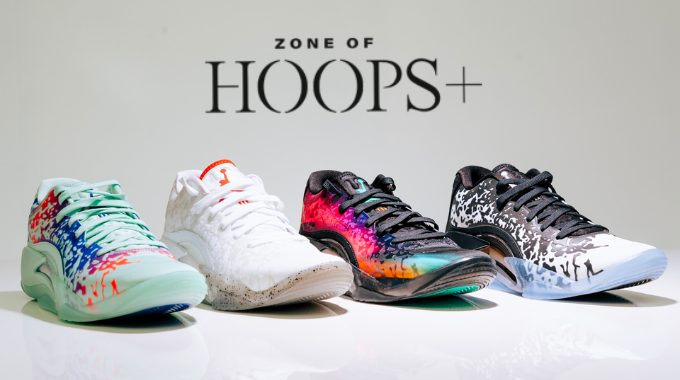言わずもがな「NBA」はアメリカ4大スポーツの一つとして位置付けられており、また世界最高のプロバスケットボールリーグと言われている存在である。
あえて「表・裏」という言い方をさせてもらうと、NBAにおける表は「試合」「スポーツの興行」であり、また「最高のエンタメ」でもあるだろう。一方でNBAにおける「裏」は、各チームが「スポーツビジネス企業」として激しい収益競争を繰り広げていることかもしれない。
それぞれのチームが収益を伸ばす・支出を減らす取り組みを数多く実施している中で、今回は一部のチームをピックアップして紹介していきたい。どんな工夫をし、どうマネタイズしているのか。
NBAのビジネススケール
世界的に有名な経済誌「Forbes」が発表した最新の球団価値ランキング(※)によれば、ゴールデンステイト・ウォリアーズ(約88億ドル:約1.3兆円)、ニューヨーク・ニックス(約75億ドル:約1.1兆円)、ロサンゼルス・レイカーズ(約71億ドル:約1兆円)がトップ3を独占。また、このTOP3は2022年から3年連続。NBAを牽引するビッグマーケットに相応しい、いや、あまりにも巨額すぎるビジネスである。
※上記は「球団の推定資産価値」であり「収益」ではない。収益については別途記載
ちなみに、ウォリアーズは2015年ほどからカリーの効果もあって圧倒的な成長を続けているが、ウォリアーズが出てくるまでは「ニューヨーク・ニックス」と「ロサンゼルス・レイカーズ」の2強だった。ニューヨークの人口は約1,900万人・ロサンゼルスは約1,300万人を有する大都市だからこその結果とも言えるだろう。いずれにしても、やはり大都市に本拠地があるチームはビジネスとしてもどうしても大きくなりやすく、特にこの3チームは放映権、スポンサー、アリーナ事業の三本柱で圧倒的な利益を上げている。
一方で近年、スモールマーケットの中にも堅実に利益を伸ばすチームが現れている。
人口規模では不利でも、地域密着型のブランディング、チケット価格戦略、デジタルマーケティングの最適化を通じて高収益を実現しているのだ。以下は、Forbesが出している収益ランキングのTOP3とワースト3をまとめたものである。
▼上位3チーム
| チーム名 | 人口 | 年間収益 | |
| 1 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 約450万人(サンフランシスコ) | 約7億6500万ドル(約1,110億円) |
| 2 | ニューヨーク・ニックス | 約1,900万人 | 約6億5000万ドル(約975億円) |
| 3 | ロサンゼルス・レイカーズ | 約1,300万人 | 約6億ドル(約900億円) |
▼下位3チーム
| 人口 | 年間収益 | ||
| 1 | シャーロット・ホーネッツ | 約330万人 | 約2.5億ドル(約375億円) |
| 2 | ニューオリンズ・ペリカンズ | 約100万人 | 約2.8億ドル(約420億円) |
| 3 | オクラホマシティ・サンダー | 約70万人 | 約3億ドル(約450億円) |
全体トップのウォリアーズの収益は、最下位のホーネッツの約3倍である。これは決してシャーロットを下に見ているわけではなく、純粋にウォリアーズが凄すぎる。ホームアリーナであるチェイスセンターをフル活用していること、またカリーというわかりやすいスターがいること、そして直近10年で複数回の優勝をしていること、そして大都市を拠点にしていること。これら複数のポジティブ要素が掛け算となってこの形になっている。
新アリーナがあり、カリーというアイコンがいるおかげで新規ファンも取り込みやすく、ユニフォームを始めとするグッズは飛ぶように売れるため客単価が非常に高い。強いチームを応援したいとスポンサーも集まる。こんな好循環が同時多発的にサンフランシスコでは起きている。
一方で、収益のワースト3位に入っているオクラホマシティは、2024-25シーズンの優勝チームである。これが非常に面白いところ。極端で乱暴な言い方だが、全然売れてないのに強いということである。競技力は人気と比例することが多いものの、マーケットがそもそも小さい。オクラホマシティは人口約70万人の都市であり、農地・牧草地が広がるような、いわゆる”田舎”である。そもそも日本からオクラホマ州への直行便はないため、テキサスのダラスで飛行機を乗り換えるか、シカゴorロサンゼルスでトランジットするしかない。目立った観光地もないため観光客がそもそも少ない。
ネガティブをあえて並べたが、この「アクセスの悪さ」が地元密着の強さにもつながっているし、そもそも物価が安く治安も良いために生活がしやすい。のどかな生活を送りたい人や選手にはピッタリでもある。
さらにいうとオクラホマシティは「スポーツ不毛の地」として知られているため、サンダーの優勝は市民に驚きを与え、またたく間に圧倒的な支持を得た結果になった。
Scenes from OKC's victory parade 🏆
Photo: OKC/NBA pic.twitter.com/YOrSpt5yYE
— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) June 25, 2025
スモールマーケットだからと言って勝てないことではないし、必ず赤字になってしまうということでもない。次章からは、儲かっているチームがなぜ儲かっているか。スモールマーケットのチームが生き抜くためにどんなことをしているかを紹介したい。
儲かっているチームTOP3の収益構造
まずウォリアーズ。サンフランシスコにホームアリーナ「チェイス・センター」を建設して以降、チケット収益だけでなくイベント・不動産・飲食など周辺事業も取り込み、NBAで最も高い営業利益率を誇る。アリーナビジネスが上手く回っているということである。テック企業が集中するベイエリアの経済圏を背景に、観客単価はリーグ平均(約53ドル(約8,000円))の約2倍(約100ドル(約16,000円))(※)。スポンサーにはGoogleやAdobe、そして日本の楽天といったIT企業が名を連ね、スポーツ×テクノロジーの象徴的存在となった。
続くニックスは、ニューヨークという世界最大級の市場を武器に、ブランド価値そのものが収益を生む稀有なチームだ。そもそもニックスはNBA創設の1946年からずっとニューヨークに腰を据え、そしてマディソン・スクエア・ガーデン(以下MSG)をホームアリーナにし続けているため、80年近い歴史がある。よって、ニューヨーカーはバスケ好きが多い。応援も他チームとは比べものにないほど。
本拠地のMSGは常に満員で、放映権を持つMSGネットワークとの相乗効果が大きい。成績が安定しない時期でも赤字を出さないのは「都市ブランド」として確立された存在感の賜物だ。
現在、日本のスーパースターである八村塁が所属するレイカーズは「スター選手の経済効果」を最大限にビジネスへ転化している。レブロン・ジェームズやかつてのコービー・ブライアントなど、象徴的存在を中心としたグローバルファン戦略が奏功。チームは自前の放映権ネットワーク「Spectrum SportsNet」を通じて安定した広告収入を確保し、世界的なライセンスビジネスでも群を抜いている。
This #BlackHistoryMonth, we’re highlighting The Vegan Hood Chefs, a Black-owned Taste Maker specializing in vegan soul food and American Classics
Give these delicious Vegan Poke Nachos a try next time you visit Chase Center!
📍Taste Makers Portable Eatery by Portal 48 pic.twitter.com/c1DqtPzeyF
— Chase Center (@ChaseCenter) February 28, 2024
チケット、グッズ、飲食などで、1家族あたり5万円〜8万円が平均単価であるため、さまざまなイベントを凝らして飽きさせない工夫をしている
”田舎”でも堅実に成長を続けるチームとは?
一方で、人口規模では不利なスモールマーケットにも堅実な成功例がある。
その代表がミルウォーキー・バックス。2018年に開業した新アリーナ「Fiserv Forum」は、地域経済を巻き込む複合施設として機能しており、NBAでは珍しく「都市再開発モデル」に近い経営を行う。チーム強化と街の活性化を結びつけたことで、スポンサー収入は10年前の約2倍に増加した。
また、サンアントニオ・スパーズは、過去の優勝経験によるブランド資産を生かしながら、育成型チーム経営を貫く。地元コミュニティとの結びつきが強く、観客のロイヤルティ(継続率)はNBA随一。華やかなスター不在でも安定黒字を維持できるのは、コスト構造の最適化と、徹底したファン基盤の強化があってこそだ。メンフィス・グリズリーズも、SNSを駆使した“若者目線”のブランド発信でスポンサー単価を伸ばしている。Z世代に特化したデジタル戦略を展開し、都市規模に反して高いエンゲージメントを実現した稀有な例だ。
What would you want to see added to Fiserv Forum and/or the Deer District? pic.twitter.com/wqSGp4QY8n
— Bucks Lead (@BucksLead) August 2, 2025
バックスの「Fiserv Forum」は、見ての通り周辺に高い建物がなく存在感がある。アリーナが地域のアイコニックな存在にもなっている
この3チームに共通しているのは、そこまでチケット単価が高くないし観客収入も多くないこと。そして支出を抑えた効率的なチーム運営をしていること。要するに、若い選手を上手く獲得するためにドラフトで上手く立ち回ったり、将来性がありそうな若手選手を引っ張ることで、支出を抑えているということ。ただ、どうでも良い選手を獲得しているわけではなく、GMが徹底的にスカウティングを重ねて欲しい選手を獲得している。
オクラホマシティ・サンダーが非常に良い例だが、彼らは現在所属しているコアメンバーの多くをドラフトで指名したり、またトレードで安価で獲得したりした。シェイ・ギルジャス・アレクサンダーが、ここまで活躍すると誰が予想したか。
スモールマーケットは特に、安くてポテンシャルのある、ルーキースケールの選手を獲得して若いケミストリーを高めていく。コスト抑制と地域密着、またドラフト戦略など、あらゆる企画を立て実行しているが、同時にスモールマーケットをしっかり経営できる、”コスパ経営”を上手く実行できるかが非常に鍵を握っている。そして獲得した選手をしっかり教育できる環境を整えてあげること、選手が育った先の未来まで考えられるかが重要だ。
収益上位ならびに下位でも、成功チームには、いくつかの共通点が見えてくる。
| 1 | 自前アリーナを持つこと | イベントやコンサートを自ら運営できるため、NBAシーズン以外の収益を確保できる。ウォリアーズやバックスは典型例。 ※建設後の収益最大化に向けた動きも非常に重要である |
| 2 | デジタル×グローバル戦略 | SNSや配信サービスを通じて“ファンの国境”を取り払う。レイカーズは世界的スポンサーを呼び込む仕組みを確立している。 |
| 3 | ブランド経営の徹底 | スター選手や地域文化を「ストーリー」として発信し、ファンの共感をビジネス価値に変換している。 |
NBAの収益構造は、もはやチケットとグッズだけでは語れない。
都市のブランド、デジタルの浸透、そしてファンとの心理的距離……。それらすべてが利益に直結する時代となった。
トップチームは“スポーツクラブ”ではなく、“都市型メディア企業”として機能しているのだ。そして、ミルウォーキーやメンフィスのような地方都市の成功例は、その構造を地方に最適化した「ローカル経営モデル」として注目に値する。競技の勝敗を超えて、いまNBAは“ビジネスとしてのスポーツ”を最も高い次元で体現するリーグになっている。
最後に。アリーナビジネスの成功事例は日本のBリーグでもしばしば参考にされている。ウォリアーズのチェイスセンターの座組みを参考にしているのは、千葉ジェッツのららアリーナTOKYO-BAYである。不動産主導で進んでいることや、商業施設、ホテル、そしてスポーツツーリズムが一体化している場所は、ウォリアーズのチェイスセンターが建設されたコンセプトと同じである。
また、ミルウォーキーやメンフィスのように、地方創生・官民連携でしっかりとローカル経営をしているのは、広島ドラゴンフライズである。広島駅周辺の再開発やチームが希望の光となり地域経済の象徴になった。飲食や観光ともに一体感を生み出せる場所がアリーナなのだから、それぞれのエリアごとに、アリーナがどのように使われているか注目するのもきっと面白いはずだ。
【参考】
https://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2022/10/27/nba-team-values-2022-for-the-first-time-in-two-decades-the-top-spot-goes-to-a-franchise-thats-not-the-knicks-or-lakers/
https://www.thescore.com/nba/news/2746994
https://investor.msgsports.com/press-releases/news-details/2025/MADISON-SQUARE-GARDEN-SPORTS-CORP--REPORTS-FISCAL-2025-THIRD-QUARTER-RESULTS/default.aspx
NBA Average Ticket Prices: Knicks, Lakers Have The Most Expensive Tickets In 2024-25
Follow @ssn_supersports